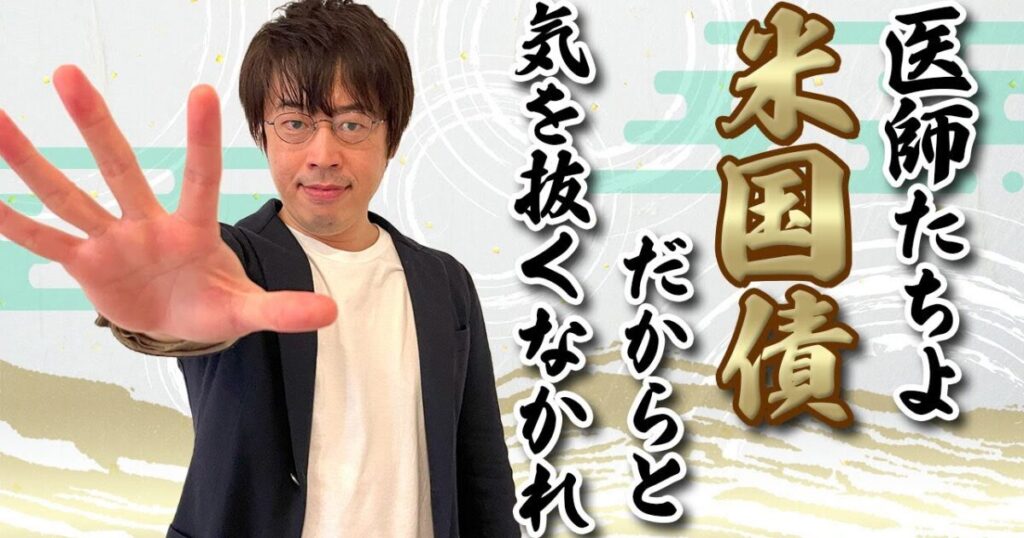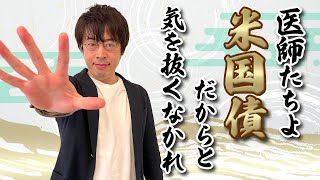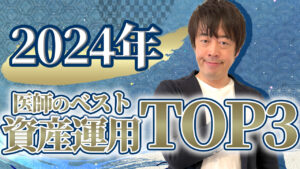目次
はじめに
皆さん、こんにちは。株式会社ウェルス・パートナー代表の世古口です。
本日のテーマは、「【検討者必見】医師に必ず知って欲しい米国債の投資リスク」です。
医師の先生の場合、米ドル債券に投資される際は、特に安定性を求めて運用したい方が多いため、米国債に投資することが非常に多く見られます。あらゆる米ドル建て債券の中で、最もリスクが低く安定的に運用できるのが米国債のイメージかと思います。
ただし、投資商品ですので、当然いろいろなリスクはあります。米国債だからということで安心して投資してしまい、リスクなどをあまり考慮せずに投資されている先生もいらっしゃるのではないかと思うので、今回は医師の先生に、投資前には必ず知っておいて欲しい米国債の投資リスクについて分かりやすくご説明します。
▼今回の内容はYouTubeでご覧いただけます
投資リスクまとめ
本題の米国債の投資リスクをまとめました。主なリスクは4つあると思います。
為替評価損失→米金利低下・円金利上昇など
為替評価損失をご理解いただいている先生は多いのではないかと思います。米国債は米ドル建てですので、為替リスクを負っている投資です。ですから、米国債に投資したときから米ドル安円高にいったとすると、為替が下がった分(米ドル安になった分)損失が発生します。円評価に引き直すと損失が発生することになるので、この為替評価で損失が出るというのが、リスクとしては大きいのではないかと考えます。
特に、米国という世界で一番の国が発行している債券なので、米国が倒産する確率は、統計上、非常に低いと考えると、やはりこの米国債において、一番起こりやすいリスクは、為替評価損失といえます。繰り返しますが、投資したときよりも米ドル安円高にいったとすると、その分は、円評価で見直すと損失になっているという部分が、この為替評価損失なのです。
どのようなことで為替評価損失が起こるのかというと、一番分かりやすいのがアメリカの金利低下です。金利が高い国の通貨に資金が集まりやすいので、アメリカの金利が上がると米ドル高円安になりますが、アメリカの金利が低下傾向にあると、米ドルから資金が逃げるので、米ドル安円高になって為替評価損失が出やすくなります。
もう一つの現象としては、円金利の上昇です。円の金利が上がると、比較的米ドルから円に資金が移るので、円の金利が上がることによる米ドル安円高ということも考えられます。そのようなことによっても、為替評価損失は出るのです。
為替に関しては、ありとあらゆる要素によって為替評価が決まります。アメリカと日本円の金利差だけでなく、いろいろなことで決まるので一概にはいえませんが、為替評価損失が出る可能性はそれなりにあると考えておく必要があると思います。
債券価格下落→アメリカの金利上昇・財政不安
2つ目の投資リスクは債券価格下落です。これも当然考慮すべきリスクかと思います。米国債においても債券の価格があります。最初に米国債が発行されたときは、価格は100ですが、満期まで保有した場合、満期が5年だとしたら5年後に価格が100になって戻ってきますが、保有している間は債券の価格は毎日動きます。
ですから、100が90に下がったり、110になっていたり、80まで下がっていたり、発行されてから債券の残存期間が終わるまで、満期に向かって100にいく過程で、値動きが発生するので、持っている間に債券価格が下落するという可能性があります。この債券価格下落も、時価ベースで米国債を評価したときは当然マイナスになるので、そのような投資リスクもあるわけです。
お伝えしたように、満期まで保有していれば債券価格は100で戻ってきます。最後まで持ち切れば、債券価格が一時的に下落していても100まで戻ってくるので、債券価格におけるリスクはないといえるのですが、万が一債券価格が下落しているタイミングで売却した場合は、その損失が確定するので、考慮すべきリスクの一つといえると思います。
では、どのようなことによって債券価格は下落するのでしょうか。アメリカの金利上昇が一番分かりやすい例ではないかと思います。経済の仕組みとして、アメリカの金利が上がると基本的に債券価格が下落し、金利が下がると既に存在している債券の価格は上昇する、という理屈で動いています。ですから、債券価格が一番下落しやすいイベントは、アメリカの金利が上がる金利上昇です。これによって起こる可能性が高いと思います。
もう一つは、アメリカの財政不安です。例えば、アメリカがたくさん国債を発行し続けていると、「アメリカの財政は大丈夫?」と皆が思うでしょう。すると、そのような不安によって米国債を売却するという動きに繋がるので、それによる債券価格下落も可能性としてはあるわけです。
ただ、アメリカの格付けがAA+で世界一大きな国ということを考えると、財政不安よりは、最初にお伝えしたアメリカの金利上昇による債券価格下落が起こり得る可能性が高く、一番先に懸念すべき事項ではないかと思います。
投資資金全損→アメリカの財政破綻・経済崩壊
3つ目の投資リスクは投資資金全損という、米国債に投資した資金が全部損失になるという大変な事態です。投資金額が1,000万円であれば1,000万円が全部返ってこない、1億円であれば1億円が全部返ってこない、このようなことが米国債でも起こり得るのかと考えると、起こる確率は極めて少ないでしょう。起こらないと思いますし、確率はすごく低いですが、起こる可能性も一部あるというのがこの投資資金全損です。
どのような投資商品においても、そのようなリスクは一定程度あります。どんな投資対象でも、全て損失になる可能性はやはり一部はあるわけです。
では、どのようなときに米国債投資において全損ということが起こり得るのでしょうか。やはり一番はアメリカの財政破綻です。経済が崩壊してアメリカという国がおかしくなってしまい、「もうこれ以上米国債を発行できない」「お金も返せない」「利息や元本も返せない」など、過去のギリシャのような状態になったり、実際に破綻している国、アルゼンチンのようになったりするときは、全部損失になるのではなく、一部返ってくる可能性の方が個人的には高いと思います。
ただし、本当に返せるお金がなくなるほど大変な状況になったとすると、当然全損の可能性もあります。そのようなことになる確率は極めて少ないと思いますが、やはりリスクがある資産に投資するということは、全損になる可能性も一部あると考えて投資するべきではないでしょうか。
流動性低い→投資後すぐ売却すると損失出る
投資リスクの4つ目は流動性が低い点です。流動性が低いといってもそれほど低くはありません。仮に購入した後に売却したとしても、米国債で流動性が大きく下がることはあまりないので、1週間ほどで換金できます。ただし、購入した後や投資した後にすぐに売却すると、損失が出る可能性が高いです。
米国債においても、基本的に債券は相対取引で売買しているので、売る人と購入する人、当然売値と買値があります。売値と買値は基本的に離れていて、購入した後にすぐに売却すると、証券会社の手数料なども入り、買値と売値の差もありますから、流動性の低さによって損失は出るという意味で、流動性は少し低くなっていると思います。
例えば、世の中に存在している時価総額が何千億円以上あるような大企業の株式と比較すると、売値と買値が離れていない可能性が高いので、上場している大企業の株式よりは流動性が低いということはいえると思います。大きな投資リスクではないかもしれませんが、ただ一つ、流動性が低いという意味において、米国債に投資することによって流動性リスクを負っているとご理解いただければと思います。
以上が、医師の先生に投資前に必ず知っていただきたい米国債の投資リスクのまとめでした。
米国債投資前4つの心得
最後に、実際に米国債に投資する前の4つの心得をお伝えしますので、参考にしていただければと思います。
米国債は他の米債より信用あるがリスクは当然ある
米国債という債券は、他の米ドル建て債券よりは当然信用力はあるのですが、当然いろいろなリスクがあると捉えるべきかと思います。米国債だから安全と思い切るのは危険ということです。
他発行体へのリスク分散も検討した上で投資実行
米国債だけでなく、他の発行体にリスク分散することも検討した方がよいと思います。やはり米国債だけでは、アメリカという国の財政に発行体のリスクが集中しすぎてしまいます。よほど米国債だけがよいということでないのであれば、格付けが米国債同等に高い企業が発行している社債にリスク分散して投資するなど、リスク分散を図った方が基本的にはよいと思います。そのようなことをした方がよいのかどうかをしっかり検討した上で、米国債に投資するかを決めるのが大事かと思います。
医療法人の資産運用の場合、一番保守的な運用であると考えて、米国債だけで運用するという決断を即決されても仕方ないと思います。個人の方や資産管理会社の運用であれば、基本的にはオーナー様や個人の方の意思一つで決められるので、「本当に米国債だけでよいのか」を自分の胸に聞いて決めていただくのがよろしいかと思います。
長期投資で損益分岐為替を切り下げ円高リスク中和
米国債の最大のリスク、一番懸念すべきリスクは為替リスクです。投資したときよりも米ドル安円高になるという為替リスクが一番大きいと思います。その為替リスクに関して、どのようにリスクヘッジするかというと、1年・2年・3年・5年などの短期間の投資ではなく、10年・20年・30年という長期間、米国債に投資します。毎年の利回り分、債券投資による利益が入ってくるので、仮に投資してから米ドル安円高にいったとしても、トータルの債券投資の利益で考えると、プラスマイナスゼロになると考えることができます。
長期投資であればあるほど、米ドル債券のトータルの利益を考慮したときの損益分岐為替が円高の方向に切り下がっていきます。長期で投資することによって、損益分岐為替を切り下げ、円高リスクを中和するのが基本戦略になってくると思います。
利回り4%で毎年運用すると想定した10年後の損益分費為替は(計算していないので正確には分かりませんが)、100円前後になったり、20年後は70円前後になったり、30年後は50円前後になったり、このように損益分岐為替は徐々に切り下がっていくことになります。ですから、米国債投資においては、やはり長期投資を前提に、円高リスクを中和しながら運用していくのがよいと思います。
長期債で債券価格と為替評価に逆の動きをさせる
先ほどの投資リスクでお伝えした、為替の評価損失という米国債のリスクと債券価格の下落、この2つのリスクを、逆の動きをさせることによってリスクヘッジするという考え方があります。
基本的に米国債や米ドル円の為替に一番影響を与える指標は、アメリカの金利です。アメリカの金利が上がったとすると、債券価格は下がります。金利が上がると為替は上がるので、米ドル高円安になります。アメリカの金利が上がったときは債券価格は下落していますが、為替は米ドル高円安なので、この債券の価格と為替で、例えばプラスマイナスゼロになると考えることができます。
逆に、アメリカの金利が下がったとすると、債券価格は上がります。為替は米ドル安円高にいく可能性が高いので、金利が下がったときは、債券価格は為替でプラスマイナスゼロに相殺されます。
このように、10年以上や20年のある程度期間が長い債券を保有することによって、債券価格と為替評価に逆の動きをさせることで、仮に米国債を時価評価したときの価格を安定させることができるので、そのようなリスクヘッジの方法が考えられると思います。
本日は「医師に必ず知って欲しい米国債の投資リスク【検討者必見】」という内容でお届けさせていただきました。

株式会社ウェルス・パートナー
代表取締役 世古口 俊介
2005年4月に日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイスのプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。
2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。超富裕層のコンサルティングを行い1人での最高預かり残高は400億円。書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者1万人超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」での情報発信を通じて日本人の資産形成に貢献。医師向けサイトm3.comのDoctors LIFESTYLEマネー部門の連載ランキング人気1位。
メディア掲載情報:「m3.com」「ZUU online」「MONEY zine」「マネー現代」でコラムを連載中