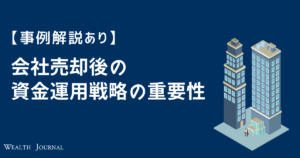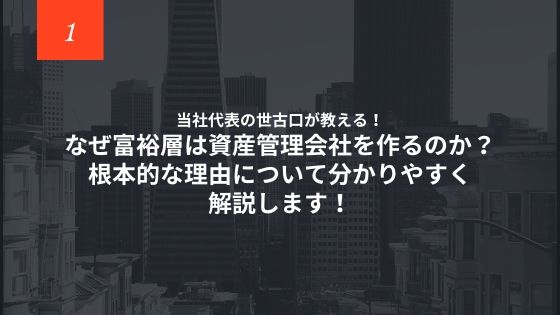
こんにちは。ウェルスパートナー代表の世古口です。私は大学を卒業した2005年からこれまでの15年間、富裕層からお金をお預かりして資産運用する仕事をしてきました。
最初の11年間は日系、アメリカ系、スイス系の金融機関のプライベートバンク部門のプライベートバンカーとして、直近の4年間は独立して資産運用コンサルティングの会社を経営しています。
そういった中で、資産運用の相談と同じくらい多いのが資産管理会社の設立・運営に関する相談です。なぜ富裕層は資産管理会社を作るのでしょうか。
富裕層が資産管理会社を作る理由から具体的な活用方法、税制までを詳しく連載でご紹介できればと思います。
個人より法人が有利な日本の税金
連載1回目は富裕層が資産管理会社(以下、法人)を作る根本的な理由をお話ししたいと思います。皆さんは日本の税金の状況をご存知でしょうか。
個人の所得税と住民税の最高税率は55%、一方で法人税の実効税率は30%です。端的に言うと、この税率25%の差が個人ではなく、法人を設立する理由です。
報酬や利益など個人で受け取るよりも、法人で受け取った方が税率上は有利になるということです。
また最高税率に加えて、法人には幅広い損益通算が認められています。事業に使われたありとあらゆる経費を利益と相殺することができるのです。
これが個人だと所得区分が複雑に分かれており、自由に損益を通算することが困難です。端的に言ってしまうと売上をあげるなら個人より、法人で上げた方が損益通算の幅が広く、最高税率も低いので、全てにおいて有利なのです。
しかし、なぜここまで法人の税金は有利なのでしょうか。それは法人税率は上げすぎてしまうと企業が海外に拠点を移してしまうからです。法人税率の戦いは海外の諸外国なのです。
そして、アメリカはトランプ減税により2018年に法人税(連邦税)を35%から21%に引き下げました。世界で一番GDPが大きい国が大幅に税率を引き下げたのです。日本も追随せざるを得ません。
個人の消費税、所得税、相続税、贈与税は今後も上昇する可能性が高いです。一方で法人税だけは世界との戦いの中で今後も下がっていくことが予想されています。これが富裕層が法人を作る本質的な理由です。
法人を作って何をするの?
では法人を作ってから具体的に何をするのでしょうか。簡単に言うと「個人の収入、資産を法人に移転する」のです。それは何の収入でも大丈夫です。
例えば現在、勤めている会社から受け取っている給料を法人と業務委託契約に切り替えてもらって業務委託報酬として法人収入として受け取る。副業の収入を個人ではなく法人で受け取る。個人で所有している不動産を法人に所有権移転する。個人で所有する金融商品を法人に譲渡する。など、法人に移せる収入は意外と多くあります。
注意点としては、個人の給料を法人契約の業務委託報酬に切り替えることは支払元の会社がそれを承諾する必要があり、大企業だと難しいケースが多いです。
比較的に人事制度が柔軟なベンチャー企業や中小企業では受け入れられるケースも多いのです。なぜなら受け入れられるかというと、中小企業にもメリットがあるからです。
会社は給料の約15%に該当する社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)を負担しています。この社会保険料は会社に戻ってくるわけでもなく、社員に還元されるわけでもなく、ただのコストなのです。こういった負担が必要ない業務委託の方が良いという判断をする会社も存在します。
あと個人から法人への報酬移転が難しいのがお医者様です。お医者様の医療行為は医師免許を持っているお医者様個人だから許されるからです。
その医療行為の対価を法人で受け取ることは難しくなります。個人のクリニックや小さい医療法人はその辺りの感覚が緩く、お医者様の法人に報酬を出しているケースに直面することもありますが、リスクがあるので報酬を個人に戻すことをお勧めしております。
ともかく報酬であれ、運用益であれ法人に移転することができれば様々な税制上のメリットを得ることが可能と言えます。法人を作って行うことは、個人から法人に収入や資産を移転することです。
法人を活用するにあたり何を考えなければならないか
法人を作るにあたり、まず合同会社か株式会社かという選択肢があります。その法人の資本金をどうするか、株主構成や役員をどうするかということも同時に考える必要があります。
そして会社を作ったあとは資産を個人で所有するか、法人で所有するかということを考えなければなりません。
資産も不動産か金融資産かにより、個人の税率も異なるので、別々に保有主体を検討する必要があります。不動産を個人で所有するか、法人で所有するかは実は難しい判断です。
不動産には減価償却という所得税を下げる効果があり、個人で所有した方が良いこともあります。あと金融商品を個人、法人どちらで所有するかも詳しい検討が必要です。税率だけで考えると金融商品の個人の税率は20%に対して法人は30%と高くなります。
それでも法人で運用した方が良いケースも多くあります。また不動産の所有は相続対策に直結するので、それも同時に考える必要があります。
以上のように法人の活用が有効なことは間違いありませんが、実は考えなければならないことがあまりに多くあります。本記事は富裕層が法人を作る根本的な理由というテーマでしたが、今後の連載ではご紹介した法人活用の論点や事例について、一つずつ紹介していきたいと思います。