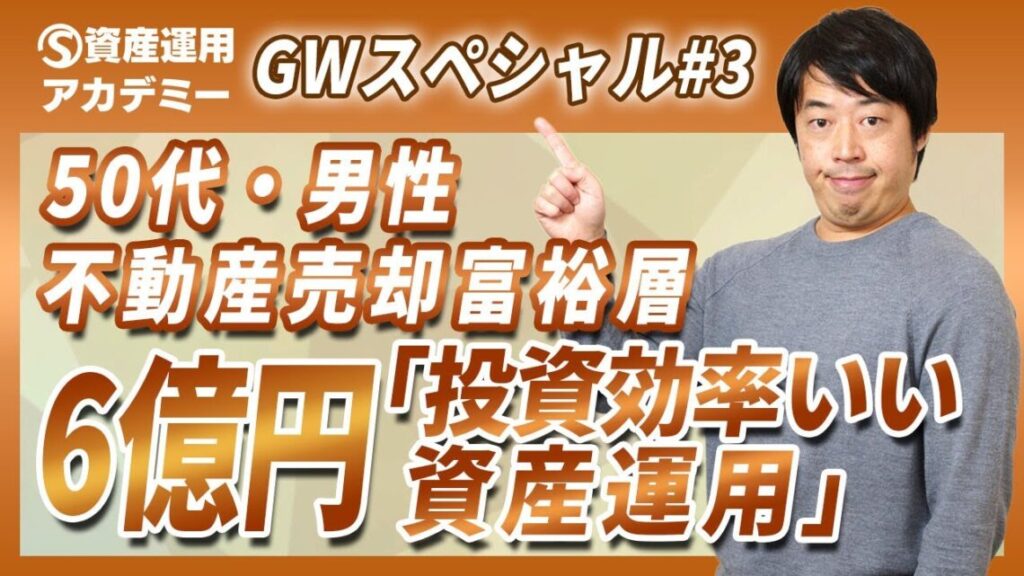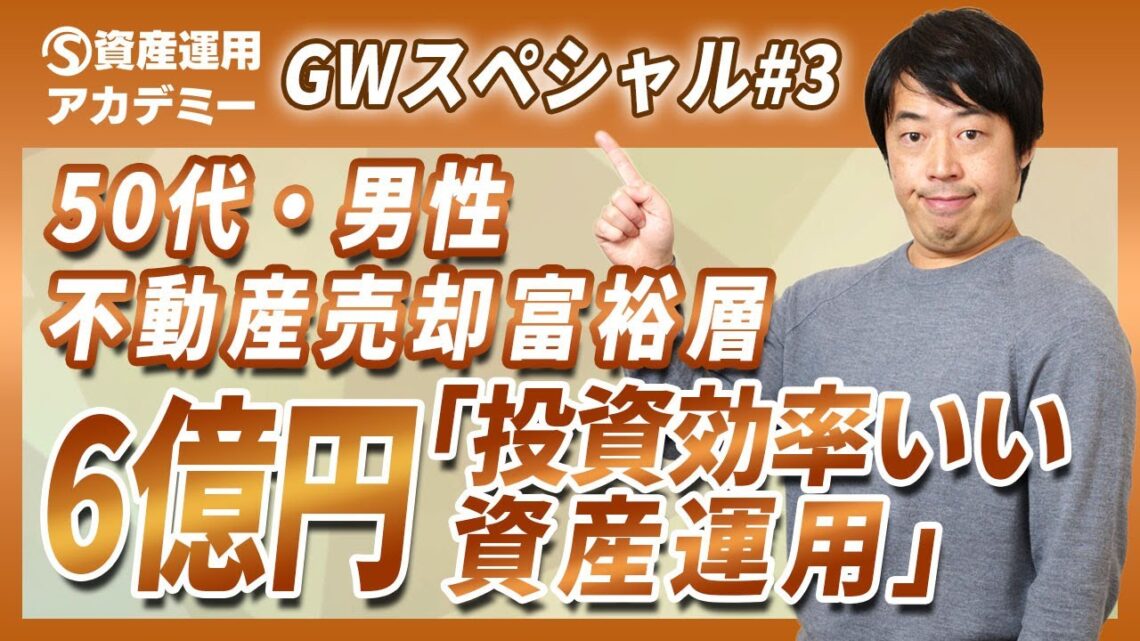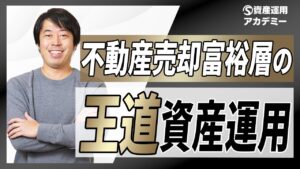こんにちは。株式会社ウェルス・パートナー代表の世古口です。
今回は【不動産売却富裕層】の方の資産運用実例をご紹介します。
今回の不動産売却富裕層のお客様は、「借入を使って運用したい」という強いご希望を持っていました。
もともと不動産投資をされていた方の場合、借入を伴った投資が多いです。そのため、不動産をお持ちだった富裕層の方にとってレバレッジは一般的なもので、金融資産を今後運用する際もそういったものを活用して運用したいというご要望が多くなっています。
そこで今回はレバレッジ重視の資産運用実例をご紹介しますので、皆様の参考になればと思います。
目次
不動産売却富裕層6億円のレバレッジを重視した資産運用実例|当初の資産配分
まずはこの不動産売却富裕層の方の資産配分状況を見ていきます。
性別は男性で年齢は50歳代後半、家族は奥様とご長女様がいらっしゃいます。
職業は会社員で年収は2,700万円とかなりの高収入です。日本国内に1.7億円のご自宅と7.1億円の投資用不動産を所有していらっしゃいます。
金融資産は日本株式と先進国株式をいくばくか持っています。債券も、日本債券と先進国債券を1,000万円ずつです。
金融資産の中心は現金預金6.5億円になっています。この6.5億円はもともと所有していた不動産を売却して入ってきた分です。不動産はもともと2棟所有しており、そのうちの1棟を売却したそうです。
不動産は、8.8億円の国内不動産で、ローンは1.2億円という状況になっています。
資産全体のバランスとしては、借入はあるのですが、借入比率は108.1%とさほど高くありません。それほどレバレッジがかかっていない状態だと言えます。
金融資産と実物資産の割合は、それぞれ45%と55%です。外貨の比率が約3%で、株式と債券の割合がそれぞれ6.8%と2.8%になっています。
この不動産売却富裕層の方のご要望は次の3つです。
- 不動産売却代金である6億円を有効活用したい
- 流動性の高い金融資産だけで運用したい。不動産は現在所有しており、ここ10数年で不動産は上昇傾向でもある。現状では不動産にこれ以上投資したくない
- 金融資産だけで運用したいが、無理のない範囲でレバレッジをかけたい
不動産売却富裕層の方の場合、また不動産に投資したいという方より金融資産に投資したいという方が最近結構多いです。ずっと不動産をお持ちだったわけで、今までどのように推移してきたというのもよく理解されています。
不動産がずっと上昇してきて、今また不動産投資したいというよりは、今は売却して金融資産で運用し、また不動産価格が下落したときに金融から不動産に移して投資したいというご希望の方が最近だと多いです。
不動産売却富裕層6億円のレバレッジを重視した資産運用実例|資産再配分後
不動産売却富裕層のお客様の資産状況やご要望を分析して資産再配分させていただいたのが上の表です。
使ったのは現金預金6.1億円です。
増加したのが日本株式や先進国株式、先進国債券などです。
- 日本株式:1,500万円
- 先進国株式:3,500万円
- 新興国株式:1,500万円
- 先進国債券:7.5億円(国内ローン2.5億円)
- 外国REIT:1,000万円
- オルタナティブ:2,000万円
- コモディティ金:1,500万円
日本株式と先進国株式、新興国株式はすべてインデックスファンドです。
それから先進国債券は個別の米ドル債券ポートフォリオなのですが、実はこの債券を担保にして借入を行っています。この借入2.5億円を含めた債券投資金額が7.5億円です。債券自体に出している資金が5億円。そこに国内ローン2.5億円を加えて7.5億円を投資しているというかたちになっています。
後は外国REITに1,000万円、オルタナティブ2,000万円がヘッジファンド。コモディティ金1,500万円が外国ETFです。多少オルタナティブに分散して投資するかたちになっています。
そうすると、資産全体のバランスも変わってきます。
再配分後の資産全体のバランス
総資産合計が借入を使ったことで膨らみ、借入比率は108%から125%に高まりました。投資効率も高まっています。
金融資産と実物資産の比率は51.6%と48.4%です。大体半々くらいになっています。
外貨の比率は60.3%ですので、やや円安を予想して外貨比率高めの水準になっています。これは証券担保ローンを使って債券の割合を増やしたので、このようになっているわけです。40%〜60%であれば、外貨比率は許容範囲かなと思います。
株式の比率は11.9%で、債券の比率は80.7%です。
株式と債券の比率で言うと保守的な運用を行っていますが、ただ、債券のところにレバレッジをかけていますので、ここの部分で比較的リスクを取っていると言えるのではないかと思います。
今回のポイントは金融資産だけで運用していて、その中でも先進国債券に5億円(大半)を出していて、そこにレバレッジ(借入)2.5億円を使って、7.5億円で運用しているところです。
ROE利回り&担保時価下落余力シミュレーション
「金融資産にレバレッジをかけて運用している」という点にもう少し注目して考えていきたいと思います。
こちらの表は先ほどの5億円の先進国債券の部分だけ切り取った分析です。その前提で読み進めていただければと思います。
5億円の債券を担保にして借入を行ってまた投資するということを行っていますので、これをレバレッジをかけた運用と言いますが、このレバレッジには当然リスクも伴うわけです。
レバレッジをかければかけるほど、借りて投資すればするほど、期待できるリターンも高くなりますが、同時にリスクも高くなります。その兼ね合い(落とし所)をどこにするかが非常に大事になってくるわけです。
その落とし所の探り方を分かりやすくお伝えできればと思います。
レバレッジとリスクの落とし所の探り方
表はROE利回りという「自己資金に対する利回りがどのくらいかという水準」と、担保時価下落時余力です。
証券担保ローンの担保にした債券(担保)の価値が下がり過ぎると担保割れになってしまい、追証になります。資産を全部売却するとか、追加で担保を差し入れなくてはいけない状況になってしまうわけです。
そういった期待できる自己資金対比の利回りと、なってはならない担保割れの水準までの余力を表したシミュレーションがこの表になっています。
表は3列になっており、5億円にレバレッジを1.3倍かけた場合(借入1.5億円で合計6.5億円)、1.5倍かけた場合(借入2.5億円で合計7.5億円)、1.7倍かけた場合(借入3.5億円で合計8.5億円)になっています。
表の3列は自己資金、担保資産、担保資産(債券)の格付けは同じです。借入比率(レバレッジ比率)が違っており、それに伴って借入金額も変わっています。借入金利はすべて同じで1.9%です。担保時価合計は借入を多くしているほど大きくなっています。
債券利回りは、基本的に投資する債券が同じなので、4.7%とすべて同じです。表のその下、ROE利回りのところから違います。
ROE、つまり借入している分も運用していて、債券の利回りが4.7%で借りたお金の金利が1.9%ですので、この差の2.8%が借入をして投資している経済効果になっています。その分、自己資金に対する全体の利回りが結構高くなっているのが特徴です。これがレバレッジをかける効果になります。
レバレッジ1.3倍だと、自己資金5億円に対する利回りは5.5%です。レバレッジ1.5倍だと利回りは6.1%、レバレッジ1.7倍だと利回りは6.7%になります。このようにレバレッジをかければかけるほど、自己資金対比の利回りは高まっていきます。
表のその下がマージンコール(MC)です。これは担保価値が下落したときにどれくらい下落余力があるかを測る基準になっています。
担保時価の下落余力はレバレッジ1.3倍のときに62%、1.5倍のときに44%、1.7倍のときに31%です。
レバレッジ比率が高くなればなるほど、当然たくさん借りているということになりますので、担保時価下落余力が低くなります。
レバレッジとリスクの落とし所としてどれがいいのか
レバレッジとリスクの落とし所としてどれがいいのかという話ですが、これはご本人様が求める期待リターンがどれくらいで、どれくらいであれば価値下落に耐えられるかという読みの兼ね合いで決めるべきかと思います。
今回ご紹介している不動産売却富裕層の方の場合、期待リターンが6%くらいでした。そこを基準に考えると、レバレッジ1.5倍か1.7倍になります。
担保時価下落余力もそれなりに欲しいというお話だったこと、私たちも40%くらいは担保時価下落余力があった方が良いと思っていたこともあり、レバレッジ1.5倍がちょうど良い落とし所ではないかという話になりました。
担保時価下落余力30%は、下がるときも結構あるわけです。円高に急速に行ったりだとか、債券価格が急に下落したりだとか。債券価格の下落と急な円高の合わせ技だとか。そうすると結構30%を切る可能性はありますので、40%は欲しいところです。
ご本人様の期待利回り6%くらいと担保時価下落余力の兼ね合いで、レバレッジ1.5倍くらいがいいのではないかという結論になりました。
不動産売却富裕層6億円のレバレッジを重視した資産運用実例|まとめ
今回の不動産売却富裕層6億円、レバレッジ重視の資産運用についてまとめます。
ポイントは4つです。
ポイント①金融資産だけで運用する不動産売却富裕層は多い
これはあくまで傾向なのですが。
日本の不動産は直近10数年くらい相場が上がり続けているという事情があります。
上がっている局面だからこそ「ちょうどいいタイミングだ」と思い売却されていると。それによって多額のキャッシュを得た方が結構多いですので、この後また不動産に投資するのは条件が合わないという方が多いわけです。
それよりも今は金融資産で流動性を保ちながら運用しておいて、また不動産が買い時になったら金融資産を売却して不動産で運用するという想定で、現状は金融資産だけで運用する方が結構多いのではないかと思います。
ポイント②証券担保ローンで投資効率を高める希望も多い
不動産を運用されている方だと借入(レバレッジ)が当たり前です。それで投資効率を高めるという発想が日常的になっているからこそ、金融資産の運用も証券担保ローン(借入)で投資効率を高めて運用することを希望される方が比較的多いのではないかと思います。
ポイント③ROE利回りと担保下落余力でレバレッジ比率を決定
証券担保ローンを使って運用するとして、やはり大事なのは「ROE利回り」と「どれくらいの担保価値の下落に耐えられるか」です。この兼ね合いでどれくらいレバレッジをかけるか決めることが大事ではないかと思います。
ポイント④円高と円金利上昇リスクに要注意
証券担保ローンは米ドル債券を担保にしますから、一番のリスクは米ドル安円高リスクです。そうなったときは評価損が大きくなる可能性があり、担保時価下落余力も下がります。そういった点に要注意です。
それと、昨今、日本の金利も上昇しています。そうすると先ほどの表の借入金利1.9%も上昇する可能性が高いわけです。
1%日本の金利が上がると、基本的に借入金利も1%ぐらい上がって2.9%になる可能性も高いです。そうすると債券利回りの差が小さくなって、ROE利回りが下がることになります。
証券担保ローンを使って米ドル建て債券に投資するリスクは「円高」と「円金利上昇」だと思いますので、この点も注視していくのが良いのではないかと思います。
当社ウェルス・パートナーは不動産売却富裕層の方の資産運用をサポートしています。
不動産を売却した資金を金融資産で運用したい方や、レバレッジ重視の運用をしたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社ウェルス・パートナー
代表取締役 世古口 俊介
2005年4月に日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイスのプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。
2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。超富裕層のコンサルティングを行い1人での最高預かり残高は400億円。書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者1万人超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」での情報発信を通じて日本人の資産形成に貢献。医師向けサイトm3.comのDoctors LIFESTYLEマネー部門の連載ランキング人気1位。
メディア掲載情報:「m3.com」「ZUU online」「MONEY zine」「マネー現代」でコラムを連載中