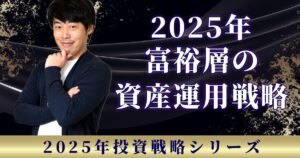目次
資産10億円超の資産家が抱える新たな課題
資産10億円を超える規模になると、資産運用の目的は「大きく増やす」ことから「どのように守りながら収益を上げるか」に移行します。
このフェーズの資産家が求めるのは、年3%〜4%の安定したインカムです。そして、資産価値を大きく毀損しない設計です。その手段として、近年見直されているのが「債券」になります。
かつての超低金利時代では、債券は魅力を失っていました。しかし現在では、利回り3%〜4%の債券が現実的に手に入る時代です。資産10億円以上の富裕層は、再び債券に注目しています。
今回の記事では、利回り3%超のインカムと、リスク分散の両立を目指す債券ポートフォリオについて、実例を踏まえながら解説します。
資産10億円超の運用で重要な3つの前提
資産運用の意思決定では、長期的かつ戦略的な対応が必要です。世代を超えて、資産を引き継ぐには、さまざまなリスクに配慮しなければなりません。富裕層の資産運用には「守りの姿勢」と「次世代への承継」の2つの柱を、同時に考慮することが重要です。
流動性リスクを最小化する
10億円規模の資産運用では、突発的な流動性リスク(不動産の購入、相続対策、企業支援など)が起こるかもしれません。債券投資に関しても、一定割合は、短期債やMMFなどで流動性を確保することが鉄則です。
相続・贈与・資産保全の観点を織り込む
相続税や贈与税の負担を抑える工夫は大切です。債券の保有方法(個人か法人)によって、課税インパクトも変わります。運用だけではなく「保有形態」もポートフォリオ設計の対象となってきます。
全体ポートフォリオにおける債券の役割を定義する
たとえば、株式において、年率5%〜10%のリターンを狙うとします。債券に関しては、年率3%でも「安定して入るキャッシュフロー」として価値を持たせます。この役割の違いを理解したうえで、リスクのバランサーとしてポートフォリオ内の債券を機能させるのです。
利回り3%超を狙う債券ポートフォリオの設計原則
資産10億円超の富裕層にとって、債券は単なる「安全資産」ではありません。「戦略的に設計されたインカム源」としての債券が求められます。年3%以上の利回りを安定的に得るためには、許容可能なリスクを見極めたうえで、的確にリスクを取ることが重要です。
債券の基本分類
債券には、さまざまな種類が存在します。代表的なカテゴリーは以下の通りです。
| 種類 | 概要 | 特徴・留意点 |
| 国債(円建て) | 日本国発行の債券 | 信用リスクは小さいが、利回りも低い(現在は10年で1.5%前後) |
| 外国国債(外貨建て) | 米国・豪州などの国債 | 為替変動リスクあり。通貨と償還までの期間によって、利回りに差 |
| 社債(投資適格債) | 格付BBB以上の企業発行 | 信用リスクをできるだけ抑えつつ、国債より利回り上乗せを期待 |
| 劣後債 | 元本返済順位が劣る | 格付の割に高利回り。金融機関が多い |
| 仕組債 | 条件付きでリターンが変動 | 元本リスクと表面利回りのバランスに注意(デリバティブの要素を内包しており、リスクを取るわりにリターンが十分ではないという指摘もあって、一般におすすめできない) |
利回り3%超で必要な「3つの戦略的選択」
利回りを高めるには、相応のリスクを取らなければなりません。安全性だけを求めると、投資対象にもよりますが一般に利回りは1%前後にとどまります。
以下の3つの視点から「選択と分散」を図るのが、10億円以上のポートフォリオ設計における基本的な戦略です。
1. 為替変動リスクを取る(外貨建て)
円建て債券では、3%超の利回りを得るのは難しいです。米ドル建て・豪ドル建てなど、金利水準の高い国の債券を活用しましょう。為替変動リスクを取る代わりに、利回り向上が期待できます。
例)米ドル建てIG社債(3年):利回り 4.2%(為替変動リスクあり)
2. 信用リスクを取る(劣後債やBBB格社債)
信用格付けの低い社債や劣後債は、信用リスクと引き換えに、高い利回りが得られます。信頼できる企業のサブ債(たとえば、大手金融機関の発行債)などは、リスクに見合った利回り商品として期待できます。
例)日本国内大手生保の劣後債:利回り 3.8%〜4.5%
3. 複合的なリスクをとる(ファンド)
複数の債券や資産に分散投資する「債券ファンド」は、単体の債券では得られない運用手法や、リスク分散効果を期待できます。適切に選ぶことで、安定的なインカムが期待できます。資産全体のパフォーマンス向上にもつながるでしょう。
利回り3.2%を狙う分散型債券ポートフォリオの実践例
ここでは、実在する事例を通じて、資産10億円を超える方々が、どのように債券ポートフォリオを組み立てているのかを、ご紹介します。
ケース:A氏(65歳・経営者引退後の資産運用)
A氏は、60代半ばで事業を売却しました。約12億円の金融資産を保有しています。目的は「年2,000万円程度のインカム(生活費・孫への教育資金など)を確保しながら、資産を大きく減らさないこと」です。株式比率は抑えて、債券を中核にした安定運用を希望しました。
A氏の債券ポートフォリオ構成(全体の70%、約8.4億円)
| 投資対象 | 配分比率 | 通貨 | 利回り(税引前) | 備考 |
| 米ドル建てIG社債(1年〜3年) | 15% | USD | 約4.2% | 為替ヘッジなし、短期で流動性高い |
| 豪ドル建て国債(5年) | 10% | AUD | 約4.5% | 為替ヘッジあり、安定国の信用 |
| 日本の劣後債(7年) | 20% | JPY | 約3.6% | 金融系、信用スプレッド魅力 |
| 新興国国債(為替ヘッジ付き) | 15% | USD/他 | 約4.0% | 通貨リスク排除、ヘッジコスト考慮 |
| 仕組債(3年・ノックイン付き) | 20% | USD | 約5.5% | 月払い型、高利回り商品。制限あり |
| 短期MMF・現金等 | 20% | JPY | 0.5%以下 | 必要資金の待機場所として活用 |
※ポートフォリオ全体の加重平均利回り:3.2%(税引前)
リスク分散のポイント
- 通貨分散:円・米ドル・豪ドルなど、複数通貨にまたがることで特定の通貨への偏りを防止
- 発行体の分散:国債・社債・劣後債・仕組債など、多様な発行主体を組み合わせ
- 償還年限の分散:1年から7年まで期間を分散させて、金利変動リスクを抑制
このように、10億円超のポートフォリオでは、リスクの抑制と収益のバランスを意識します。「許容可能な部分にリターン重視の配分を行う」設計が重要です。
利回りを優先しすぎた投資の失敗事例について
「利回り3%以上」を目指す投資は魅力的です。一方で、リスク管理を誤ると、大きな損失につながるおそれがあります。ここでは、利回りを優先した場合の、3つの失敗事例を紹介します。
事例①:表面利回り6%の仕組債で元本毀損
B氏(50代・経営者)は、国内証券会社から提案された「表面利率6%の仕組債」に1億円を投資しました。この債券は「日経平均株価があらかじめ決められた水準を下回らなければ、元本償還+ 6%クーポン」という条件付き商品でした。
しかし、予想に反して株価が急落したのです。ノックイン(条件到達)が発動して、元本が株価水準に連動して償還されました。これによって、最終的な実質元本回収額が約7,000万円になったのです。
損失額:約3,000万円
問題点と教訓:
- 表面利回りの裏にある「リスクの構造」を理解していなかった
- 1銘柄への投資比率が高すぎた
- 債券=元本確保という誤解があった
結論:利回りが高い商品ほど、「見えにくいリスク」や条件を確認することが重要になります。
事例②:新興国通貨建て債券で為替損
C氏(60代・不動産オーナー)は、利回りが6%超に魅力を感じました。そのため、南アフリカランド建ての国債を複数購入しました。
しかし、南アフリカランドの為替相場が大きく下落したため、受け取った利子を上回る為替差損が発生したのです。その結果、元本の円換算額も大幅に減少しました。利回りだけでなく、円ベースでも年5%以上のマイナスになったのです。
問題点と教訓:
- 「為替変動リスク」のインパクトの大きさを見落とした
- 通貨分散されておらず、新興国通貨に偏っていた
結論:外貨建て債券は、利回りだけでなく「通貨の安定性」が非常に大切になります。
事例③:一部の金融機関に偏った債券保有で「信用リスクが集中」
D氏(70代・資産管理会社の会長)は、信頼していた大手証券会社の助言を受けて、同グループの関連会社が発行する劣後債を複数購入しました。表面利率は、3.8%〜4.5%と高水準です。すべて同一グループ企業が発行するため、信用リスクが一極集中していました。
しかし、その企業の業績が悪化して、債券の価格は急落したのです。結果として、D氏は大きく目減りした評価額で、債券を売却しました。
問題点と教訓:
- 発行体の分散がされておらず、信用リスクが集中していた
- 「信頼している会社だから大丈夫」という思い込みがあった
結論:利回りだけではなく「どこの債券を何%持つのか」の配分バランスを考慮しなければなりません。
3つの事例に共通する失敗要因
債券は一般的に「安定した資産」として認識されます。しかし、実際の運用においては、思いがけない落とし穴も多いです。高利回り商品や複雑な構造を持つ債券では、大きな損失を被るケースも見受けられます。失敗に陥りやすい典型的なパターンと、その背景にある共通の注意点を整理して、上記の失敗要因を表にまとめました。
| 共通事項 | 失敗の解説 |
| 利回りに目がくらんで、構造を理解していない | 仕組債や外貨建て債券において、商品設計を十分理解せずに購入している |
| リスク分散がなされていない | 通貨、発行体、期間のいずれかに偏りがある |
| 投資目的が不明確になっている | インカムなのかキャピタルなのか、明確でないまま購入している |
「ポートフォリオの組み立て方」と「戦略的な分散投資」が重要
「債券=守り」というイメージを持つ方も多いです。実際には、設計次第で大きく成績が変わります。
高利回りに惹かれるのは自然なことです。しかし、その背後にあるリスクの仕組みや、分散の工夫がなければ、債券であっても思わぬ損失を被るかもしれません。
プロに相談して設計する際の5つのチェックポイント
資産10億円以上を運用する際、債券ポートフォリオの設計は「利回りとリスクのバランス」が重要です。「ポートフォリオの戦略的な目的と構成バランス」の視点も欠かせません。
証券会社や金融機関の提案を、そのまま受け入れて投資商品を購入することは、さまざまな失敗につながります。ここでは、独立系IFAや信頼できる専門家に相談する際に、確認するべき5つのチェックポイントを紹介します。
チェック①:自身のポートフォリオ全体における“債券の役割”は何か?
最初に確認するべき点は、自身の資産全体の中で、債券がどのような役割を担うかです。
- 年間2,000万円のインカムを得るため、中核の商品として活用するのか?
- 株式や不動産の値動きを和らげる安定役で、ポートフォリオに組み入れるのか?
- 相続対策でリスクを抑えた、長期的な保有資産にするのか?
このように、目的によって取るべき債券の種類や通貨、期間が異なります。
チェック②:為替変動・再投資・信用の各リスクを踏まえて、どのようにリスクバランスを設計するのか?
債券投資におけるリスクは「為替変動リスク」だけではありません。以下の3つのリスクをどのようにコントロールするのかが、設計上の大きなポイントです。
| リスク項目 | 説明 | 避け方・工夫 |
| 為替変動リスク | 為替変動によって、元本や利子が目減りするリスク | ヘッジ付き債券の活用、通貨分散 |
| 再投資リスク | 満期を迎えた際に、好条件で再投資できないリスク | 満期をずらす、債券ファンドの活用 |
| 信用リスク | 発行体の財務悪化による元本・利子の毀損 | 発行体の分散、格付の確認 |
「利回りの高い商品」の選択は効率的に見えるかもしれません。しかし、3つのリスクを適切に調整しなければ、資産全体のバランスが崩れるおそれがあります。
チェック③:為替ヘッジの有無とコストを把握しているか?
為替ヘッジを行うことで、為替変動リスクが抑えられます。一方で、ヘッジコスト(通貨スワップ差)が発生します。現在のように円とドルの金利差が大きい局面では、年間4%前後のヘッジコストがかかる場合もあるのです。
為替ヘッジの有無で、実質的なリターンが大きく変わります。ポートフォリオ設計時には、必ず確認すべき項目です。
チェック④:提案者の利益相反を見極められているのか?
証券会社や銀行では、自社が取り扱っている商品を中心に提案する場合もあります。そのため、提案された内容が中立的とは限りません。販売手数料や保有報酬を目的とした提案もあり得ます。
- 「なぜその商品を勧めるのか?」
- 「他の選択肢と比較した場合のメリット・デメリットは?」
などの問いを、提案者に投げかけましょう。「自身の利益が最優先されているのか」を見極めることが重要です。
独立系IFAやフィー・ベース型の提案者は、金融商品の販売から利益を得ません。利益相反が起こりにくいという観点では、独立系IFAやフィー・ベース型の仕組みは、非常に優れています。
最適な債券ポートフォリオを見つけるには、プロの視点を取り入れることが近道
資産10億円超の運用では「とりあえず高利回りな債券を選ぶ」という考え方は非常に危険です。自身の目的や資産全体の設計、リスク許容度、そしてライフステージに合わせる必要があります。債券の組み入れ方ひとつで、資産運用の成果が大きく変わります。
債券のポートフォリオは、単なる「商品選び」ではありません。戦略の構築になります。設計の段階で、信頼できる専門家との連携が何よりも重要です。

株式会社ウェルス・パートナー
代表取締役 世古口 俊介
2005年4月に日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイスのプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。
2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。超富裕層のコンサルティングを行い1人での最高預かり残高は400億円。書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者1万人超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」での情報発信を通じて日本人の資産形成に貢献。医師向けサイトm3.comのDoctors LIFESTYLEマネー部門の連載ランキング人気1位。
メディア掲載情報:「m3.com」「ZUU online」「MONEY zine」「マネー現代」でコラムを連載中