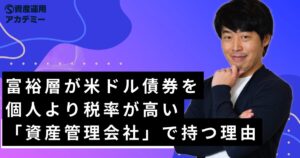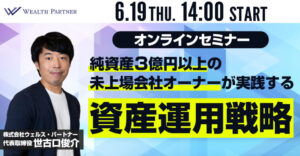目次
はじめに
会社を売却することは、経営者人生の一区切りであると同時に、ご自身やご家族の将来を大きく左右する「出口戦略」でもあります。とりわけ富裕層の会社オーナーにとっては、会社売却によって得られる資金をいかに守り、次の資産戦略へとつなげていくかが重要なテーマとなります。
そうしたなか、2023年度に税制改正が行われ、2025年1月から施行された「株式譲渡益への課税強化」は、これまでの常識を大きく変える出来事となりました。株式を売却して得た利益に対する税率が最大で27.5%へと引き上げられ、これまで想定していたよりも“手取り額が大きく目減りする”という現実が突きつけられています。
すでにこの制度は始まっており、影響を受けるのは一部の超富裕層だけではありません。会社オーナーであれば、会社売却によって得られる利益が数億円規模になることは珍しくなく、この税率改正は、まさに“自分ごと”として捉えるべき問題なのです。
本記事では、この税制改正の概要とそのインパクトをわかりやすく整理しつつ、オーナーが今後どのように出口戦略を設計すべきか、実践的な対策を解説していきます。制度が変わる今だからこそ、「正しい知識と備え」が資産を守るカギとなるでしょう。
税制改正で何が変わったのか
2025年1月1日以降、株式の譲渡益に対する課税制度が大きく見直されました。これにより、会社を売却する際の「最終的な手取り額」にも、これまでにない影響が及ぶことになります。
これまで、上場・非上場を問わず株式の譲渡益に対する税率は、おおむね20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)で統一されていました。ところが、今回の税率改正では、一定の高所得者層を対象に、新たに、「所得税22.5%+住民税5%=最大27.5%」が課税されることになりました。
変更となるのは所得税のみで、住民税に関しては従来通りとなります。つまり、2025年1月より、下記の表のように変更されているのです。
| 税金の種類 | 引き上げ前 | 引き上げ後 |
| 所得税 | 一律で15% | 最大で22.5% |
| 住民税 | 一律で5% | 一律で5% |
この課税強化の基準となるのが「基準所得金額」です。すべてのケースが引き上げ対象となるわけではありません。具体的には、譲渡益や配当などを含む年間の合計所得が3.3億円を超える場合、その超過部分に対して上記の税率が適用される仕組みで、「(年間の所得-3.3億円)×22.5%=最低所得税額」となります。
これは、OECDが主導する「国際最低課税制度(グローバルミニマム課税)」の国内適用の一環であり、日本では“ミニマムタックス”とも呼ばれています。一見すると、ごく一部の超富裕層にのみ関係するように思えるかもしれません。しかし、会社売却によって得られる譲渡益が数億円規模にのぼるケースは少なくありません。
例えば、保有する自社株を10億円で売却したとしましょう。取得費等を差し引いた純粋な譲渡益が7億円であれば、そのうち3.7億円に対しては、新税率による重い課税が発生することになります。
要するに、「会社売却」という人生の大きな意思決定に対して、税制が新たなハードルを設けたともいえるのです。この改正はすでに施行されており、今後、会社売却を検討するすべての会社オーナーにとって、避けては通れない“前提条件”となっています。
株式譲渡税率引き上げの背景 -富裕層への課税強化と「1億円の壁」
今回の株式譲渡税率の引き上げには、政府が掲げる「富裕層への課税強化」という明確なメッセージが込められています。これは、従来の税制が抱えていた不均衡を是正し、より公平な社会の実現を目指すための動きといえるでしょう。
これまで、日本の税制においては、給与所得や事業所得が累進課税である一方、株式譲渡益や配当所得に対する課税が比較的軽く、「資産家ほど有利」との批判が根強くありました。特に、スタートアップや中小企業の創業オーナーが自社株を売却して得る多額のキャピタルゲインに対しても、一律約20%の課税で済む現行制度は、所得格差是正の観点から見直しの対象となっていたのです。
この税率引き上げの背景には、高所得者ほど税負担の割合が小さくなるという「1億円の壁」問題が大きく影響しています。一般的に高所得者は給与所得や事業所得よりも株式などの譲渡所得の割合が高い傾向にあります。給与所得や事業所得にかかる所得税は所得が高くなるほど税率が上がる累進制であるのに対し、譲渡所得は一律で課税されるため、結果として高所得者の所得税の負担割合は低下する傾向が見られました。
国税庁の調査によると、所得が5,000万円から1億円の富裕層の負担率が27%であるのに対し、50億円から100億円の超富裕層では17%台にまで低下するという逆転現象が確認されています。所得金額1億円を境に所得税の負担割合が低下するというこの現象を是正し、公平な税制を実現するために、今回の株式譲渡税の引き上げが決定されました。
また、近年の国家財政悪化や社会保障費の増大も、高所得層や資産家に対する「公平な負担」を求める声が強まった要因の一つです。このような流れを踏まえると、今後も“資産への課税強化”の動きは続く可能性があり、会社売却や事業承継を検討する会社オーナーにとっては、税制改正の動向を見極め、タイミングを見誤らない判断がますます重要になってくるでしょう。
実際どれだけの影響があるのか?手取り額のシミュレーション
政府が検討を進めている株式譲渡益への課税強化。最大27.5%が適用となった場合、会社売却による手取り額にどのような影響があるのでしょうか。ここでは、譲渡益が5億円と10億円のケースを例に、シミュレーションを行ってみます。
・ケース1:譲渡益5億円の場合
| 区分 | 税率 | 納税額 | 手取り額 |
| 現行制度(分離課税20.315%) | 20.315% | 約1億158万円 | 約3億9,842万円 |
| 税率引き上げ後(27.5%) | 27.5% | 1億3,750万円 | 3億6,250万円 |
| 差額 | — | — | ▲約3,592万円 |
・ケース2:譲渡益10億円の場合
| 区分 | 税率 | 納税額 | 手取り額 |
| 現行制度(分離課税20.315%) | 20.315% | 約2億315万円 | 約7億9,685万円 |
| 税率引き上げ後(27.5%) | 27.5% | 2億7,500万円 | 7億2,500万円 |
| 差額 | — | — | ▲約7,185万円 |
このように、税率が20.315%から27.5%になるだけでも、数千万円単位で手取りが減少するのがおわかりいただけたでしょう。特に譲渡益が高額なケースでは、税率のわずかな変動が資産形成に大きな影響を及ぼします。今後も政策動向を注視しつつ、会社売却を行う際はタイミングを慎重に見極めることが重要です。
※具体的な税率や控除の適用範囲については、今後の法改正の内容に応じて変更される可能性があります。
影響を受ける会社オーナー
今回の株式譲渡税率の引き上げは、すべての会社オーナーに一律の影響を及ぼすわけではありません。特に大きな影響を受けるのは、譲渡益が一定水準を超えるケース、すなわち「高額譲渡益が見込まれる会社売却」を検討している会社オーナーです。
具体的には、長年にわたり企業価値を積み上げてきた中堅企業や、特にIT・医療・EC・物流など成長性の高い業種のオーナーが該当しやすい傾向にあります。このようなケースでは、数億円〜数十億円規模の譲渡益が発生するため、新たな税率構造のもとでは、手元に残る資金が大きく減る可能性があるのです。
また、将来的に会社売却し、引退後の生活資金や次世代への資産承継を見据えている会社オーナーにとっては、課税後の実質的な資産額がその後の人生設計に直結します。税負担のわずかな違いが、ライフプラン全体に与える影響は決して小さくありません。
このように、影響を強く受ける層は限られているように見えますが、「いずれ売却を考える可能性がある」会社オーナーすべてにとって、税率の変化はすでに現実のものとなっています。すでに始まった新税制のもとで、手取り額を最大化するにはどうすればよいのでしょうか。次章では、会社オーナーが今まさに検討すべき具体的な対策について解説します。
会社オーナーが今すぐ実践すべき5つの具体的対策
株式譲渡にかかる税率が引き上げられた今、会社オーナーにとっては、節税や資産保全のための対策は待ったなしの課題といえるでしょう。以下に、実際に検討すべき代表的な5つの対策をご紹介します。
① 資産管理会社を活用して、長期的に税効率を高める
譲渡益を個人ではなく「法人=資産管理会社」で受け取ることで、所得分散が可能となり、累進課税の影響を軽減できます。資産管理会社を通じて得た資金を再投資に回すことで、法人税の繰延効果も期待でき、資産形成の観点でも有利です。ただし、税務上の要件や実務の整備が必要なため、専門家への相談が必要となります。
資産管理会社については、詳しく解説している下記の記事をご参照ください。
② タイミングを分けて段階的に譲渡する
譲渡時期を複数年に分けて実行することで、1年あたりの譲渡益を抑えることができ、税率を低く抑える効果があります。特に、累進課税構造をとる新制度では、課税所得が集中することで最大税率が適用されるリスクがあるため、段階的な売却は有効な回避策となります。
具体的には、株式譲渡契約書で分割譲渡を明記したうえで、初年度に50%、残りの50%は翌年以降の業績目標達成後に譲渡とするなどの方法が有効です。さらに、売却価額を業績連動型とすることで、株価が上がれば売却益が増える可能性もあります。これは、買い手側としても資金負担のタイミングを分散できるため、双方にとって効果的な方法といえるでしょう。
③ エンジェル税制などの優遇制度を活用する
一定の条件を満たす未上場企業・ベンチャー企業への投資や出資については、エンジェル税制などの特例措置により、投資額に応じて所得税や住民税の控除が受けられます。また、将来の売却時点では、譲渡益に対して税制優遇が受けられる場合があります。M&Aによって株式を取得する投資型オーナーや事業承継型の取引でも活用可能性があるため、制度の適用要件を確認する価値はあるでしょう。
参考:経済産業省「エンジェル税制」https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angeltax/index.html
④ 他の譲渡損失との損益通算を図る
過去に発生した株式の譲渡損失がある場合、一定の期間内であれば譲渡益と相殺することで課税額を減らすことが可能です。また、保有資産の中に含み損がある場合には、売却タイミングを調整することで通算効果を得る戦略も考えられます。
⑤ M&Aスキームを再検討する
事業売却を株式譲渡ではなく、資産譲渡や会社分割、合併といった他のM&A手法に切り替えることで、課税関係を柔軟に設計できるケースがあります。特に、会社分割やホールディングス化などのスキームを用いることで、事業承継や資産移転といった目的を達成しながら、課税タイミングの調整が可能になります。
これらの対策は、税理士・会計士・FAなどの専門家との連携が不可欠です。私たちウェルス・パートナーには、富裕層の方の資産管理会社設立や節税対策、資産保全に関する専門知識を有するアドバイザーが在籍しております。お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案し、大切な資産を守り、育てるお手伝いをいたします。まずはお気軽にご相談ください。
資産保全の視点で考える「出口戦略」
会社売却により得られる資金は、単なる“売却益”ではありません。それは、経営から一線を退いた後の人生を支え、次の世代へとつないでいくための「資産基盤」となります。そのため、売却後にどのように資産を保全・活用していくかという“出口戦略”が、これまで以上に重要となってきています。
特に、今回の税制改正では譲渡益に対する課税強化が進んだことで、売却の「入口」での最適化だけでなく、「出口」における戦略設計の良し悪しが、手元に残る資産の総額を大きく左右するようになりました。つまり、売った後こそが本当の意味での資産運用のスタートであり、その一歩をどう踏み出すかが問われているのです。
出口戦略においてまず検討すべきは、譲渡益をどこに、どのような形で移すかという視点です。例えば、売却資金を資産管理会社に移すことで、法人税ベースでの運用益管理や所得の分散、家族を巻き込んだ資産承継の仕組みづくりが可能になります。仮に、家族を役員や従業員として給与を支払えば、生前贈与に代わる節税効果も見込めるでしょう。
運用対象としては、分散性と安定性を重視した不動産投資やプライベートアセット(未上場株式、PEファンド、アート等)などが王道ですが、それだけにとどまりません。海外資産に分散することで為替リスクをとりつつ通貨の多様化を図る戦略が有効です。
例えば、外貨建て債券や株式などを購入する際に、為替ヘッジを行うことで、為替変動リスクを抑えつつ運用益を狙うことができます。ヘッジ比率を調整することで、リスク許容度に応じたポートフォリオを構築できます。また、海外不動産やオフショアファンドなどは、一定の資産規模と知見があれば、富裕層にとって魅力的な選択肢となります。
一方で、こうした出口戦略は複雑な制度や税制が絡むため、独自判断で進めると逆に課税リスクや資産凍結の懸念も生まれかねません。それゆえ、税金に精通した専門家とともに、「ライフプラン」と「相続プラン」を統合した設計を行うことが不可欠です。譲渡後の10年、20年を見据えたうえで、どのように守り、どのように遺すか。その設計こそが、売却益を真に“富”へと変える鍵となります。
関連する下記の記事もご覧ください。
まとめ
株式譲渡益課税の強化は、すでに2025年1月から始まっています。これからの会社売却・資産戦略には、「売却前から出口まで」の一貫した設計が求められます。情報を正しく捉え、専門家とともに最適な道筋を描くことが、資産を守り、次世代へとつなぐための第一歩となるでしょう。

株式会社ウェルス・パートナー
ポートフォリオマネージャー
早稲田大学国際教養学部卒業後、大和証券株式会社へ入社。富裕層と会社経営者を中心とした資産運用のコンサルティング業務に従事。顧客の資産全体の最適化や会社経営者への相続対策まで支援をしたいという思いがあり、株式会社ウェルスパートナーに入社。