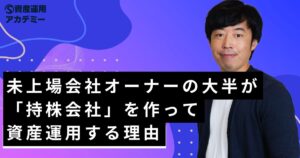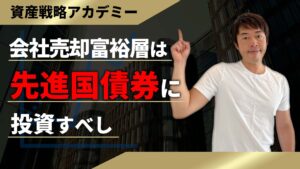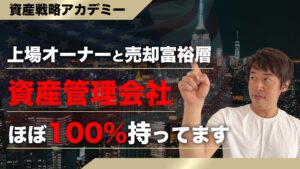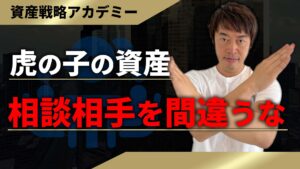目次
はじめに
会社売却は、人生において大きな節目であり、経済的にも精神的にも大きなインパクトをもたらします。特に富裕層にとっては、売却によって得た資金が資産運用や次世代への承継に直結するため、売却後にどれだけ手元に資産を残せるかが極めて重要です。
会社を売却して得た利益には、当然ながら税金がかかり、売却価格が大きければ大きいほど、その税負担も無視できないものになります。せっかく築いた資産も、適切な税金対策を講じなければ多額の税負担が発生し、手元に残る金額が大幅に目減りすることもあります。要するに、「いかに税負担を抑え、効率よく資産を残すか」が、売却を成功させるうえでカギとなるのです。
本記事では、会社売却時にかかる主な税金の種類から、富裕層が会社売却を行う際に実践すべき節税のポイント、それに伴うリスクや注意点を詳しく解説します。
会社売却にかかる主な税金の種類
節税のポイントの前に会社売却にかかる主な税金の種類をご説明します。会社売却の際に最初に検討すべきは、「株式譲渡」と「事業譲渡」のどちらの形態を取るかです。これにより、節税のアプローチが大きく変わってきます。
実際に富裕層の会社オーナーが実践するM&Aスキームには株式譲渡・事業譲渡以外にも、「会社分割」があります。後継者に一部事業を承継させ、他事業を第三者に売却する場合、会社分割が有効です。資産と負債が整理された法人は買い手にとってもリスクが限定され、買いやすくなります。ですから、「売却の前段階」「税務戦略」で活用するという考え方になります。
ここでは、個人が株式譲渡するケース、法人が株式譲渡するケース、事業譲渡(法人)の3パターンを解説します。
株式譲渡にかかる主な税金(個人・法人別)
まずは株式譲渡にかかる主な税金について、個人と法人に分けて解説します。
個人が株式を譲渡した場合の税金
自社株を「個人」で保有している場合、売却益は「譲渡所得」として扱われ、一律20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)の税率で課税されます。
譲渡所得は次のような計算式で算出されます。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
[売却価格]
株式売却によって得た金額。実務では、会社の純資産に加え、営業権(のれん)も含めた金額が基準となることが多い。
[取得費]
株式を取得したときにかかった費用。創業者株式の場合は払込金額、相続や贈与で取得した場合は評価額が用いられる。
[譲渡費用]
弁護士費用やM&Aアドバイザーへの報酬、契約書作成費などが含まれる。
【具体例】売却価格が3億円の課税額(個人の場合)
- 売却価格:3億円
- 取得費:1,000万円
- 譲渡費用:500万円
- 譲渡所得:2億8,500万円
- 所得税・住民税:2億8,500万円 × 20.315%=約5,789万円
この場合、個人に残る金額(手取り)は約2億2,711万円になります。このように一律の分離課税(20.315%)が適用されるため、非常に低い税率で済むのが大きな特徴です。
一方、通常の役員報酬やボーナスなどは「給与所得」として累進課税が適用され、所得が高額になるほど税率が上がります。最高税率は約55%にも達するため、仮に同じ3億円を役員報酬として受け取った場合、手取りは大きく目減りします。ですから、株式譲渡は非常に効率の良いキャッシュ化の手段であり、資産形成や引退後の生活設計においても有利な選択肢といえるでしょう。
法人が株式を譲渡した場合の税金
法人が株式を保有している場合、株式を売却すると、その利益は法人の「譲渡益」として計上されます。この譲渡益は、法人の通常の所得と合算され、法人税・法人住民税・法人事業税などが課税されます。
法人税率は法人の規模や所得によって異なりますが、一般的な中堅企業の場合、これらを合計した実効税率は約30〜40%とされています。
【具体例】売却価格3億円の課税額(法人の場合)
- 売却価格:3億円
- 取得費:1,000万円
- 譲渡費用:500万円
- 譲渡益:3億円 −(1,000万円+500万円)=2億8,500万円
仮に、実効税率を35%と想定すると、課税額は以下の通りになります。
- 法人税等:2億8,500万円 × 35% = 9,975万円
この場合、法人に残る金額(手取り)は約1億8,525万円となります。
株式譲渡にかかる主な税金(個人・法人)比較
| 比較項目 | 個人株主の場合 | 法人株主の場合 |
| 利益の扱い | 譲渡所得(分離課税) | 法人所得(総合課税) |
| 税率の目安 | 約20.315%(所得税+住民税) | 約30〜40%(実効税率) |
| 消費税 | 非課税 | 非課税 |
| 不動産取得税 | 原則かからない | 原則かからない |
| 印紙税(契約書) | 原則不要 | 原則不要 |
| 印紙税(領収書) | 受取金額に応じて課税 | 受取金額に応じて課税 |
| 損益通算 | 株式の譲渡損益のみ | 他の事業所得とも通算可能 |
| 節税策 | 退職金など | 経費計上、繰越欠損金など |
事業譲渡にかかる主な税金
一方、会社が事業の一部または全部を第三者に譲渡する「事業譲渡」にはどのような税金がかかるのでしょうか。主に法人税・消費税・不動産関係の税金の3つですが、具体的には次の一覧のような税金が関係してきます。
事業譲渡にかかる主な税金一覧
| 税金の種類 | 課税される対象 | 負担者 | 備考 |
| 法人税等 | 営業権などの譲渡益 | 売り手 | 実効税率約30〜40% |
| 消費税 | 課税資産(建物、営業権など) | 買い手 | 非課税資産(土地・売掛金など)は除外 |
| 登録免許税 | 不動産の所有権移転登記 | 買い手 | 土地:15/1,000、建物:20/1,000 |
| 不動産取得税 | 取得した不動産 | 買い手 | 評価額の3% |
| 印紙税 | 契約書・領収書 | 売り手または双方 | 金額に応じて課税 |
1. 法人税等
事業を売却して得られた利益に対しては、約30~40%の法人税等(法人税・地方法人税・法人住民税・事業税)が課税されます。課税対象は法人であり、オーナー個人に直接課税されることはありません。
2. 消費税
事業譲渡では、譲渡対象の中で「消費税が課税される資産」にのみ消費税が課されます。
- 課税対象となる資産:建物・営業権(のれん)・備品
- 非課税となる資産:土地・売掛金・有価証券
例えば、3億円の事業譲渡であっても、課税対象資産が1億円であれば、消費税はその1億円に対して課されます。
3. 不動産が含まれる場合の税金
譲渡対象に不動産が含まれる場合、以下の税金が追加で発生します。
登録免許税(不動産の所有権移転登記にかかる税金)
- 土地:固定資産税評価額 × 15/1,000(軽減措置適用時)
- 建物:固定資産税評価額 × 20/1,000
不動産取得税(不動産の取得自体に対して課税される税金)
- 取得価額 × 3%
印紙税
不動産の売買契約書や領収書には、契約金額に応じた印紙税が課されます。
事業譲渡には複数の税金が関係し、それぞれの資産の内訳によって税額は大きく変わります。特に営業権の評価や、不動産を含む場合の追加税負担などは見落としがちです。スムーズで納得のいく譲渡を行うためにも、税理士やM&Aアドバイザーと連携し、事前の税務戦略を立てておくことが重要です。
富裕層が押さえておくべき税金対策の基本戦略
それでは本題に入りましょう。会社売却に伴う税負担を抑えるために、富裕層の会社オーナーが押さえておくべき主な税金対策を、以下の6つの観点から解説します。
1. 含み損資産との相殺(キャピタル・ロスの活用)
会社売却によって株式譲渡益が発生すると、20.315%の税金(所得税+住民税)が課税されます。これに対して、他の資産(たとえば上場株式、不動産等)で評価損が出ているものを売却して損失を実現することで、譲渡益と相殺することができます。
ポイント:
- 売却益と損失は同じ所得区分(譲渡所得)であれば通算可能
- 損失が売却益を上回った場合は、翌年以降に繰越控除(最長3年)も可能
注意点:
- 損失を出すための売却は年内に行う必要がある
- 同一銘柄を短期で買い戻すと「損益通算の否認」対象となる恐れあり
2. 退職金の活用
会社売却と同時に経営者が退任する場合、退職金を支給することができます。退職金は所得税上、最も優遇された所得区分の一つであり、税負担を大幅に抑えることが可能です。
メリット:
- 勤続年数に応じて「退職所得控除」が適用される(例:35年勤務で1,550万円)
- 控除後の金額に対してさらに1/2課税される(実効税率が極めて低い)
注意点:
- 過大な退職金は損金不算入・役員報酬との比較で否認リスクあり
- 否認されないためには業種・規模・過去の報酬履歴に基づいた「妥当性」が必要
3. 譲渡時期の工夫と分散
売却時期を工夫し、譲渡益が発生する年度の他の所得との合算状況を調整することで、所得税の累進課税による影響を緩和できます。また、部分的な売却や複数年に分けた売却によって、課税を一定程度均一にする戦略もあります。
具体例:
- 売却を12月から翌年1月にずらして課税年度を変更
- 株式を第三者や親族に段階的に売却して利益を分散
注意点:
- 株式評価のタイミング、企業価値の変動に留意
- 複数年に分けた売却は、買い手との合意形成が前提
4. 会社分割や持株会社の活用
事前に会社分割や持株会社設立などの組織再編を行うことで、税務上有利なスキームを構築することができます。特に資産・事業の切り離し、分社化、相続対策などに有効です。
具体例:
- 本業とは関係のない不動産・有価証券を会社分割で別会社に移管し、売却対象から除外(譲渡価格を抑制)
- オーナーが持株会社を設立し、そこに株式を集約して売却することで、資産の再投資や承継の柔軟性を確保
注意点:
- 組織再編には専門的な税務・法務知識が必要
5. みなし譲渡課税の回避
「みなし譲渡課税」とは、会社売却時に資産や株式を時価ではなく低額・無償で親族や関係者に譲渡した場合に、本来は時価で譲渡したものとみなされて課税される制度です。特に富裕層の会社オーナーが節税や相続を目的に、事前に株式を子どもや持株会社に安く譲渡した場合に問題となります。
課税対象:
- 所得税(譲渡所得)または贈与税(贈与とみなされた場合)
- 法人間の譲渡であっても、移転価格税制の対象となる場合がある
回避対策:
- 株式や資産を移転する際は、客観的な時価(DCF法や類似業種比準法)を算定し、それに基づいた適正価格で譲渡することで「みなし譲渡」にはならない
- 譲渡であることを明確化する(対価を伴う譲渡とみなされ贈与課税対象外となる)
- 特定の親族への贈与であれば、贈与税の非課税枠や相続時精算課税制度を活用する
6. 取得費加算の特例の活用(相続発生から3年以内の売却)
相続や遺贈で取得した財産(株式など)を、相続開始から3年10か月以内に売却した場合、相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算できる制度です。これにより、譲渡益が圧縮され、所得税・住民税の負担が軽減されます。
対象資産の例:
- 相続で取得した自社株式、上場株式、不動産 など
注意点:
- 加算できる相続税額は、売却した資産に対応する部分のみ(他の財産分は不可)
- 株式評価や分割の状況によっては、相続税との紐づけが困難なケースあり
- 相続税の納税猶予制度を併用している場合は、特例対象外となることもある
会社売却後の資産管理と相続対策
会社を売却して多額の現金が手元に残った場合、その後の資産管理や相続対策も重要になります。特に富裕層の場合、相続税の負担も大きくなりがちなため、早い段階での対策が求められます。
資産管理会社の活用
売却益を個人ではなく、法人(資産管理会社)で受け取ることで、法人税率(実効約30%)を適用できます。個人にかかる所得税の累進課税(最大55%)より低い税率で資金をプールすることが可能で、将来的な相続対策にもつなげられます。法人を活用すれば、所得分散や損益通算、経費計上など、多様な節税策が可能です。
生前贈与の活用
富裕層の方であれば、すでにご存知かと思いますが、相続税の軽減策として、暦年贈与(年間110万円以内)や相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税)などを活用し、生前に少しずつ資産を移転することで、後々の相続税負担を抑えることができます。ただし、近年の税制改正により、生前贈与に対する国税庁の監視は厳しくなっており、「形式的な贈与」とみなされないような対策や記録の整備が求められます。また、2,500万円までの非課税制度を一度選ぶと110万円の暦年贈与は使えなくなるので注意が必要です。
事業承継税制の戦略的活用
一部の売却資産を後継者へ無税で移転するには、「事業承継税制」の適用が有効です。事業承継税制とは、中小企業の後継者が、自社株を贈与または相続によって引き継ぐ際に発生する税金(贈与税・相続税)について、その納税を猶予する制度です。また、一定の条件を満たせば、猶予された税額は将来的に全額免除されることもあります。これにより、後継者が贈与税・相続税を実質ゼロで自社株を承継できる道が開かれ、資金繰りや事業運営における不安が大幅に軽減されます。
詳しくは、下記をご参照ください。
国税庁「事業承継税制特集」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm
中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」
まとめ
会社売却は、一生に一度の大きな転換点であり、税金対策次第で手元に残る金額が大きく変わります。特に富裕層にとっては、売却後の資産をどう守り、次世代へどう承継するかが重要なテーマとなります。信頼できる税理士やIFA、ファイナンシャルプランナーと連携し、自分に最適な戦略を練ることが成功への第一歩です。
私たちウェルス・パートナーでは、富裕層の方の資産運用や長期的な資産形成をサポートしております。税務・法務の専門家とも連携しておりますので、税負担を抑え、効率よく資産を残したいという富裕層の方々のお悩みにもお応えいたします。オンラインでの無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
ご参考までに、本記事に関連するYouTubeはこちらです。

株式会社ウェルス・パートナー
ポートフォリオマネージャー
早稲田大学国際教養学部卒業後、大和証券株式会社へ入社。富裕層と会社経営者を中心とした資産運用のコンサルティング業務に従事。顧客の資産全体の最適化や会社経営者への相続対策まで支援をしたいという思いがあり、株式会社ウェルスパートナーに入社。