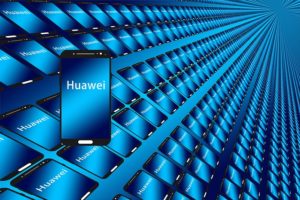はじめに
2016年1月から始まった、マイナンバー制度が現在でもなかなか普及していないことをご存知でしょうか?
マイナンバーカードは確定申告の際の課税所得を自動で行えるだけでなく、どこのコンビニでも住民票や印鑑証明書を発行できるという利便性があります。
しかし、その一方で徴税強化をするために作られたという世間的な印象もあり、普及が進まない原因になっています。
そこで、総務省は2020年9月を目途にマイナンバーを発行している人を対象に25%のポイント還元を実施する方針を打ち出しました。
まだ決定していませんが、今後のマイナンバー利用促進や国内の消費促進のために金融政策以外で財政出動している点が好感されるでしょう。
今回は、「マイナンバーカードとは何か」と「普及率における現状と課題」、「ポイント還元策が実施される必然性」について解説していきます。
マイナンバーカードとは?
マイナンバー制度は2016年1月に本格始動し、個人に12桁の番号が与えられることで、福祉サービス・税・災害対策の3分野で迅速に行政サービスを受けられるようにしたものです。
具体的には、福祉サービスを受けたり、税金の控除を受ける際に今まで多くの書類や手続きの時間を要してきた事務処理をマイナンバーカード1つで迅速に行えることを実現しているのです。
というのも、これまで福祉や税、災害対策について国民の個人情報は各行政機関が管理しており、税金の控除申請などでそれぞれの情報が必要になったとき、各行政機関に問い合わせることや、提出書類が多数必要だったのです。
マイナンバーカードはこうした行政機関と個人の間の煩雑な事務処理を即座に行えるようにしたのです。
また、マイナンバーカードは身分証としての機能だけでなく、コンビニで住民票や印鑑証明書を発行できるので市役所に書類を取りに行く手間が省けるのです。
さらに、マイナンバーカードを発行する際もオンラインで申請することができ、受け取りの際だけ市区町村の役所に行くだけでカードの現物が手に入るのです。
そして、2022年度中に保険証の代わりにも適用できるそうで利便性はどんどん高まってきていますが、その一方で世間的には「結局のところ徴税強化だ」という認識があるのも事実です。
また、個人情報としての利便性が高い反面、紛失時や情報漏洩時にセキュリティ面で懸念があるため、マイナンバーカードを発行することに抵抗がある人も多いでしょう。
それもあって、マイナンバー制度が始まって3年が経過した今でも全国で14.3%(2019年11月1日現在)しか普及していないのです(出典:総務省http://www.soumu.go.jp/main_content/000654411.pdf)。
マイナンバーカードが普及しない理由
なぜ、 3年経ってもマイナンバーカードは全国で14.3%しか普及しないのでしょうか?
その答えを知るために、全国の特別区・市の中で最もマイナンバーカードが普及している宮崎県都城市(普及率31.7%)の普及策を見ていきましょう。
人口16万6000人の都城市は、マイナンバー制度開始後すぐにタブレットでのマイナンバーカード申請を始めました。市内には高齢者も多く、役所から遠い場所に住んでいる人が申請できるように商業施設などでタブレットを使い、申請支援したのです。
また、金融機関と協力しマイナンバーカードを発行している人に定期預金や子育て支援ローンの金利で優遇されるような制度を作っています。
そして、子育て支援の一環として子どもたちの健康診断の結果や予防接種の履歴もオンラインで確認できるようにしています。
このように都城市では市民がマイナンバーカードを使うインセンティブを多く設定し、また、申請しやすいように支援しているのです。
つまり、現在の全国的にマイナンバーカードが普及していないのは、得られるメリットの割に徴税強化やセキュリティへの懸念といったデメリットが上回っているのでしょう。
キャッシュレスポイント還元「マイナポイント」は還元率25%!?
総務省は2020年東京五輪後の消費減速を懸念し、マイナンバーカードでのポイント還元を検討しています。
また、この還元策のために予算は2500億円となっており、約1年間の期限付きで実施される可能性があります。
もし実現されれば、利用者側としては25%のポイント還元なので消費税10%に対して15%多く税金を受け取れるという不思議な現象が起きることになります。つまり、簡単に言うと「買い物をしたときに15%の消費税を私たちが受け取れる」と解釈できるのです。
あまりに不思議ですが1年間しか実施しませんし、現在の日本経済を見ればそこまでして消費・物価を底支えしたいという考えが出てもおかしくはないでしょう。
経済環境を見ると、金融緩和でマイナス金利を導入しても銀行収益の悪化と株式市場の歪みができてしまっただけで、物価目標2%は実現できないように思います。
そこで、金融政策だけでなく今回のような財政政策も併用すべきという意見が出てき始め、今年「MMT(現代貨幣理論)」という本がヒットしたほど、財政出動が必要に迫られていたのです。
このように考えると、金融政策の面でもマイナンバーカード普及の面でも、ポイント還元は不思議なように見えますが、当然といえば当然かもしれません。
というわけで、マイナンバーカードのポイント還元が始まれば、できるだけ利用した方がお得でしょう。