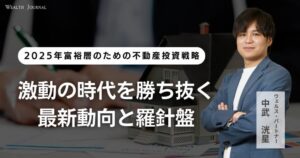目次
はじめに
2025年後半、世界の金融市場は複数の変化が同時に押し寄せる局面を迎えています。米国では利下げサイクルが始まる観測が高まり、年末には政策金利が3.75%〜4.00%へと低下する見通しです。一方で、日本では2024年から日本銀行が利上げを実施し、政策金利は0.50%となりました。また、中国では不動産市場の長期低迷が続き、国内消費の回復は鈍く、世界経済における成長エンジンとしての役割が弱まっており、世界の金融市場は目まぐるしく変化しています。
金融市場だけにとどまらず、ウクライナ戦争の長期化や、台湾有事への警戒の高まりによる、「地政学リスクの上昇」が世界的なインフレを引き起こす1つの要因となっています。また、米国のトランプ大統領による、「関税政策」に端を発したグローバリズムの後退も、インフレを長期化させる要因であることから、資産をインフレから防衛することも大きなテーマになります。
ドル円相場は150円近辺と円安水準で推移しており、為替の変動が資産価値に与える影響が一層鮮明になっています。外貨建て資産を多く保有する富裕層にとって、この円安は評価益を押し上げる要因となる一方、今後円高へ反転した場合の影響も大きくなるため注意が必要です。また、米国の利下げ観測により債券価格は上昇基調にありますが、再投資時の利回り低下という課題も控えています。こうした背景から、2025年後半マーケット予想をしつつ、数年先を見据えてポートフォリオを構築する重要な時期と言えるでしょう。
世界経済の動向予測(米国・中国・日本)
米国:利下げ後の景気減速とソフトランディングの行方
米国経済は、2024年までの急速な利上げの影響が、時間差をもって徐々に表れています。住宅ローン市場では依然として高水準が続き、30年固定金利は2024年末に7%台に達した後、2025年夏時点でも6.5%前後と、利下げの影響は限定的です。そのため不動産市場の取引量は年初より持ち直しているものの、本格的な回復には至っていません。
一方で、インフレは年初の3%台から2%台半ばへと落ち着き、7月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比2.7%上昇と、物価安定の兆しが見えています。しかし実質GDP成長率は第2四半期に年率3.0%と回復したものの、前四半期がマイナス成長だったことを踏まえると、依然として景気基調には強弱が混在しています。
雇用市場は底堅さを保ちながらも、やや軟化の兆しを見せています。失業率は6月に4.1%、7月には4.2%へわずかに上昇、賃金の伸びも前年の4%超から3%台半ばに鈍化し、消費者信頼感指数も前年より低い水準にとどまりました。企業収益も好調を維持していますが、通年では減速するとの予測もあります。
歴史的にみても、利下げ初期には株価が一時的に持ち直す傾向がありますが、その後は景気減速懸念が優勢となり、株式市場が横ばいから下押し圧力を受けやすい局面に移行することが少なくありません。2025年後半も同様のパターンに入り、特に金利・為替・景気指標の変化に敏感な相場展開になることが予想されます。
中国:回復の芽と構造課題が混在する「不均衡な成長」
中国の景気は、半導体装置や新エネルギー車、ロボティクスといった政策色の濃い分野が押し上げてはいますが、ボトルネックはやはり不動産です。公的統計では5月の新築価格が前月比で再び下落し、2年に及ぶ調整からの明確な底入れには至っていません。他方で、民間調査では100都市平均が小幅に反発する月も出ており、都市と物件の「選別」が進行しています。価格の底割れを嫌う当局は、購入制限の緩和や保証支援など断続的に手を打っていますが、販売・着工・投資が同時に立ち上がるまでには時間を要するでしょう。
雇用面も強弱が混在します。若年失業率は6月に14.5%まで低下しつつも依然として高く、可処分所得の伸びを抑える一因です。加えて、工業部門の利益は6月に前年同月比でマイナスを深掘りしており、価格競争の激化や在庫調整が収益を圧迫しています。
為替と対外環境も見逃せません。米中の通商休戦延長で当面の混乱は避けられているものの、関税リスクは常にくすぶります。輸出の先取り効果が剥落すれば外需の風向きは変わりやすく、人民元は対ドルで弱含みが続く公算です。もっとも、中国側は家電・自動車の買い替え補助といった家計テコ入れ策を継続する姿勢を示しており、「外需でつなぎつつ、消費で底固め」という当面の運営方針は明確です。
日本:金利正常化の「ゆっくりした坂道」と円安の持続、ただし転換点への備えも
日本は、インフレ鈍化と賃上げ定着をにらみながら、極めて緩やかな金融正常化を続けています。直近の東京都区部コアCPIは7月に前年比2.9%と目標を上回る伸びを保ち、日銀内では将来の追加引き上げを視野に入れた議論も散見されますが、8月会合では政策金利0.5%の据え置きが決まりました。
実体経済はセクターごとの差が鮮明です。製造業は6月に1年1か月ぶりの拡大に転じたものの、7月は再び50を割り込み、受注の弱さが表面化しました。一方、サービスは7月に53.6と拡大ペースを高め、内需の底堅さを示しています。観光や対面サービスの回復が全体を支える一方、輸出関連は世界的なサイクル鈍化や相互関税の不確実性の影響を受けやすい構図が続きます。
為替は足元で、「140円台〜150円台」という円安レンジが定着しています。今後、米国が利下げに踏み出すにつれて日米金利差はじわじわ縮まる見通しで、円の戻り余地が意識される場面も増えるでしょう。もっとも、賃金と物価の持続的な関係がなお検証段階にある日本では、日銀の引き締めテンポは限定的との見方がコンセンサスで、当面は「高止まりする円安圏」と「不意の円高反転リスク」の両方を前提に資産設計を行うのが現実的です。
貿易面の展開は月次で変化しますが、資源価格の落ち着きと内需の底堅さの組み合わせが、企業マージンと家計の実質購買力を支えている一方で、輸入原材料に依存する業種や価格転嫁力の弱い中小企業はコスト圧力が残り、個別銘柄の差は大きくなりがちです。そのため、投資家としては、円安メリットが利益に直結する輸出・観光関連と、円安でもコスト高の痛みが薄いディフェンシブ内需を使い分ける目線が重要になります。
株式・債券・為替のマーケット見通し
景気や物価、金利の方向感が同時に入れ替わる年は、相場の「主役」が季節ごとに変わります。2025年後半マーケット予想は、その入れ替わりが特に起こりやすい時期です。ここでは、米国株、米国債、為替(ドル円)、日本株の順に、いま見えている流れと注意点を整理します。
米国株:上がる理由も下がる理由もある。鍵は「銘柄えらび」と「買い方」
米国株は「利下げが続きそう」という期待に支えられやすい一方で、「景気が少しずつ息切れしてきた」サインも垣間見えます。結果として、全体で大きく上がるというより、強い銘柄と弱い銘柄の差が広がる相場になりがちです。たとえば、AIを材料にした半導体やソフトウェアなど、将来の成長がはっきり見える企業には資金が集まりやすい一方、消費に敏感な小売や耐久財は、家計が節約モードに入ると売上が伸びにくくなり、値動きが重くなります。
富裕層の視点では、短期の上げ下げで判断せず、「景気がゆっくりになる環境でも利益を積み上げやすい業種」をコアに据えるのが現実的です。具体的には、薬や医療サービスなどのヘルスケア、料金収入が安定しやすいインフラ関連、そして、手元資金を厚く持つ大企業の高配当銘柄は、荒れた相場でも持ちこたえやすい柱になります。買い方も大切で、まとまった資金を一度に入れるより、数回に分けて同じ金額で購入する方が、値動きのブレを和らげられます。
米国債:いまの利回りを「固定」できる魅力と、あとで困る「再投資」の悩み
債券は、金利が高いときに買えば、その利回りを償還まで固定できる点が魅力です。市場の金利見通しでは「金利はこれから少しずつ下がるかもしれない」という見方が広がっており、金利が下がる前に今の利回りを確保しておこうという動きが目立ちます。
ただし、償還を迎えたあと同じ条件で運用を続けようとすると、次に買う債券の利回りが下がっているかもしれません。これが「再投資リスク」です。米国債投資戦略としては、長い年限の債券だけに偏らず、短めの債券も混ぜておき、数年後に来る満期を階段のように分散させておくと、その時々の金利に合わせて柔軟に組み替えができます。富裕層の資産運用としては一部を現金で残しておくと、のちのチャンスを拾うことが可能です。
為替見通し 2025(ドル円):150円近辺の円安は味方にもなるが、逆回転に備えるほど強い
足元のドル円は150円近辺。米国がゆっくり利下げ、日本は小幅な利上げを慎重に続ける、という組み合わせなら、日米の金利差はじわじわ縮んでいきます。差が縮めば、円安の勢いは以前より落ち着きやすく、材料次第では130円方向へ動く場面も想定されます。一方で、米国の景気が想像以上に粘り強かったり、地政学リスクで安全通貨としてドルが買われたりすれば、155円方向まで円安が進行することもあり得ます。
為替見通しにおいては不確実性が高いことから、外貨建て資産を多く持つときは、この往復に備えるだけで結果が変わります。リスクヘッジを0%か100%の二択にせず、50%〜70%等の範囲で段階的にかけておくと、円高に振れたときの評価減を抑えつつ、円安の追い風もある程度は残せます。例えば、1億円のうち5,000万円をドル建てで持っているなら、半分だけヘッジしておくイメージです。
日本株:円安メリットは残るが「二極化」に注意。配当と自社株買いが心の支え
日本株は、円安の追い風が輸出企業の収益を底上げする一方、輸入コストの上昇が重荷になる業種もあり、どうしても明暗が分かれます。自動車や機械などの輸出は為替の恩恵を受けやすい一方、原材料を多く輸入する小売・外食などはコスト転嫁の力が弱いと利益が削られやすい。つまり、「円安だから全部買い」という単純な話ではありません。
ここで頼りになるのが、配当と自社株買いの姿勢です。近年は株主還元を積極化する企業が増えています。利益が多少ぶれても、配当と自社株買いの土台がある企業は、株価の下支えが期待できます。また、観光やインバウンドの回復は内需にも追い風で、為替の影響を受けにくい電力や通信といった生活インフラ系は、景気が揺れる局面のクッションになりやすい存在です。
全体に通じる「落とし穴」と「コツ」
2025年後半のマーケットでは、「利回りが高いから」「円安が続いているから」といった単純な理由だけで動くと、思わぬ逆風にさらされます。見ておきたいのは、金利・為替・期間の3つの掛け算です。たとえば、米国債を買うときは、いまの利回り(=金利)だけでなく、為替が逆方向に動いたときの影響、償還までの長さ(=期間)によって値動きの大きさがどう変わるか、の三点セットで考えるだけで判断の質が上がります。
「分散」も言い換えればシンプルです。株式は「稼ぐ力」、債券は「安定した受け取り」、現金は「次の手の自由」、金や不動産は「想定外への備え」。この役割を重ねすぎないように配分するだけで、波乱の年でも資産全体が大きく崩れにくくなります。「買うタイミングは、何度かに分ける」、「為替の保険は、ゼロかフルではなく、真ん中を広く使う」これが、今のマーケットで無理をしない勝ち方です。
富裕層が考えるべき資産配分とリスク管理
2025年後半に向けて資産を整える際は、為替と金利の両方が動く前提で計画を立てておくことが大切です。足元のドル円は150円近辺で、外貨建て資産は円換算で大きく見えやすい反面、円高に戻った時の揺れも大きくなります。無理なく続けられる設計にするために、まずは現金の見取り図をつくります。今後24か月の生活費や事業費、税金や教育費などを月ごとに置き、すぐ使うお金、1年以内に使うお金、当面使わないお金という3つの層に分けます。最初の層は円の現金や短期の安全資産でしっかり確保し、次の層は値動きの小さい円資産を中心に置き、最後の長期部分だけを増やす目的で動かします。こうしておくと、相場が荒れても必要資金のために売らされる場面が減ります。
通貨の配分は、目安の比率と許容の幅を先に決めておくと迷いが少なくなります。たとえば外貨の比率を40%前後に置き、上振れや下振れが大きくなったら数回に分けて元に戻します。為替の保険は全額かける必要はありません。外貨建て債券や外貨の現金の一部に保険をかけ、比率は50%を出発点に、相場が極端な水準に来たら少し厚く、落ち着けば薄く戻すといった運用が扱いやすいです。総資産1億円で、そのうち外貨が5,000万円あると仮定すると、ドル円が150円から140円へ変動すると円換算でおよそ500万円の目減りになりますが、半分に保険をかけていれば影響は概ね半分に抑えられます。保険のコストは時期により変わりますが、いまは比較的落ち着いた水準ですので、安心料としての効果は得やすい局面です。
債券は償還までの長さを分けて持つのが基本です。短めと長めを混ぜておくと、毎年のように償還が巡り、その時の金利で自然に組み替えられます。金利がゆっくり下がる方向なら、やや長めの比率を増やして今の利回りを確保し、逆の局面では短めを厚くして次の機会を狙います。個々の商品に深く悩むよりも、全体としての平均の長さを一定の範囲で保つ意識の方が、値動きと再投資の両面を管理しやすくなります。
株式はテーマよりも体質で選ぶと安定します。景気の波があっても利益を出し続けているか、借入に過度に頼っていないか、手元資金から配当や自社株買いを無理なく続けられるかという基本を数年分の実績で確かめます。為替の恩恵を受けやすい輸出企業と、価格転嫁ができる内需企業を並走させると、円安が続くときも円高に戻るときも全体のバランスが取りやすくなります。購入は一度にまとめず、数回に分けて同額で積み上げると取得単価が平準化し、心理的にも安定します。
金や不動産に連動するオルタナティブ資産は、いざというときの備えとして少量でも効果があります。金は地政学やインフレが意識される場面で機能しやすく、全体の3%〜5%を目安に置くと安心感が違います。不動産関連の商品は、賃料の通貨や改定の仕組み、流動性の条件を先に確認し、偏りすぎない範囲で組み入れます。換金に時間がかかるものは、資産全体の10%を超えない水準から始めると無理がありません。
最後に、非常時の手順を簡単に書き出しておくことをおすすめします。市場が急落した、為替が短期間に大きく動いた、想定外の資金が必要になったといった場面で、どの資産をどの順番でどれくらい動かすのか、誰に連絡するのかを1枚にまとめます。準備があるだけで、焦りからの誤った行動は確実に減るはずです。円安が続く局面でも、円高に戻る局面でも、こうした手順があれば資産は大きくぶれにくくなります。
富裕層資産運用 2025の動き方のヒント
富裕層の資産戦略では、マーケットの短期的な動きに振り回されず、冷静かつ計画的にポジションを動かすことが重要です。そのためには、まず「現状把握」と「シナリオ分析」を徹底します。
現状把握では、保有資産を通貨別・資産クラス別に整理し、各割合を円グラフなどで可視化します。そして、為替や金利の変動がどの部分にどれだけの影響を与えるかを数値化します。たとえば、円安がさらに進み155円になった場合と、逆に145円まで円高が進んだ場合の評価額の差、米国株が10%下落した場合の影響などをあらかじめ試算しておくのです。
次に、シナリオ分析です。2025年後半は「米国の利下げペースが加速するシナリオ」「日銀が追加利上げを行うシナリオ」「地政学リスクで原油価格が急騰するシナリオ」など、複数の想定を立て、それぞれに対してどのような行動を取るか事前に決めておきます。こうした準備があるだけで、市場が急変したときの判断速度と精度が格段に向上します。
資産配分の変更は、一度に大きく動かすのではなく、3〜6か月に分けて段階的に実行します。たとえば、米国債投資戦略としては、毎月一定額を買い付ける「時間分散」を行うことで、金利変動リスクを平準化できます。株式の売却や買い増しも同様に、小分けで実行することでタイミングの失敗リスクを軽減できます。
情報収集の習慣も欠かせません。金融機関の提案だけでなく、独立系アドバイザーや海外の経済ニュース、企業決算など多角的な情報源を持つことで、特定の立場や商品に偏った判断を避けられます。また、情報は「鮮度」と「信頼性」の両方を意識し、短期の市場騒ぎに過剰反応しないためのフィルターを自分の中に持つことが重要です。
最後に、2025年後半は「守り」と「仕込み」を同時に行うことができる稀有な時期です。利下げ局面での債券の魅力を享受しつつ、為替や株式の反転局面に備えて現金ポジションも一定程度保持する。これにより、突発的な市場の変動が逆に投資機会となる環境を作ることができます。「富裕層資産運用2025」にとっては、こうした余力のある待ち方が長期的な資産形成において大きな差を生みます。
2025年後半の注目イベントと市場への影響
2025年後半は、複数の重要イベントが市場の変動要因となります。9月と12月にはFOMCが予定されており、利下げペースや政策声明のトーンが株式・債券・為替市場に大きな影響を与えます。日銀の金融政策決定会合は10月と12月に開催され、追加利上げの可能性や長期国債買い入れ方針の変更が円相場を動かす要因になります。
さらに、トランプ政権下での政策において、関税と減税のベクトルが企業収益と物価に同時作用します。全輸入に一律10%の基準関税や相手国別の上乗せでコスト上振れと報復リスクが続き、ドルと長期金利の振れが大きくなりやすいです。一方、下院を通過した減税延長は家計と企業の手取りを下支えしますが、中期の財政負担は重くなるなど、経済にとってプラスになる要因とマイナスになる要因が入り交じっている状況です。不透明感が強い局面ではリスク分散、或いは減らす方針が選好されます。
中国では10月に共産党の重要会議が予定されており、不動産市場の安定化策や人民元の為替政策に関する発表が注目されます。これらの政策はアジア全体の株式市場や為替市場に波及する可能性があるため、事前に情報を収集しておくことが重要です。
まとめ
2025年後半マーケット予想は、利下げ、円高、景気減速という三つの大きな流れが同時に進む可能性が高く、富裕層にとって資産を守りつつ成長機会を見極める難しい局面です。為替変動リスクを軽減し、債券の利回りを確保しつつ、株式ではセクターと地域を慎重に選別することが成功の条件となります。
判断を誤れば、利回りの取り逃しや円高による評価損が資産に直接響きます。不安を解消するために専門家に相談し、ポートフォリオ全体の見直しを検討することで、変動の大きな市場を一緒に乗り切りましょう。2025年後半は「守り」と「仕込み」を同時に行う時期であり、ここでの判断が今後数年間の資産形成の成否を分けることになります。

株式会社ウェルス・パートナー
ポートフォリオマネージャー
早稲田大学商学部卒業後、株式会社群馬銀行へ入社。富裕層と会社経営者を中心とした資産運用のコンサルティング業務に従事。銀行での提案には限界があると感じ、もっと付加価値の高い提案をしたいと思い株式会社ウェルスパートナーに入社。富裕層、会社経営者の資産配分最適化や具体的な金融資産の投資実行サポートを行う。