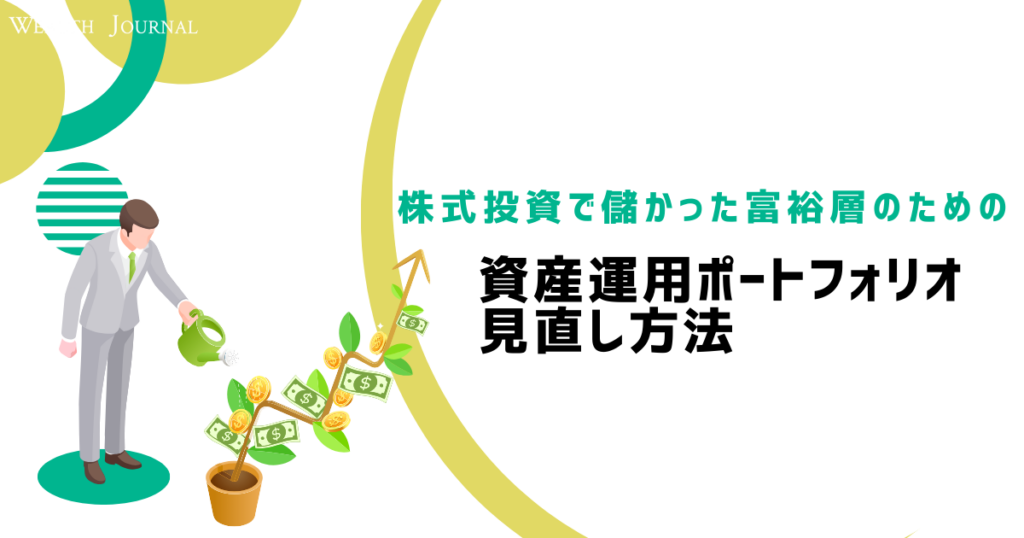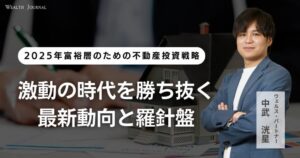株式投資で大きな成果を得た富裕層にとって、本当の課題はその後の資産運用です。成功体験に基づく過信や株式偏重は、一瞬で資産を失う落とし穴となりかねません。本記事では、典型的な失敗例と回避策を紹介し、IFA活用による中立的な立場からの資産配分見直しの重要性を解説します。
目次
株式で成功した富裕層が陥る3つの落とし穴
株式投資で大きな成功を収めた方の多くは、マーケットの波をうまく捉え、資産を短期間で大きく増やしてきた経験を持っています。特に近年では、コロナ禍後の世界的な株価上昇局面で莫大な含み益を得た富裕層も少なくありません。しかし、その後の資産運用においては「成功体験がもたらす心理的な落とし穴」に注意する必要があります。ここでは、典型的な3つの落とし穴について見ていきましょう。
1. 利益確定を先延ばしにして暴落で半減
株式投資で含み益を得た際、多くの投資家が悩むのが「売却のタイミング」です。実際に、株価が順調に上がっている局面では「まだ上がるかもしれない」「売ったらその後の上昇を逃してしまうのでは」という心理が強く働きます。その結果、利益を確定させる判断が後回しになり、相場の急落で一気に資産を減らしてしまうケースが少なくありません。
これは単に「売却のタイミングが悪かった」というだけではなく、人間の心理的なバイアスも影響しています。行動経済学では「プロスペクト理論」によって、人は利益を確定するよりも損失を回避したい心理が強いと説明されています。つまり、利益が出ている間は「もっと伸ばせる」と期待し、売却をためらってしまう傾向があるのです。
こうした状況を避けるには、あらかじめ利益確定のルールを決めておく、あるいは一部を段階的に売却して利益を実現させるといった方法が有効とされています。特に資産規模が大きい場合、ポートフォリオ全体のバランスを見ながら「守りの戦略」を同時に検討する必要があるでしょう。
2. 株式以外に興味を持たず、資産が偏在
次に多いのが、資産のほとんどを株式に集中させてしまうケースです。株式投資で大きな成功を収めた方ほど、「やはり株式が一番効率的に増やせる」と考え、株式以外の資産に目を向けにくくなります。
たとえば、総資産が3億円あり、そのうち8割を株式に投じているとしましょう。この場合、株式市場が好調であれば大きなリターンを得られますが、逆に相場が下落すると資産全体が急速に目減りしてしまいます。さらに、株式だけに依存していると、為替変動リスクや金利変動、地政学的リスクといった外部要因にも過度に影響を受けやすくなります。
分散投資の基本は「異なる値動きをする資産を組み合わせること」です。株式のほかに、債券、不動産、コモディティ(商品)、あるいは現金や外貨資産を適切に組み込むことで、相場環境に左右されにくい安定したポートフォリオを築くことができます。富裕層にとっては、資産全体を守る観点からも「株式一辺倒」から脱却することが重要だといえるでしょう。
実際、長期的に資産を維持しているファミリーオフィスや海外の富裕層は、株式だけでなく複数の資産クラスに投資を分散していることが一般的です。株式で成功した方ほど、あえて「株式以外」にも関心を持つことが資産防衛の第一歩になると考えられます。
3. 成功体験の過信でリスクを取りすぎる
3つ目の落とし穴は、過去の成功体験に基づく「過信」です。株式投資で何度も大きなリターンを得た方は、「自分は相場を読む力がある」と考えがちです。その結果、信用取引やレバレッジを使った取引に踏み込み、想定以上のリスクを取ってしまうケースが見られます。
もちろん、一定のリスクを取ることがリターンの源泉になる場合もあります。しかし、レバレッジ取引は資産を増やすスピードが早い反面、損失が出たときにそのスピードも加速します。特に富裕層の場合、運用する金額そのものが大きいため、わずかな下落でも絶対額にすると巨額の損失につながる可能性があります。
さらに厄介なのは、成功体験が「判断のブレーキ」を弱めてしまう点です。過去に大きく資産を増やした経験があると、「今回もきっと同じように勝てるはず」と思い込みやすくなります。これが心理的なバイアスとなり、冷静な判断を失わせるのです。
資産規模が大きいほど、リスクを取りすぎた場合のダメージは甚大になります。成功を維持するためには「自分のリスク許容度を正しく把握し、分散やヘッジを組み合わせる」ことが重要です。
ポートフォリオ見直しの基本原則 ― 守りと攻めのバランス
株式投資で数億円規模の資産を築いた方にとって、次の課題は「いかに資産を減らさずに維持・承継していくか」です。投資を始めた頃は「いかに資産を増やすか」が最優先になりがちですが、一定以上の規模に達した時点で、その発想は大きく転換する必要があります。
特に5億円、10億円といった規模になると、生活水準を大きく変える必要がない場合も多く、資産の一部が減るだけでも心理的ダメージや次世代への影響が大きくなります。そのため、「守りを固める運用」と「成長を狙う運用」の両立が求められるのです。
株式依存からの脱却 ― 安定資産を組み込む
多くの富裕層が資産を築いたのは株式市場での成功体験です。しかし、株式だけに依存したポートフォリオは、市場環境の変化に大きく左右されます。株式は高いリターンが期待できる一方で、リスクも高く、暴落時には資産全体が大きく揺さぶられます。
そこで重要となるのが「株式以外の資産」を組み込むことです。たとえば以下のような安定資産が選択肢になります。
| 資産クラス | 特徴 |
| 債券 | 一般的には国債や社債は株式とは異なる値動きとされる。定期的な利息収入が期待できる。特に米ドル建て外債は富裕層に人気で通貨分散にも有効。 |
| 不動産 | 国内外の不動産を組み入れることで、賃料収入(インカムゲイン)やインフレヘッジ効果が得られる。現物だけでなくREITも選択肢。 |
| 外貨資産 | 米ドル・ユーロなどの外貨を保有することで、円安局面では円の資産価値の目減りを防止する効果。 |
株式依存から脱却し、安定資産を増やすことは、資産規模が大きい方ほど重要な戦略といえるでしょう。
富裕層向けの配分例 ― 5億円以上の資産を持つ場合
資産規模が数千万円程度であれば「資産を増やす」比重が高くてもよいかもしれませんが、5億円以上を保有している場合は「増やす」よりも「減らさない」ことが優先されます。そのためには、資産配分(アセットアロケーション)を戦略的に設計することが欠かせません。
一例として挙げられるのが、以下のような配分です。
| 資産クラス | 配分 | 特徴 |
| 株式 | 30% | 成長余地を取り込むために一定の株式比率は残す。ただし集中投資ではなく、グローバル株式やセクター分散を意識。 |
| 債券 | 40% | 安定した利回りを得つつ、資産全体のボラティリティを抑える。外国債・国内債の組み合わせが効果的。 |
| 不動産 | 20% | 賃料収入や物価上昇局面での価値維持を狙う。実物不動産とREITの組み合わせも検討される。 |
| オルタナティブ投資 | 10% | ヘッジファンドやプライベートエクイティ、コモディティなど、株式や債券など伝統的資産とは低い相関を持つ資産を加える。 |
もちろん、この配分は一例にすぎません。投資目的、年齢、リスク許容度によって最適なバランスは異なりますが、重要なのは「株式偏重からの脱却」と「複数の資産クラスを組み合わせること」です。
現金ポジションを活かしたリバランスの重要性
忘れがちですが、富裕層にとって「現金」を一定割合で持つことも大切です。現金はリターンを生まないと考えられがちですが、以下のような役割を果たします。
- 相場下落時の買い増し余力
株式市場や不動産市場が急落したときに、現金があれば割安なタイミングで追加投資が可能になります。 - 生活費や事業資金の安定供給
現金を一定量確保しておくことで、急な出費や事業の資金繰りに柔軟に対応できます。 - リスク資産の比率調整(リバランス)
株式市場が上昇すれば運用資産のなかで株式比率が自然に高まり、逆に下落すれば比率が下がります。現金ポジションを活用して、定期的に「当初決めた配分」に戻すことで、資産全体のリスクを安定させることができます。
リバランスは地味な作業に見えますが、長期的に見ると「守りながら安定的に増やす」ための重要な仕組みとなります。富裕層ほど資産規模が大きいため、わずかな比率の変動が大きな金額差につながります。だからこそ、定期的なチェックと調整が欠かせません。
富裕層が実践すべき分散投資戦略
資産規模が数億円を超える富裕層にとって、重要なテーマは「いかにして安定性と成長性を両立させるか」です。株式投資で資産を増やした後は、その成功体験を引きずらず、幅広い資産クラスを組み合わせることが求められます。ここでは、富裕層が実際に取り入れることの多い代表的な分散投資戦略について整理してみましょう。
1. 債券投資 ― 米ドル建て外債による安定利回り確保
債券は、株式と比べて値動きが安定しており、定期的な利息収入が得られる点が特徴です。特に富裕層に人気が高いのが「米ドル建て外債」です。
米ドル建て外債が選ばれる理由
- 世界的な基軸通貨である米ドル:資産を円だけでなくドルで保有することで、通貨分散の効果を得られる。
- 相対的に高い利回り:日本国内の金利が長らく低水準にある中、米ドル建て外債は比較的高いクーポン(金利収入)が期待できる。
- 信用度の高い発行体:米国債や格付けの高い企業の社債などは、安全性を意識する富裕層にとって魅力的な選択肢になりやすい。
ただし、為替変動によるリスクもあるため、為替ヘッジを行うかどうかは資産全体の設計によって判断する必要があります。米ドル資産をあえて「そのまま保有」することで円安時にメリットを享受する方もいれば、安定性を優先して為替ヘッジを選ぶ方もいます。
2. 不動産投資 ― インカムゲインとインフレ対策
不動産もまた、富裕層のポートフォリオで重要な位置を占める資産です。特に株式や債券とは異なる性質を持ち、「安定収益」と「インフレ対応力」という2つの効果が期待できます。
不動産のメリット
- インカムゲイン(賃料収入):保有することで継続的に現金収入が得られる。生活費や事業資金の安定供給にもつながる。
- インフレ対策:物価上昇局面では、土地や建物の価値が上がりやすく、実質的な資産防衛の役割を果たす。
- 相続・承継の観点:不動産は相続時の評価が現金より低くなる場合があり、相続税対策の一環として組み込まれることもある。
実物不動産を直接所有するだけでなく、REIT(不動産投資信託)を活用すれば流動性の高い形で投資が可能です。国内不動産だけでなく、海外の不動産に分散することで、地域的なリスクヘッジにもつながります。
3. オルタナティブ投資 ― 低相関を狙う選択肢
オルタナティブ投資とは、株式や債券といった伝統的資産に加えて投資される代替資産の総称です。代表的なものにヘッジファンドやプライベート・エクイティ(PEファンド)、コモディティ(商品)、インフラ投資などがあります。
ヘッジファンド・PEファンドの特徴
- ヘッジファンド:市場が下落しても収益機会を狙える戦略を持ち、相場の影響を和らげる可能性がある。
- PEファンド:未上場企業や成長企業に投資することで、上場株式とは異なるリターン源泉を取り込める。
富裕層にとっての魅力は「株式市場と低い相関を持つ」という点です。株価が下落しても影響を受けにくい資産をポートフォリオに加えることで、より分散効果を高めようとするものです。
ただし、オルタナティブ投資は流動性が低い場合も多く、長期的な資金拘束を伴うケースがあります。そのため、資産規模が十分に大きい富裕層だからこそ取り入れやすい選択肢といえるでしょう。
4. 外貨資産 ― グローバルな通貨分散
富裕層の資産形成においては、通貨の分散も大きなテーマとなります。日本円に集中していると、円安が進んだ場合に購買力が低下し、海外での消費や投資に不利になることがあります。逆に円高になれば海外資産の評価額が下がることもあり、為替の変動は無視できません。
通貨分散のポイント
- 米ドル:基軸通貨として安定性があり、国際的な投資や消費に幅広く活用できる。
- ユーロ:欧州経済圏での取引や投資に有効。
- その他の外貨:スイスフランや豪ドルなど、資源や金融システムに強みを持つ通貨を組み合わせることでリスク分散。
富裕層の中には、海外不動産や外債への投資を通じて自然に外貨資産を増やしている方もいます。重要なのは「どの通貨をどの程度保有するか」を全体の資産戦略に合わせて設計することです。
実際の失敗例と再構築事例
理論として分散投資の重要性を理解していても、実際には「成功体験」や「市場環境への期待」によって判断を誤ってしまうことがあります。特に富裕層の場合、運用金額そのものが大きいため、わずかな比率の偏りや判断ミスが巨額の損失につながることも少なくありません。ここでは、実際によく見られる3つの事例を通じて、どのような失敗が起こり、どのように再構築されたのかを見ていきましょう。
事例①:60代経営者 ― 株式比率80%で資産が半減
ある60代の経営者は、長年事業で築いた資金を株式投資に積極的に振り向けていました。資産総額3億円のうち、実に8割を株式で保有していたのです。株式市場が好調なときは、配当収入に加え含み益も膨らみ、「このまま運用すれば老後も十分安泰」と考えていました。
しかし、世界的な景気後退や金融危機級の下落が訪れた際、株式市場は急落。資産は一時的に1.5億円にまで縮小しました。これまでの成功体験があっただけに、「一時的な下げだから回復するはず」と考えてしまい、売却の判断が遅れたのです。
その後、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に相談することで、資産の再構築が進みました。株式比率を下げ、債券や不動産を組み込むことで、安定収益と値動きの緩和を実現。特に、米ドル建て債券から得られる利息収入や、賃料収入のある不動産を加えたことで、景気に左右されにくい資産構成に切り替えることができました。結果的に「守りと攻めのバランス」を持つポートフォリオへと進化したのです。
事例②:50代医師 ― テック株集中からレバレッジで失速
次の事例は、50代の開業医です。医師としての安定収入があることもあり、余裕資金のほとんどを米国のテクノロジー株に集中投資していました。ちょうどテック株が急成長した時期で、数年のうちに資産は倍増。株式投資の成功体験が自信につながり、「自分は市場を読む力がある」と考えるようになりました。
その後、さらなる利益を狙って信用取引やレバレッジを活用。短期的には大きな利益を得ましたが、相場が調整局面に入った際に資産は一気に半減しました。半年で資産が元の水準に戻ってしまったのです。
冷静に考えれば、テック株の値動きはボラティリティが高く、レバレッジをかけることでリスクは何倍にも増大していました。しかし成功体験の勢いが判断を鈍らせてしまったといえます。
その後はIFAの助言を受け、株式比率を30%程度に縮小。残りは外債や外貨建て生命保険など、安定的な資産に分散しました。これにより、為替変動リスクをヘッジしつつ、景気変動の影響を抑えた堅実なポートフォリオへと再構築することができました。
事例③:40代起業家 ― 上場益10億円を「現金と株式」で放置
最後は、40代の起業家です。自身が立ち上げた企業が上場し、まとまった株式売却益を得て、10億円もの資産を保有しました。しかし、事業に集中していたこともあり、その後の資産管理について深く考える時間を取れなかったのです。
結果として、資産は「上場株式と現金」のみで放置されたままになりました。数年間は特に問題はありませんでしたが、インフレや円安の進行によって、実質的な資産価値は目減りしていきました。見た目の数字は変わらなくても、購買力ベースでは資産が減っていたのです。
IFAに相談した結果、分散投資と同時に「資産承継対策」にも着手しました。具体的には、不動産や外債をポートフォリオに組み入れる一方で、相続税対策を意識した信託スキームを導入。これにより、資産を守るだけでなく、次世代にスムーズに承継できる体制が整えられました。
事例から得られる教訓
これら3つの事例に共通するのは、「成功体験に依存しすぎた結果、リスク管理が後回しになった」という点です。
- 株式に偏りすぎると、市場環境の変化で一気に資産が減る
- レバレッジや集中投資は、一度の失敗で資産規模が大きく縮小する可能性がある
- 「株式+現金」のみの放置は、インフレや為替変動に弱く、実質的な価値を減らす要因になる
富裕層にとって重要なのは、これらの経験から学び、次のステージで「守りと成長のバランスを持つ運用」に切り替えることです。そのためには、中立的な立場から助言できるIFAのような専門家のサポートを活用することが有効だといえるでしょう。
IFAを活用したポートフォリオ見直しのメリット
資産運用において「誰に相談するか」は、投資成果と同じくらい重要なテーマです。特に富裕層の場合、資産規模が大きいため、運用戦略の一つひとつが将来の生活や次世代への承継に直結します。そのため、中立的かつ長期的な視点を持つ相談先を選ぶことが欠かせません。ここでは、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)を活用することで得られるメリットについて整理します。
1. 金融機関に縛られない中立的な提案
銀行や証券会社に所属する担当者は、それぞれの組織が扱う商品を中心に提案を行うことがあります。もちろん、それが必ずしも悪いわけではありませんが、営業担当者によっては「自社商品ありき」の提案になりやすい側面があります。
一方で、IFAは特定の金融機関に縛られない立場で活動しています。複数の証券会社や運用機関と提携しているIFAも多く、顧客にとってより幅広い選択肢の中から提案を行えることが特徴です。
たとえば「株式比率を下げたいが、どの債券を組み合わせるべきか」「外貨資産を取り入れたいが、為替変動リスクのコントロールをどうすべきか」といった相談に対して、IFAは顧客の資産規模や目的に合わせて柔軟にプランニングすることができます。商品ありきではなく「顧客の資産をどう守り、どう成長させるか」という視点が中心になるため、中立的なアドバイスを期待できる点が大きなメリットといえるでしょう。
2. 富裕層特有の課題に対応可能
富裕層が抱える悩みは、一般的な投資相談とは異なります。単に資産を増やすだけでなく、以下のような複合的なテーマを同時に考える必要があります。
- 相続対策:相続税の負担を軽減する仕組みや、資産を分割して承継するための設計。
- 事業承継:経営者の場合、会社株式をどのように次世代に引き継ぐか。
- 税務:投資収益にかかる税金だけでなく、所得税や贈与税、海外投資に関わる税制までを総合的に検討。
銀行や証券会社でも一定のサポートはありますが、IFAはより顧客の立場に近い形で、これらの課題に対応するプランニングを行うことが可能です。必要に応じて、弁護士・税理士・会計士などの専門家と連携して総合的な解決策を提示するIFAもいます。富裕層にとっては「資産運用=投資」だけでなく「資産管理=包括的な仕組みづくり」が不可欠であり、その橋渡し役を果たすのがIFAの大きな役割です。
3. 長期的な伴走と定期的リバランスの実行力
資産運用は一度ポートフォリオを組んで終わりではありません。市場環境は日々変化し、数年単位で見れば金利、為替、地政学リスクなど大きな潮流が資産価値に影響を与えます。そのため、定期的にポートフォリオを見直し、リバランスを行うことが欠かせません。
IFAの特徴は、短期的な販売ノルマに縛られず、顧客と長期的に伴走する姿勢を持っている点です。半年や1年ごとの定期面談を通じて、資産状況の変化や生活環境の変化に合わせた調整を提案してくれます。
たとえば、
- 株式市場の上昇で比率が高くなりすぎた部分を債券に振り替える
- 為替の変動が大きい時期に外貨資産の割合を見直す
- 将来的な相続を見据えて、資産を流動性のある形にシフトする
こうしたリバランスは、投資家本人が自己判断で行うには難しいこともありますが、IFAが定期的に伴走してくれることで継続的に実行しやすくなります。
4. プライベートバンク・証券会社との違い
富裕層の相談先としては、プライベートバンクや大手証券会社も候補に挙げられます。それぞれに強みがありますが、IFAとは性質が異なります。
- プライベートバンク
グローバルネットワークや専門的な商品ラインナップを持ち、総合的な資産管理を提供。ただし、一定以上の資産規模(数億円〜数十億円)を条件とする場合が多く、提案が金融機関の方針に影響されることもあります。 - 証券会社
投資商品の提供力やマーケット情報の豊富さが強み。ただし、販売方針や推奨商品が限定されることもあるため、顧客本位の選択肢が狭まるリスクがあります。 - IFA
特定の金融機関に属さず、複数の選択肢から顧客に合った商品を提案可能。富裕層特有の課題に柔軟に対応できるほか、比較的少額からでも相談できる点もメリットといえるでしょう。
このように、プライベートバンクや証券会社とIFAは競合する存在ではなく、むしろ補完し合う関係にあります。顧客の目的や資産規模に応じて、複数の相談先をうまく活用することが賢明です。
まとめ
株式投資で得た大きな成果は、次の運用フェーズでは「増やす」より「守る」ことが重要になります。資産規模が大きいほど、市場の変動や判断の遅れによる損失は甚大になりかねません。成功体験の延長で株式偏重を続けたり、リスクを取りすぎたりすることは、富裕層に特有のリスクを高める要因となります。
そこで有効なのが分散投資です。株式に加えて債券、不動産、外貨資産、オルタナティブを効果的に組み合わせることで、ポートフォリオ全体の安定性を高められます。さらに定期的なリバランスによって「守りと攻めのバランス」を取り戻しやすくなります。
こうした設計を自ら継続的に行うのは容易ではないため、中立的なIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に相談する価値があります。資産配分の見直しに加え、相続や税務といった富裕層特有の課題まで視野に入れた助言を受けられる点が強みです。
まずは「現状のポートフォリオ診断」から始め、資産の偏りやリスクを客観的に把握することが、次世代へ資産を守り継ぐ第一歩となるでしょう。

株式会社ウェルス・パートナー
代表取締役 世古口 俊介
2005年4月に日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイスのプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。
2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。超富裕層のコンサルティングを行い1人での最高預かり残高は400億円。書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者1万人超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」での情報発信を通じて日本人の資産形成に貢献。医師向けサイトm3.comのDoctors LIFESTYLEマネー部門の連載ランキング人気1位。
メディア掲載情報:「m3.com」「ZUU online」「MONEY zine」「マネー現代」でコラムを連載中