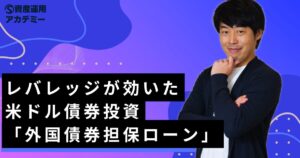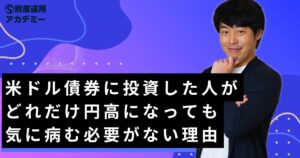はじめに
コロナ禍の中、テレワークの広がりや副業解禁の流れの中、金融機関にも働き方改革の波が押し寄せています。銀行や保険、証券などの大手金融機関も例外ではありません。今回はみずほフィナンシャルグループの働き方改革を受けて日本の金融機関の働き方がどのように変わりつつあるのかを考えていきたいと思います。
みずほフィナンシャルグループの働き方改革とは
みずほフィナンシャル・グループ(FG)は2019年10月に社員の副業を解禁しました。当時、産業界で副業解禁の流れが相次いでいましたが、金融業界ではコンプライアンス、情報セキュリティなどの面から導入に関して出遅れていたこともあり驚きをもって受け止められました。
社員は副業開始2ヶ月前の月末までに「どのような副業を」「いつから」「就労時間にしてどのくらい」「どのようなリターン(成長)が見込めるか」を申請して、審査を受けるシステムです。
承認には、いくつかの条件があり、たとえばみずほFGの業務と競合しない、ノウハウや情報が漏洩しない、「みずほ」のブランドは使わないというものです。そのほか雇用契約は結ばないことも条件としており、アルバイト・パートなどの副業ではなく、個人事業主として業務委託契約によることが必要です。
このようにみずほ銀行の副業は社員の収入補てんを目的としたものではなく、人材の成長にながる副業をOKとし、人材の活用に重きをおいた制度設計となっています。
さらに2020年12月には、週休3日制・4日制を導入し、希望者の募集を開始しました。
介護や資格取得、子育てなど多様化する働き方のニーズに対応し、副業改革として人材の確保施策としています。週3日の勤務では給与はこれまでの8割、週休4日ではこれまでの6割に減ります。
背景には金融機関を巡る環境の変化
背景には金融機関を巡る環境の変化があります。長引く低金利やフィンテックの波を受け金融機関の収益は伸び悩みが続いています。合理化により人件費を圧縮するという背景もそのひとつです。
また、銀行だけでなく証券、保険などの金融業界では若手の流出も相次いでいることもあり、人材のつなぎとめや採用強化のために働き方改革を進めることが不可欠となっています。そのような中、既存の人材の活用の強化のため、副業により得られた知見や人脈を自社の業務に活かしてほしいとする思惑も大きいでしょう。
コロナ禍もこの動きを加速させています。コロナによるテレワークの広がり、在宅勤務の増加も副業のしやすさにつながっています。テレワークで企業側も勤務地に関わらず、副業人材を募集しやすくなりました。また、通勤時間を副業にあてることが出来るようになったことも大きいでしょう。
営業活動もオンライン化が進んでいます。
顧客側においてもオンラインでのセミナー受講や資産運用の相談の利用も広がっており、密を避けられるなどのメリットの他、来店や訪問などの手間も掛かりません。保険や投資信託などの金融商品の契約もオンラインで完結できる金融機関が増えています。
業務についてもデジタル化が進んでおり、タブレットやノートパソコンで顧客データの呼び出しや金融情報の提供など自宅のテレワークでもオフィスと同様の作業が出来るようになっています。
金融機関で広がる同様の動き
このような動きは証券・保険業界など金融業界全体に広がっています。
国内証券最大手の野村ホールディングスは、大都市などの店舗の統廃合を進めて、営業人員の富裕層への再配置やコンタクトセンターへの配置転換を進めています。大和証券グループは、店舗の統廃合や間接部門から営業部門への人員の再配置により、経営の効率化を図っています。
保険業界では第一生命ホールディングスが業界では初めて、4月から約15000人の職員を対象として副業を解禁すると報じられています。
副業の希望者は申請し、みずほFGと同様に雇用契約は認めず、個人事業主として業務を委託する形の副業であれば認める方針だとしています。
また、資格取得などを目的とした休職制度の導入も検討しています。
まとめ
金融業界における働き方改革は、他の業界と同様に加速しているものと思われます。
既存の人材の活用もさることなから優秀な人材の採用に必要不可欠となっていることも背景といえます。このような流れの中で金融業界においては、テレワークなどのITスキルの他、専門スキルの獲得による自己研鑽の必要性がこれまで以上に高まっているといえるでしょう。
副業により専門スキルの習熟や社外人脈のネットワークなどいわゆる「出来る人材」の希少価値はさらに上昇します。本業の金融機関においてもこのような人材に対してはそれなりの報酬や評価で報いることが必要になります。
一方で介護や子育てなどのライフスタイルの多様化も進むと見られ、旧来より言い古されているワードではありますが、「人材の活用」に成功した金融機関とそうでない金融機関の二極化は今後さらに進んでいくと思われます。