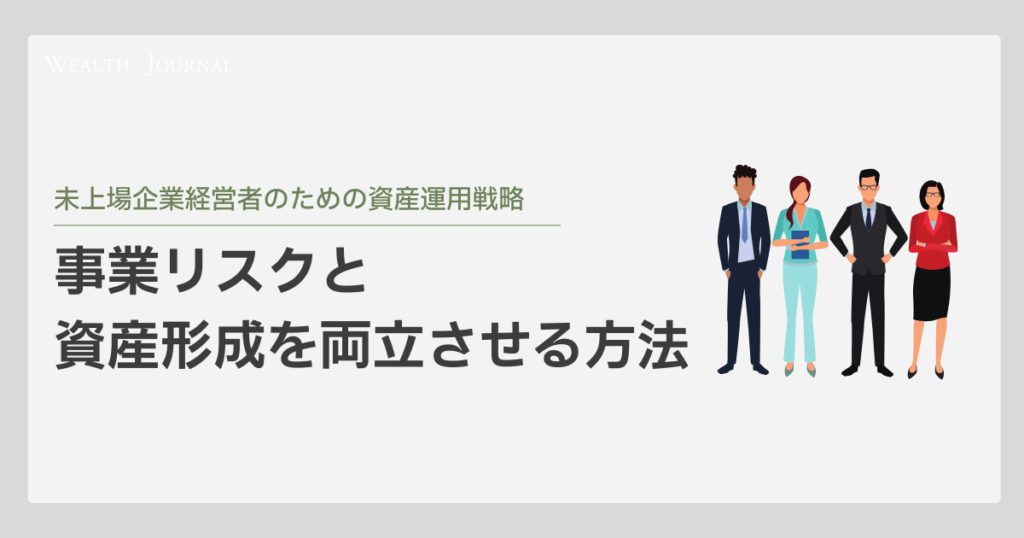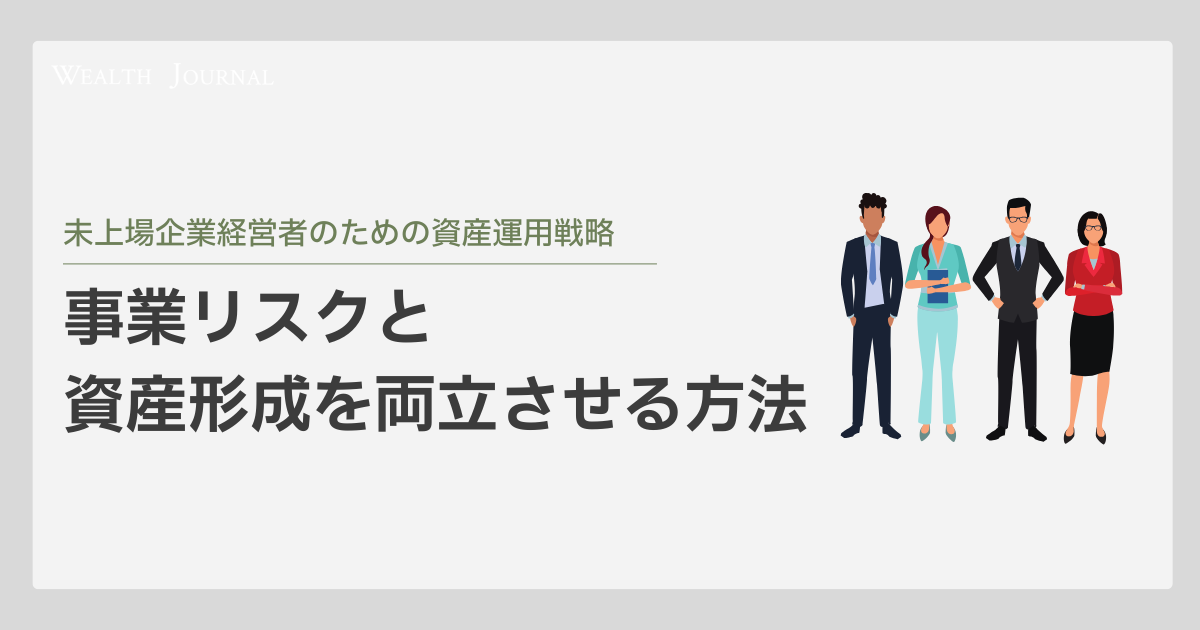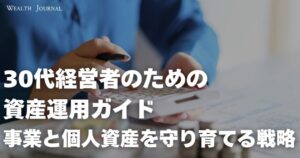未上場企業経営者にとって資産運用は、事業リスクと切り離せない独自の課題を抱えています。自社株への資産集中や会社資産と個人資産の混在は、経営不振や承継時に大きなリスクとなり得ます。本記事では、事業と資産を分離した運用の重要性と、安定収益を確保するための具体的な戦略を解説します。
未上場企業経営者が直面する資産運用の課題
未上場企業の経営者にとって、資産運用は一般的な個人投資家とは異なる独自の難しさを伴います。特に「自社株に資産が集中しやすいこと」「会社資産と個人資産の境界があいまいになりやすいこと」「金融機関の提案が必ずしも中立的でないこと」が代表的な課題です。本章では、それぞれのリスクと背景を整理しながら、なぜ「経営と資産運用を一体で考えると危ういのか」を掘り下げていきます。
自社株への資産集中 事業不振=資産価値の毀損リスク
未上場企業の経営者の多くは、自社株で資産の大半を保有しています。会社の成長とともに株式の評価額が上昇すれば紙面上の資産は膨らみますが、その価値は事業の安定性に強く依存しています。
上場企業の株式であれば、一定の流動性が確保されており、必要に応じて一部を売却して資金化できます。しかし未上場株は市場で簡単に売却できず、相対取引やM&Aを通じた第三者への譲渡が中心となります。そのため「資産はあるが現金化できない」という状態に陥りやすいのです。
加えて、自社の経営が悪化した場合は資産価値そのものが毀損されます。例えば、主要取引先の倒産や業界の構造変化などによって業績が落ち込むと、自社株の評価額は大幅に減少する可能性があります。経営者個人の資産が自社株に集中している場合、事業リスクがそのまま個人の資産リスクに直結するのです。
会社資産と個人資産の混在 税務・承継の観点からも不安定
中小企業のオーナー経営者にとって、会社資産と個人資産の境界があいまいになりやすい点も大きな課題です。会社名義の不動産や社用車を私的に利用していたり、余剰資金を経営者個人の判断で運用に回したりするケースは珍しくありません。
一見すると柔軟に資産を使えるメリットがあるように思えますが、税務や事業承継の場面では大きな問題を引き起こします。例えば、会社資産を私的に流用していると「役員報酬」として認定され、追徴課税を受ける可能性があります。また、承継時に会社資産と個人資産が入り乱れていると、後継者がどこまでを相続するのかが不透明になり、余計な争いの火種になりかねません。
さらに、金融機関や投資家と資金調達の交渉を行う際にも、会社と経営者個人の財務が混在していると信用度が下がります。資産運用を考える上でも、「会社の資産」と「経営者個人の資産」を明確に切り分けておくことは必須条件といえるでしょう。
銀行・証券会社の提案の限界 販売色が強く中立性に欠ける
多くの経営者は資産運用を検討する際、まず銀行や証券会社に相談します。彼らは専門的な知識や豊富な商品ラインナップを持っているように見えますが、必ずしも中立的な立場で提案しているとは限りません。
金融機関は自社の収益を優先するため、手数料が高い投資信託や保険商品を強く勧めることがあります。経営者側が「資産を安全に分散したい」と考えていても、提案内容が販売目標に沿ったものになりやすいのです。その結果、商品ごとのリスク構造や流動性の低さを十分に理解しないまま契約し、後から資金繰りに困るケースも見られます。
また、銀行や証券会社の担当者は異動が多く、長期的に一貫した資産運用のサポートを受けにくいという点も無視できません。未上場企業経営者にとっては「事業のライフサイクルと資産運用を並行して考える」視点が必要ですが、金融機関の提案は必ずしもそこまで踏み込んでくれないのが現実です。
「経営=資産運用」と考えるとリスクが一気に増す
経営者が陥りやすい誤解のひとつが「自社の成長こそ最高の投資先である」という考え方です。もちろん、事業拡大のために利益を再投資することは重要ですが、それだけに依存するのは非常に危険です。
もし景気変動や規制強化、競合の台頭といった外部要因によって事業が停滞すれば、経営者の個人資産も一気に減少します。つまり、経営と資産運用を切り離さず「同じかごに卵を入れる」状態を続けると、リスクが二重に膨らむのです。
資産運用の本来の目的は「事業が不調でも生活や家族の将来を守るための安全網を築くこと」です。経営者がこの視点を持たず、経営と資産運用を一体として考え続けると、事業リスクが個人の資産リスクに直結してしまい、想定外のトラブルに耐えられなくなります。
資産運用の基本方針 二層構造で考える
未上場企業経営者にとって、資産運用の最大のテーマは「いかにして事業リスクと個人資産の安全を切り分けるか」です。事業は常に変動要因にさらされ、予期せぬトラブルによって資産価値が一気に揺らぐ可能性があります。そのため、資産を「事業資産」と「金融資産」に分けて管理する二層構造の発想が欠かせません。本章では、その考え方と実践のポイントを解説します。
事業資産(高リスク)と金融資産(安定リターン)の分離
経営者が持つ資産は大きく分けて二種類に分類できます。
- 事業資産
自社株や会社が保有する設備、不動産、運転資金など、企業活動に直接結びつく資産です。リターンが大きい反面、事業環境の変化により価値が変動しやすい「高リスク資産」です。 - 金融資産
株式、債券、不動産、投資信託など、事業とは切り離して保有できる資産です。特に国債や社債などはリスクが低く、安定的なリターンを得られる手段となります。
この二つを意識的に分離して運用することが重要です。経営者の多くは「事業が最大の投資先」と考え、事業資産への再投資を優先しますが、これだけに依存すると外部要因で資産全体が一気に毀損する恐れがあります。金融資産を安定的に保有しておけば、事業が不調に陥っても生活や家族の将来を守る「セーフティーネット」として機能します。
キャッシュフローを意識した余剰資金運用
経営者が資産運用を考える際に忘れてはならないのが「キャッシュフローの視点」です。事業の成長過程では、設備投資や運転資金などで手元資金が必要になる場面が多くあります。ところが、資産の大半を不動産や非流動性の高い投資に振り分けてしまうと、いざという時に資金を捻出できず、事業継続に支障が出かねません。
そのため、余剰資金を運用する場合には「いつでも引き出せる資金」「中期的に使える資金」「長期的に寝かせられる資金」の三層に分けて考えることが有効です。
- 短期資金:普通預金や短期国債など流動性を重視
- 中期資金:社債や投資信託など、数年単位で運用可能なもの
- 長期資金:不動産や退職金準備、相続を意識した資産
キャッシュフローを意識した資産設計を行うことで、事業資金の需要と個人資産運用のバランスを取りやすくなります。
長期的な事業承継・相続を見据えた設計
未上場企業経営者にとって、資産運用は単に「今を増やす」だけでなく「次世代にどう引き継ぐか」という観点も欠かせません。特に自社株は相続財産として評価されるため、株価が高くなればなるほど相続税負担が重くなります。資産の分散や法人を活用した運用を検討することは、相続対策としても有効です。
例えば、資産管理会社を設立して金融資産を保有させることで、事業承継の際に自社株と金融資産を分けて相続できます。これにより後継者の負担を軽減し、会社の安定経営を支えることが可能となります。
また、不動産やドル建て債券といった事業と相関性の低い資産を組み入れることで、相続後の資産価値を守りやすくなる点も見逃せません。資産運用を「事業承継・相続の一部」と位置づけることで、長期的な安定性を確保できます。
短期のリターンに偏らず、経営の安定性を優先すべき
資産運用を考える際、多くの経営者が「どの投資が一番儲かるか」という視点に引き寄せられがちです。しかし、経営者にとっての資産運用の役割は「短期的な利回りの追求」ではなく「事業の安定性を守ること」です。
高利回りをうたう商品は往々にして高いリスクを伴います。経営資産そのものが高リスクである以上、個人資産まで同じ方向に偏らせるのは避けるべきです。むしろ、金融資産は安定性を重視し、事業リスクと逆の性質を持つものを中心に組み合わせることで、全体としてのリスクをコントロールするのが賢明な戦略です。
未上場企業経営者に適した資産運用手法
資産運用の基本方針として「事業資産と金融資産の二層構造を分けて考える」ことの重要性を確認しました。では実際に、未上場企業経営者にとってどのような資産運用手法が有効なのでしょうか。本章では、比較的適性が高いとされる具体的な手段を紹介しつつ、留意すべきリスクについても整理します。
米ドル建債券・社債投資:安定利回り+通貨分散
経営者にとって第一に検討すべき選択肢のひとつが「米ドル建て債券・社債」への投資です。
日本の低金利環境では、円建て資産だけでは十分な利回りを得にくいのが現状です。米ドル建て債券は相対的に高い利回りを確保できるうえ、通貨を分散する効果があります。万一、円高局面で評価額が下がるリスクはありますが、長期的には「円資産一本槍の偏り」を避けるうえで有効な手段です。
また、社債であれば発行体の信用力に応じて利回りが変わり、分散投資を行うことで比較的安定した収益を確保できます。特に流動性の高い米国国債や格付けの高い米社債を中心に組み入れることで、安全性と収益性のバランスを取りやすくなります。
不動産投資:事業と相関が低く承継しやすい
不動産投資は、事業資産とは異なる性質を持ち、相関が低いことからリスク分散に有効です。特に日本国内の居住用不動産や収益不動産は、承継しやすい資産としても注目されています。
経営者の資産運用として不動産を取り入れる場合、次のようなメリットがあります。
- 長期的に安定した賃料収入を得られる
- 相続資産として評価しやすく、事業承継対策に組み込みやすい
- 事業不振時にも独立した収益源となる
一方で、不動産は「流動性が低い」という弱点を抱えています。急に資金が必要になってもすぐに売却できるとは限らず、価格も市況に左右されます。そのため、事業資金に充てる可能性がある資産を不動産に偏らせるのは危険です。「長期で持てる余剰資金の一部」を充てるのが妥当といえるでしょう。
投資信託・ETF:分散効果でリスク低減
投資信託やETFは、複数の株式や債券に自動的に分散投資できる仕組みを持っています。経営者にとっては、事業で大きなリスクを取っている分、資産運用では「分散」と「安定性」を重視することが望まれます。その点で、低コストのインデックス型ETFやバランス型投資信託は有効な選択肢です。
例えば、世界株式に広く分散するETFや、株式と債券をバランスよく組み合わせた投資信託を活用すれば、特定の市場や資産クラスへの依存を減らせます。長期的な成長を取り込みつつ、安定的なリターンを期待できるのが魅力です。
また、上場ETFであれば市場での流動性も高く、必要に応じて売却して資金化しやすいという実務的な利点もあります。
法人を活用した運用(資産管理会社設立など)
資産運用を個人だけで行うのではなく、法人を活用する方法も有効です。特に「資産管理会社」を設立し、自社株や不動産、金融資産を法人で保有させるケースは少なくありません。
資産管理会社を活用するメリットは以下の通りです。
- 法人税率の活用による税負担の軽減
- 自社株や不動産を法人に移管することで、事業承継の際に資産を整理しやすい
- 個人資産と法人資産を切り分けることで、経営リスクから一定程度保護できる
ただし、設立や運営にはコストがかかるため、税務・法務の専門家と相談しながら設計する必要があります。特に、相続対策や後継者への承継を見据えて長期的にメリットが得られるかどうかを見極めることが重要です。
過度なリスク追求は禁物
どの運用手法にも必ずリスクは存在します。特に経営者が注意すべきなのは以下の点です。
- 為替リスク(ドル建て商品)
米ドル建て債券や外貨資産は、円高局面で価値が目減りします。為替ヘッジの有無や保有比率を慎重に調整することが必要です。 - 流動性リスク(不動産)
不動産は換金に時間がかかるため、短期的に必要となる資金とは切り分けるべきです。 - 高リスク商品の過度な投資(FX・暗号資産など)
「短期間で大きく増やせる」という誘惑はありますが、経営者はすでに事業という大きなリスクを抱えています。資産運用でまで過度なリスクを取るのは本末転倒です。
成功と失敗の事例から学ぶ
資産運用の理論や基本方針を理解しても、「実際にどう行動すればよいか」という具体像がなければ、自分の状況に当てはめにくいものです。ここでは、未上場企業経営者が直面しやすい典型的な事例を紹介します。成功事例と失敗事例を比較することで、資産運用の実務に潜む落とし穴と、取り組み方のヒントを整理していきます。
成功事例:年商50億円オーナー、自社株偏重からドル債券・不動産で分散し安定収益を確保
ある地方の製造業を営むオーナー経営者(50代男性)は、長年にわたり自社株に資産の大半を集中させていました。会社の成長に伴い株式評価額は大きく膨らみ、資産規模は数十億円に達していましたが、資産のほとんどは「紙の上の評価額」にすぎず、実際に使える資金は限られていました。
加えて、業界再編の波や取引先の動向によって業績が不安定になった時期、自社株の評価額は大きく変動。将来の事業承継や相続を考えると、「このままではリスクが高すぎる」と感じるようになりました。
そこで彼は、専門家に相談しながら資産の一部を金融資産にシフト。具体的には、余剰資金を活用して米ドル建て債券を購入し、為替分散と安定利回りを確保しました。さらに、収益不動産を数件取得し、家賃収入を得る仕組みを構築。
この結果、自社の業績が一時的に落ち込んだ時期でも、債券利息や賃料収入が安定収益源となり、生活や事業継続に支障は出ませんでした。資産が分散されたことで心の余裕も生まれ、結果的に経営判断の質も向上。「資産運用を経営と切り分けることが、むしろ経営を守ることにつながる」と実感するようになったのです。
失敗事例:全資産を不動産投資に振り分け、流動性不足で事業資金に困窮
一方、別のオーナー経営者(40代男性)は、事業から得た余剰資金をすべて不動産に投資しました。知人からの勧めで複数の収益物件を購入し、当初は安定した家賃収入を得られていました。
しかし、景気後退と同時に入居率が低下。さらに修繕費や借入金の返済負担が重くのしかかり、キャッシュフローが悪化しました。その矢先、本業でも急な設備投資が必要となりましたが、手元資金が不足して対応できません。
不動産を売却しようとしましたが、タイミング悪く市況が冷え込んでおり、希望価格では売れず、資金化に時間もかかりました。その結果、事業資金を確保できず、経営自体が苦境に陥ってしまったのです。
このケースは「流動性リスク」を軽視した典型例といえます。不動産は長期的な資産形成には有効ですが、短期の資金需要に対応するには不向きです。資産全体を不動産に偏らせたことで、事業と個人の両面に悪影響が及んでしまったのです。
資産はバランスと流動性を意識することが不可欠
上記の成功と失敗の違いは、端的にいえば「バランス」と「流動性」を意識したかどうかに尽きます。
- 成功事例の経営者は、自社株偏重というリスクを認識し、債券や不動産といった異なる資産を組み合わせることでリスク分散を実現しました。流動性のある資産と安定収益を生む資産をバランスよく取り入れたことで、事業環境の変化にも対応できました。
- 失敗事例の経営者は、目先の安定収入に目を奪われ、不動産という一つの資産クラスに過度に依存しました。その結果、事業資金という「即時に必要なキャッシュニーズ」に応えられず、経営を圧迫する結果となりました。
経営者の資産運用は、一般の個人投資家以上に「安全弁」としての役割が大きくなります。すでに事業という高リスクの資産を抱えている以上、その他の資産は安定性と流動性を優先することが肝要です。
まとめ
未上場企業経営者にとって、資産運用の最大の課題は「事業リスクと個人資産のリスクが直結してしまうこと」です。自社株や事業資産に偏りすぎると、業績の変動がそのまま資産価値の毀損につながりかねません。だからこそ、事業資産と金融資産を切り分け、安定的な収益を確保できる仕組みを構築することが不可欠です。
具体的には、米ドル建て債券や不動産投資、投資信託・ETFを組み合わせて分散を図り、さらに資産管理会社を活用するなど、承継や相続も見据えた長期的な戦略が必要になります。一方で、それぞれの手法には為替リスクや流動性リスクといった注意点も存在するため、独力で最適な配分を判断するのは容易ではありません。
そのためには、販売目的に偏らない中立的な立場からアドバイスを行うIFAや独立系プライベートバンクなどの専門家に相談することが有効です。自社とご自身の資産状況を丁寧に整理し、事業リスクと個人資産のリスク分散を両立させる最適な戦略を設計することが、経営者にとっての安心と未来への備えとなるでしょう。
まずは自社とご自身の資産状況を整理し、最適な資産運用戦略を一緒に考えてみませんか?