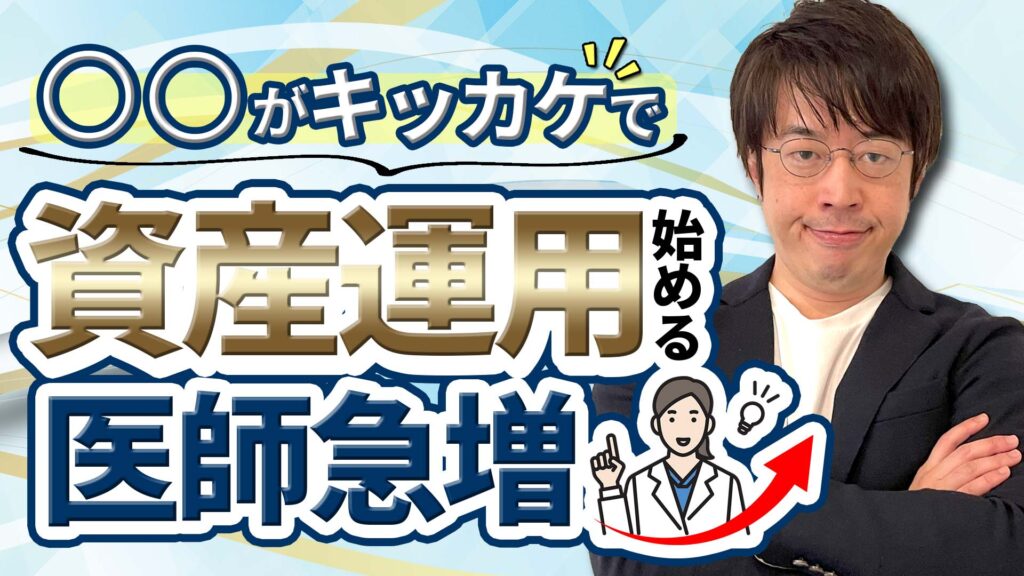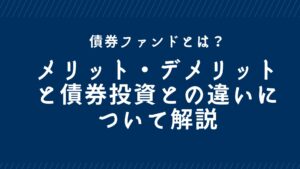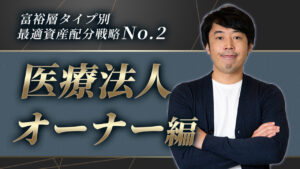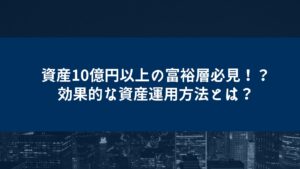皆さん、こんにちは。株式会社ウェルス・パートナー代表の世古口です。
はじめに
本日のテーマは、「医師が資産運用を始めるキッカケTOP5」です。当社にも多くの医師の先生からのご相談をいただいており、資産運用を始めようと思ったキッカケについて詳しくお伺いしています。今回は、医師の先生方がどのような理由・キッカケで資産運用を始めようと思われたのか、お話しできればと思います。
医師の先生が資産運用を始めるキッカケを5位から順番にご説明しましょう。
5位「YouTube」
5位は「YouTube」です。今お話ししているような資産運用系のYouTubeや、経済・投資に関するYouTubeを見て、「投資・資産運用をしよう!」と思われる医師の先生が増えています。簡単に資産運用の勉強がYouTube等を通してできるようなご時勢となり、私たちのように資産運用の話を気軽にできるようになったため、このように情報収集をしていくことによって、始めてみようと思われる方が結構増えたということで、5位はYouTubeになりました。
4位「海外旅行」
4位は「海外旅行」です。こちらは最近の話なのですが、かなりドル高円安になってきたことに加え、海外は物価が上がっています。医師の先生が家族旅行でハワイに行き、実際に1週間程度過ごしてみて、日本との物価・為替の違いを大きく感じるわけです。ハワイでは、為替がドル高円安で物価がかなり上がっているので、体感で日本の2倍程度の物価の差を感じるはずです。物価が高くなると感じるということは、その国の通貨が弱くなっていると感じることと同義です。そこで、「もっと外貨を持った方がいいのではないか」「資産運用を始めた方がいいのではないか」「インフレになったとしても、増やした方がいいのではないか」と考えるキッカケに海外旅行がなっているように感じます。コロナが明けて、海外に行きやすくなった今年(2023年)に資産運用の相談をいただくキッカケになったのは海外旅行が多いので4位に挙げました。
3位「日々のニュース」
3位はテレビやネットの記事で毎日上がってくる「日々のニュース」です。毎日少しずつ積み重ねて情報が入ってきますので、インフレで物価が上がった、賃金が上がらないなど、プラスとマイナスのニュースをどちらも得ることによって、サブリミナル効果ではありませんが、「自分も何かやらなければ!」と思ってしまうのでしょう。特に、2022年・2023年に関しては、日本も物価が上がってきたというニュースが多かったと思います。一方で、賃金はなかなか増えないということで、「今後は何か資産形成を考えなければならない」と考えるようになります。そのような時代の流れもあり、毎日ニュースを聞くことによって、どこかのタイミングで「資産運用を始めよう!」というキッカケになったという医師の先生も多かったのではないかと思います。
2位「親の相続」
2位は「親の相続」です。親からの相続があり、ご自身にまとまった資金が入ってくる、現預金で1億円~2億円が入ってきて、「急にお金が入ってきたのですが、どうしたらいいですか?」というキッカケ、ご相談です。これは、今までの3位~5位までとは少し違います。いきなりお金が入ってきて、「どうしたらよいか分からない」「そのまま円預金に置いておいてもよいが、そのままでよいのかも分からない」「資産運用した方がよいとは思うが、どのようにしたらよいのか分からない」「実際に資産運用が必要な状況になってから資産運用について考える」というシチュエーションで一番多いのは、親の相続ではないかと思います。親御様もお医者様である方のケースが多いので、相続が起こったときにまとまった資金が手元に入ってくる医師の先生に多いわけです。
1位「子供の成長」
1位は「子供の成長」です。医師の先生が資産運用を始めようと思ったキッカケとしては一番多いです。医師の先生のお子様の場合、大きくなるにつれて高度な教育を受けられることが多いため、将来医師になるため・留学するため等、教育費がかなりかかります。お子様一人が私立の高校・大学まで行って卒業~独立するまでの間の教育費は、医師の先生のお子様の場合、一人当たり5,000~6,000万円かかる可能性が高いです。お子様が3人、4人いるともの凄い金額になってしまいます。そのようなことを勘案すると、収入は他の職業の方より高いですが、税金や保険料も高いので、手元に残るお金が多いわけではありません。資産運用した資金をお子様が大学に入る費用や留学の費用に将来充てるために、資産運用を始めようと思われる医師の先生が非常に多く、キッカケとして1番多いと思いましたので、「子供の成長」を1位に挙げました。
TOP5のおさらい
ここで、「医師が資産運用を始めるキッカケTOP5」のおさらいをします。
5位は「YouTube」です。私がやっているようなYouTubeを見て、「資産運用を始めなければ!」と思い、相談する方が最近多くなっています。
4位は「海外旅行」です。ドル高円安なので海外に行って物価の高さを感じて、「将来、海外旅行に行けないのではないか?!」と思うことによって、「外貨を持たなければ!」「資産運用しなければ!」と思うわけです。
3位は「日々のニュース」です。毎日積み重ねて情報を浴びていると、医師の先生も「自分も何かしなければ!」と思うわけです。
2位は「親の相続」です。まとまった資金が手元に入ってきて、「何かしなければ!」と思い、資産運用を始める方が多いです。
1位は「子供の成長」です。お子様に教育費がたくさん必要になると思いますので、「そのために何かできないか」ということで資産運用にたどり着く方が多いと思います。
本日は「医師が資産運用を始めるキッカケTOP5」という内容でお届けさせて頂きました。

株式会社ウェルス・パートナー
代表取締役 世古口 俊介
2005年4月に日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイスのプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。
2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。超富裕層のコンサルティングを行い1人での最高預かり残高は400億円。書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者1万人超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」での情報発信を通じて日本人の資産形成に貢献。医師向けサイトm3.comのDoctors LIFESTYLEマネー部門の連載ランキング人気1位。
メディア掲載情報:「m3.com」「ZUU online」「MONEY zine」「マネー現代」でコラムを連載中