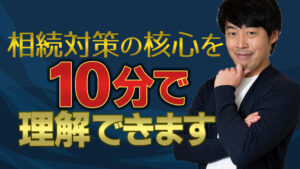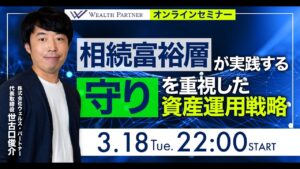受け継いだ財産は、単なるお金やモノではなく、故人の人生や想いが込められた大切な資産です。相続後、多くの人が「この財産をどのように守るべきなのか」不安や責任を感じるでしょう。資産は、ただ持っているだけでは守れません。
税金や相続トラブル、経済情勢の変化など、さまざまなリスクから資産を守る必要があります。次世代へつなぐには、計画的な管理と知識が不可欠です。今回の記事では、相続後に考えるべき「資産防衛」の基本と、将来に備えるための実践的なポイントを、分かりやすく解説していきます。
目次
パートナーの死後に直面する資産との向き合い方とは
「故人が全部やってくれていたので、私は何もわからない」このような言葉は、資産に関する相談でよく耳にします。初めて資産と向き合う方が、お金の管理や運用、金融商品などを意識せずに過ごしてきたというのは、よくある話です。
長年連れ添った配偶者は、築いた資産について内容を詳しく知らない状態で、すべてを受け継ぎます。何が、どこに、どのくらいあるのか、どのように扱えばいいのか戸惑いと不安は大きいです。
- 「いまさら聞いていいのか?」
- 「子どもたちに聞くのは気が引ける」
- 「銀行や専門家に相談するのは、少し勇気がいる」
多くの方が、上記のような悩みを抱えるケースがあります。誰にも相談できずに、時間だけが過ぎてしまうのです。
しかし、それは決して配偶者が悪いわけではありません。日本では、夫婦のどちらか一方が家計や資産を管理する場合があります。残された配偶者が「どのようにすればいいのか、わからない」と感じるのは自然なことです。
資産を増やす前に減らさない基本の投資戦略
多くの方が資産を受け継いだ際に「この資産をどのように活用すればよいのか」を考えなければなりません。将来の生活を支える必要もあります。そのような状況のなかで、金融機関からさまざまな提案が行われるでしょう。
- 「インフレ対策に成長株ファンドを」
- 「外貨建て保険で長期的に増やしましょう」
- 「最近の人気商品は◯◯です」
たとえば、上記のような話や提案が挙げられます。しかし、ここで一度立ち止まらなければなりません。配偶者に必要なのは「攻める運用」ではなく「守る運用」です。故人の資産は、無理なリスクを避けながら、少しずつ増やすことを目的にしていくことをおすすめします。
相続後にリスクの高い商品へ資金を移すと、その守りの資産が崩れるかもしれません。まずは、資産全体を把握してください。そして「減らさない運用」を基本設計にすることで、配偶者の生活に必要な資金が守れます。
3つのステップで整理する相続後の対策とは
相続は、単なる財産の引継ぎにとどまりません。遺された家族が故人の想いを胸に、未来へと進むための大切な過程です。しかし「何から始めるべきなのかわからない」「資産全体を把握できていない」などの悩みも、よく聞かれます。
そこで重要になるのが、相続の準備段階から、資産整理を「見える化」して、計画的に進めることです。ここでは、故人の資産を円滑に整理するための、3つのステップを解説します。
1. 持っている資産を洗い出す
まずは、預金通帳や証券、保険証券、不動産権利書、税務申告書類などをすべて集めましょう。「何がどこにあるのか」を整理する必要があります。
| 項目 | 内容例・チェックポイント |
| 銀行口座 | 普通預金・定期預金の有無、複数の口座に分散していないかを確認する |
| 証券口座 | 株式、投資信託、債券、外貨建て商品(海外債券や外貨建資産など)の有無を調べる |
| 保険 | 死亡保険、年金保険、医療保険を一覧化(契約内容、受取人、保障内容など)させる |
| 不動産 | 評価額(相続税評価額、時価)、収益性(賃貸収入の有無)、相続税評価額との違いを整理する |
| その他 | 金地金、未上場株式、貸付債権、貸付金などの有無と評価する |
上記の作業は、親族や知人と一緒に行うことで、スムーズに進みます。税理士や、信頼できるFPに依頼するのも有効です。
2. 収支と支出の計画を立てる
「今後の生活にどのくらいお金が必要なのか?」 この悩みを明確にすることで「使うべきお金」と「守るべきお金」に分けられます。
| 支出項目(例) | 計算内容 | 金額(万円) |
| 毎月の生活費 | 35万円 × 12ヶ月 × 20年 | 8,400 |
| 予備費(医療・介護・修繕など) | 固定額 | 2,000 |
| 旅行や贈与など | 固定額 | 2,000 |
| 合計 | ー | 1億2,400 |
上記の例から「現金で確保するべき金額」「安全な運用にまわせる金額」の線引きができます。
3. 家族と共有する
相続後の資産運用を始めるにあたって、子どもや信頼できる親族と現状を共有することが大切です。将来の二次相続に備えるためにも、早い段階で関係者の間で意識を共有しましょう。このような対策で、相続に関するトラブルが未然に防げます。
相続でよくある失敗から学ぶ!後悔しないための選択肢
相続は、配偶者にとって重要な出来事ですが、トラブルや後悔も起こりがちです。特に、知識不足や感情的な判断から「避けられたはずの失敗」が頻発します。ここでは、よくある相続後の失敗例を3つ紹介します。大切な資産と家族関係を守るために、ぜひ確認してみてください。
1. 説明を深く理解しない状態で高コスト商品を契約
「わからないから任せます」と銀行や証券会社に資産を移した結果、手数料が高くてパフォーマンスの悪い投資信託を買わされたケースです。
- 結果:3年間で数百万円の含み損になる。不信感と後悔のみを残す。
2. 相続税の納税資金確保のために急な売却
「納税期限までに現金が必要」と焦って、株式や不動産を安値で売却したケースです。
- 結果:数千万円単位で、本来得られたはずの資産を失う。
3. 相談相手がいないまま、10年間放置
不安や億劫さから資産に手をつけず、10年以上そのまま放置。銀行口座で資産が動かず眠っている。
- 結果:インフレによって、資産の実質価値が10%〜15%目減りする。
資産を守るための「3つの運用原則」
資産運用は「増やすこと」に目が行きがちです。しかし「守ること」が、安定した資産形成の基盤につながります。市場の変動やインフレ、予期せぬ支出などのリスクに備えて、資産を維持・成長させるには、戦略的な判断が不可欠です。ここでは、大切な資産を守るために知っておきたい「3つの運用原則」を解説します。
原則①:自身が理解できるものに投資する
- 債券やETF、個人向け国債など、構造がシンプルな商品を中心に選ぶ
- 「値動きが比較的安定しているもの」を優先する
原則②:資産の分散と流動性を重視する
- 特定の資産(例:不動産・株式)に偏らない
- すぐに引き出せる現金資産(生活費の3年分が目安)を確保する
原則③:定期的な見直しを習慣にする
- 年に1度、資産配分をチェックする
- 世の中の金利・為替の変動を調べる
- 大きな決断は「相談相手」と一緒に行う
| 原則 | ポイント | 具体例・注意点 |
| 原則①:リスクを取りすぎない | ・自分が理解できる範囲で投資
・構造がシンプルな商品を選択 ・値動きが安定するものを優先 |
・個人向け国債
・ETF(代表的な指標連動型) ・債券(国債・社債) ※難しい商品や仕組みは避ける |
| 原則②:分散と流動性 | ・資産を幅広く分散
・特定資産(株式・不動産など)へ偏らない ・生活費3年分の現金確保 |
・株式や債券、現金、不動産、REIT、外国資産の組み合わせを考える
・現金はすぐ引き出せるようにする |
| 原則③:定期的な見直し | ・年1回は配分比率チェック
・金利・為替動向も確認 ・大きな変更は相談相手と検討 |
・配分が崩れていないか確認する
・家族やFP(専門家)などに相談する |
相談すべき相手をどのように見極めるのか?
人生において、相続や資産運用は大きなテーマです。だからこそ、誰に相談するのかは、非常に重要です。「銀行は商品を勧められそうで不安」「家族には相談しにくい」と感じる方もいるかもしれません。
そのような時にこそ、親身に寄り添ってくれる中立的なパートナーの存在が不可欠です。ここでは、代表的な中立的パートナーの特徴やメリットなどを、簡単に紹介します。
独立系IFA(金融商品仲介業者)
- 特徴:証券会社に属さない独立した立場で、顧客本位の提案を行う
- メリット:利益相反が少なく、透明性のある説明が多い
- 注意点:個人差が大きいため、実績や信頼性の確認が必要になる
税理士や相続分野に詳しい専門家
- 特徴:相続税や名義変更、遺産分割などに精通している
- メリット:チーム体制での支援に安心感がある
- 注意点:初回でも相談しやすい環境なのか、依頼しないと分からない
将来への備えとして「守る運用」が配偶者の支えになる
将来への不安が高まるなかで「守る運用」の重要性が増しています。経済環境の変動や予測不能な事態に備えて、資産を増やすだけでなく、守りの視点が欠かせません。個人の価値観を尊重しつつ、安定した資産運用で人生を支える必要があります。
これからの資産運用は、お金の管理を超えて、長生きリスクへの備え、家族への安心、自分らしい生き方の選択肢を増やします。すべてにおいて「お金の安心」が重要です。資産を受け継いだ配偶者には「未来を設計する権利と責任」があります。自身と大切な家族の未来を見据えて、安心できる資産運用を行いましょう。
「知らないまま」にしない姿勢が資産を守る第一歩
相続をきっかけに、これからの人生のハンドルを握ることになった配偶者の方は多いです。しかし、すべてを一人で抱え込む必要はありません。「誰かに任せきり」にするのではなく、まずは、ご自身が理解できる範囲で資産と向き合いましょう。その小さな一歩が、これからの人生を守り、支える大きな力になります。
無料個別相談相談のご案内:資産の整理・守り方に不安がある方へ
私たちウェルス・パートナーでは、相続後の資産運用に関する初回無料相談を承っております。
- 資産の見える化
- 必要なお金と残すお金の線引き
- 債券や分散型ポートフォリオの提案
- 誰にも相談できなかった悩みの整理「誰に相談すればいいのかわからない」そのような方こそ、お気軽にご連絡ください。

株式会社ウェルス・パートナー
ポートフォリオマネージャー
早稲田大学商学部卒業後、株式会社群馬銀行へ入社。富裕層と会社経営者を中心とした資産運用のコンサルティング業務に従事。銀行での提案には限界があると感じ、もっと付加価値の高い提案をしたいと思い株式会社ウェルスパートナーに入社。富裕層、会社経営者の資産配分最適化や具体的な金融資産の投資実行サポートを行う。