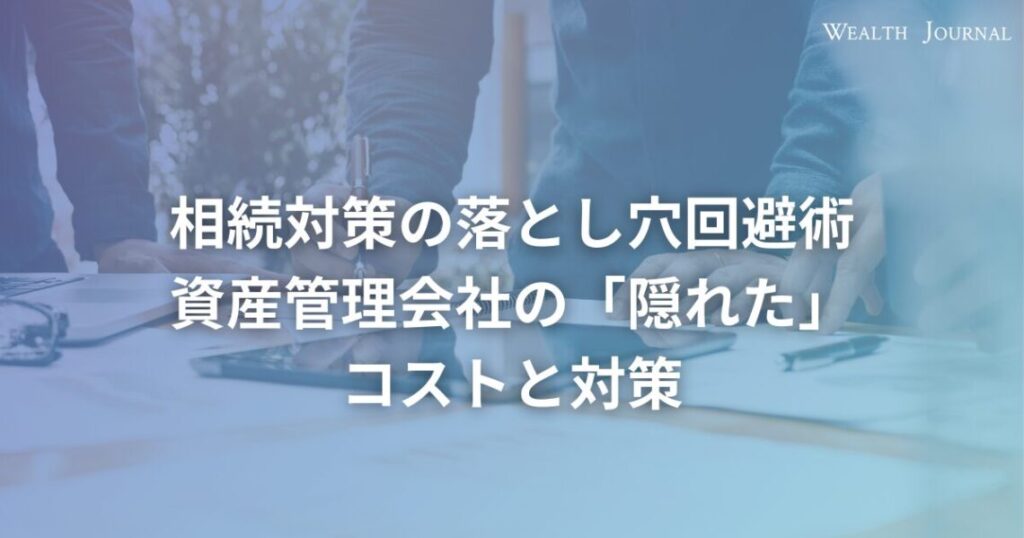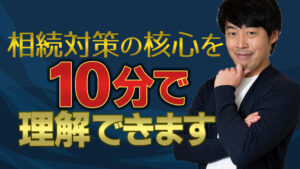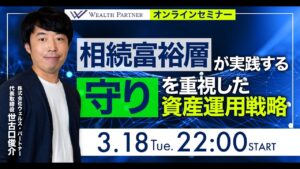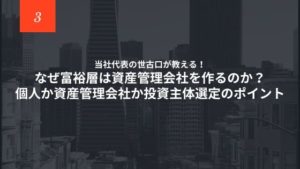はじめに
富裕層の相続対策として、資産管理会社の活用は、株式評価の引き下げ、不動産の所得分散、贈与の最適化といった多岐にわたる節税メリットをもたらす強力かつ魅力的な選択肢として広く認識されています。弊社の「WEALTH JOURNAL」でも、メディア立ち上げ当初より、富裕層にとっての資産管理会社の重要性を何度となくお話ししてきました。しかし、その華やかな節税効果・相続対策の陰に隠れ、あまり語られない「隠れたコスト」が存在することをご存知でしょうか。
実は、目先の節税メリットにばかり注目しすぎると、想定外の制度設計・運用コスト、潜在的な税務リスク、そして将来の事業承継計画への予期せぬしわ寄せといった、多方面にわたる「見えない落とし穴」に陥るリスクを抱えることになります。
本記事では、資産管理会社を活用した相続対策を検討する際に、多くの人が見落としがちなこれらの「隠れたコスト」の具体的な内容を徹底的に掘り下げます。そして、それらを未然に防ぎ、真に効果的で持続可能な相続対策を実現するための実践的なアプローチを詳しく解説します。
資産管理会社の基本
富裕層の相続・節税対策として、このメディアでも幾度となく取り上げてきている資産管理会社ですが、ここでは、簡単に資産管理会社の基本をおさらいしておきましょう。
資産管理会社とは
資産管理会社とは、個人や一族が所有する資産を法人として一元的に管理・運用するための会社です。法人形態を取ることで、個人名義では行いにくい取引の柔軟化、税務面での最適化、資産の分離・保全などを実現することができます。
設立するには
設立の形式としては、株式会社や合同会社などが一般的です。特に非上場の中小企業オーナーや医師、士業など、一定以上の資産規模を有する方々の間で、資産承継、相続対策を目的として、近年その利用が広がっています。
設立には、公証人役場での定款認証、法務局での法人登記などの手続きが必要となります。しかし、その手続きは比較的簡便で、短期間かつ低コストで設立が可能です。ただし、設立後は法人としての決算・税務申告義務が発生し、帳簿作成や経理処理といった実務対応も必要になります。
保有資産
資産管理会社が扱う資産の内容は多岐にわたります。賃貸不動産、有価証券、自社株、不動産管理業務や保険契約、さらには貸付金・預貯金といった流動資産まで、一族の資産全体を法人の枠組みで保持することができます。
資産管理会社は、事業会社のように積極的な売上や利益を追求するわけではなく、あくまで「資産の箱」としての役割を担う存在です。そのため、比較的シンプルな経営体制で済む一方、オーナーの意向や資産の性質に応じてカスタマイズ性が高いという特徴もあります。とはいえ、その柔軟性ゆえに制度設計を誤ると、かえって不利益を被ることもあるため、設計段階の専門家の関与が極めて重要になります。
富裕層が資産管理会社を選ぶ理由
相続対策や資産保全の手段として、資産管理会社を活用する富裕層は年々増加しています。では、なぜ富裕層の方は資産管理会社を選ぶのでしょうか。単なる節税目的にとどまらず、将来を見据えた「守り」と「引き継ぎ」の戦略として、そのメリットに注目が集まっています。
理由1:節税効果が最大の動機
資産管理会社を設立する最大の理由のひとつが、税務上の優位性です。個人の所得に対する最高税率(55%)に比べ、法人の実効税率は約23%。この差を活かし、法人に利益を蓄積したり、家族に役員報酬を支給したりすることで、所得の分散や税負担の軽減を実現することが可能です。
また、法人での資産保有により、相続税評価を引き下げられるケースもあります。例えば賃貸不動産を法人が保有している場合、評価対象は法人株式となり、その評価額に一定の調整が入るため、結果的に相続税額が圧縮される可能性があります。
理由2:相続の“争族化”を防ぐ
資産管理会社は、相続の局面でも大きな効力を発揮します。不動産や株式などの現物資産を個人で持っていると、相続時の分割が困難となり、兄弟姉妹間・親族間等の争いを引き起こす原因となりがちです。
しかし法人化された資産であれば、「株式」という形で均等に分けることができ、実物資産を無理に分割する必要がなくなります。これにより、承継時の「トラブル=争族」を大幅に回避することができます。
理由3:個人と法人を分けることでリスクコントロール
資産管理会社は、資産とオーナー個人のリスクを分離する役割も果たします。例えば、オーナー個人が何らかの債務や訴訟リスクを負った場合でも、法人が保有する資産は直接的な影響を受けにくくなります。これは、不動産収入や配当収入といった安定資産の保全においても大きな意味を持ちます。
また、法人であれば複数の家族を「役員」として従事させることができ、家族ぐるみで資産管理・承継体制を構築しやすくなる点も魅力です。
理由4:節税だけではない、“統合管理”としての意義
資産管理会社の真の価値は、単なる節税だけではありません。資産の統合的な管理、次世代へのスムーズな承継、そして税務リスクを管理しながら資産を守り続ける“プラットフォーム”として、富裕層にとっては極めて戦略的な意味合いを持っています。
ただし、その効果はあくまで設計と運用の質によって左右されます。目先の節税だけでなく、10年後・20年後の資産状況を見据えた上での活用が求められるのです。そのためには、私たちウェルス・パートナーのように資産管理会社設立にも詳しい専門家への相談が必須となります。
資産管理会社に潜む「隠れたコスト」とは何か
それでは、本題に入りましょう。資産管理会社は、多くのメリットをもたらす一方で、設立時には見えにくい「隠れたコスト」が存在します。こうしたコストを事前に把握しておくことは、想定外の負担や将来のリスクを避けるために極めて重要です。ここでは、特に注意すべき4つのコストを解説します。
①毎年発生する維持・運営コスト
資産管理会社は設立して終わりではなく、継続的な運営にコストがかかります。具体的には、次のような費用が毎年発生します。
「税理士による決算・申告報酬」「顧問料や登記変更の手数料」
「社会保険料(役員報酬がある場合)」「会計ソフトや書類管理の実費」など
資産の規模や収益に比して維持コストが高くつく場合、節税どころか逆にキャッシュアウトの方が大きくなることもあるため注意が必要です。
②解散・清算時の課税リスク
資産管理会社は長期にわたって維持することを前提としていますが、将来の事業整理や家族構成の変化によって「使わなくなる」場面もあります。ところが、解散・清算を行う際には、思わぬ税負担が生じる可能性があります。
例えば、会社に残る資産を株主へ分配する場合、「みなし配当」課税がかかり、法人・個人の双方で課税されることになります。また、不動産を法人から個人へ移す場合には、不動産取得税や登録免許税が発生することもあります。
長期的な「出口戦略」を描かないままスタートすると、将来に大きなコストが跳ね返ってくるリスクがあるため、覚えておくとよいでしょう。
③相続時の「争族」がもたらす見えないコスト
資産管理会社の株式は、オーナーが亡くなれば「相続財産」として承継対象となります。しかし、誰がどれだけ株式を相続するかが明確に決まっていない場合、家族間の意見の対立を招くことがあります。これは、金銭に換算しにくい“見えないコスト”を生む原因となります。
例えば、長男が後継者として経営を担う想定だったにもかかわらず、他の兄弟姉妹にも株式が分散された場合、意思決定に支障が生じることがあります。会社の資産を動かすにも、株主の同意が必要となり、場合によっては不動産の売却や新規投資が停滞する原因になります。また、感情的な対立が長期化すれば、弁護士の介入や訴訟に発展するケースもあり、その過程でかかる法務コストや精神的ストレスは、決して小さな負担ではありません。
さらに、経営に関与しない相続人が株主として配当を要求するようになると、会社からの資金流出が続き、法人の健全な運営が損なわれるリスクもあります。このような「争族」を未然に防ぐには、遺言書や株主間契約などによって承継の方向性を明確にしておくことが不可欠です。
④税務リスクと否認の可能性
資産管理会社を使った節税策は、あくまで“実体に即して”行うことが大前提です。形式的に制度をなぞっただけのスキームは、税務署から否認されるリスクを伴います。例えば、「実態のない高額な役員報酬」「同族間での不自然な不動産取引」「使用実態のない保険契約」などは、「租税回避目的」とみなされる可能性があります。
税務調査が入った場合、多額の追徴課税やペナルティが発生することもあり、節税のつもりが高コストに転じるおそれもあります。こうしたリスクを最小限に抑えるには、税理士や弁護士などの専門家による継続的なアドバイスと記録の整備が不可欠です。
資産管理会社には多くのメリットがある一方で、「隠れたコスト」は目に見えにくく、後になって問題化することが少なくありません。設立の段階で“将来の使い方”や“終わらせ方”まで含めてプランを立てることで、これらのリスクを未然に防ぐことが可能になります。
次章では、このようなコストやリスクを抑えながら資産管理会社を有効に活用するための実践的な対策をご紹介していきます。
「隠れた」コストとリスクを最小限にするための実践的対策
資産管理会社は、うまく活用すれば相続や資産承継の強力なツールとなります。しかし、設計や運用を誤れば、節税効果が失われるばかりか、思わぬトラブルやコスト増につながりかねません。ここでは、そのようなリスクを最小限に抑えるための実践的な対策を、5つの視点から整理して解説します。
①活用目的を明確にする
資産管理会社を設立する際は、「何のために使うのか」「いつまで使うのか」を明確にしておくことが何より大切です。節税目的だけにとらわれず、資産の保全、分割のしやすさ、家族間の合意形成、納税資金の確保といった複数の観点から、設計目的をはっきりさせましょう。
また、「解散する可能性があるか」「将来誰が引き継ぐのか」といった“出口戦略”も同時に描いておくべきです。資産管理会社の活用には終わりがあります。将来的な清算や持株の処理まで想定しておくことで、不要な税務コストや相続トラブルを避けることができます。
②株式の承継設計を早い段階で検討する
資産管理会社の最大の落とし穴は「株式の相続」です。せっかく資産を法人に集約しても、その株式を巡って家族が争えば意味がありません。特に注意すべきなのは以下の点です。
- 株主の分散による経営の分裂
- 相続人の間での評価額を巡る不公平感
- 家族以外の第三者への株式流出
これらを防ぐには、生前からの株式移転計画、遺言書の作成、株主間契約や持株会制度の導入などが有効です。実務上は、贈与税や相続税とのバランスも考慮しながら、段階的な承継スキームを構築する必要があります。
③運営体制と記録整備を徹底する
資産管理会社の節税効果を担保するには、「実態」が伴っていなければなりません。例えば、役員報酬を家族に支払う場合は、業務内容や労働の実態がなければ、税務上否認される可能性があります。また、以下のような基本的な法人運営を怠ると、思わぬ税務トラブルを招くことがあります。
- 株主総会や取締役会の議事録を作成していない
- 不動産の賃貸契約や売買契約が適正でない
- 取引先との契約書類が不備のまま放置されている
こうした形式面の整備も、資産管理会社の信用性と安全性を保つ上で非常に重要です。税務調査では、このような“見えないガバナンス”の有無が重視される傾向にあります。
④専門家と定期的にレビューを行う
設立当初は万全の設計であっても、数年後には税制や家族構成、資産内容が変化しているかもしれません。ですから、少なくとも年1回~数年に1回は、税理士やFA、私たちのようなIFAなどと資産管理会社の現状をレビューする機会を持つことをおすすめします。以下のような点は、見直し対象として重要です。
- 保有資産の構成や収益性の変化
- 株主構成・後継者候補の状況
- 生命保険や借入金の必要性
- 税務リスクや制度変更への対応
見直しとともに「次の10年の使い方」を見据えることで、資産管理会社は本来の機能をより強く発揮します。
⑤家族内での合意形成を怠らない
最後に忘れてはならないのが、「家族全体での理解と合意形成」です。資産管理会社の株式は、一族の富の象徴ともなりうる存在です。その運営や承継方法について、関係者の理解や納得感が得られていなければ、どんなに緻密な設計も崩れてしまいます。設立前や重要な意思決定のタイミングでは、家族会議や信頼できるアドバイザーを交えた説明機会を設けることが大切です。
まとめ
富裕層の相続対策において、資産管理会社は非常に有効なツールです。しかしその運用は、“導入したら終わり”ではなく、常に見直しと調整を要する「生きた制度設計」が求められます。
目に見えないコストや将来のリスクに目を向け、定期的な検証を行うことで、本当に家族を守る資産運用へと昇華させることができます。節税にとらわれすぎず、「守る」相続から「引き継ぐ」相続へ、富裕層にふさわしい持続可能な資産管理を目指していきましょう。
私たちウェルス・パートナーでは、富裕層の方の資産運用はもちろんのこと、資産管理会社設立のお手伝いも承っております。相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

株式会社ウェルス・パートナー
代表取締役 世古口 俊介
2005年4月に日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイスのプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。
2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。超富裕層のコンサルティングを行い1人での最高預かり残高は400億円。書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者1万人超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」での情報発信を通じて日本人の資産形成に貢献。医師向けサイトm3.comのDoctors LIFESTYLEマネー部門の連載ランキング人気1位。
メディア掲載情報:「m3.com」「ZUU online」「MONEY zine」「マネー現代」でコラムを連載中