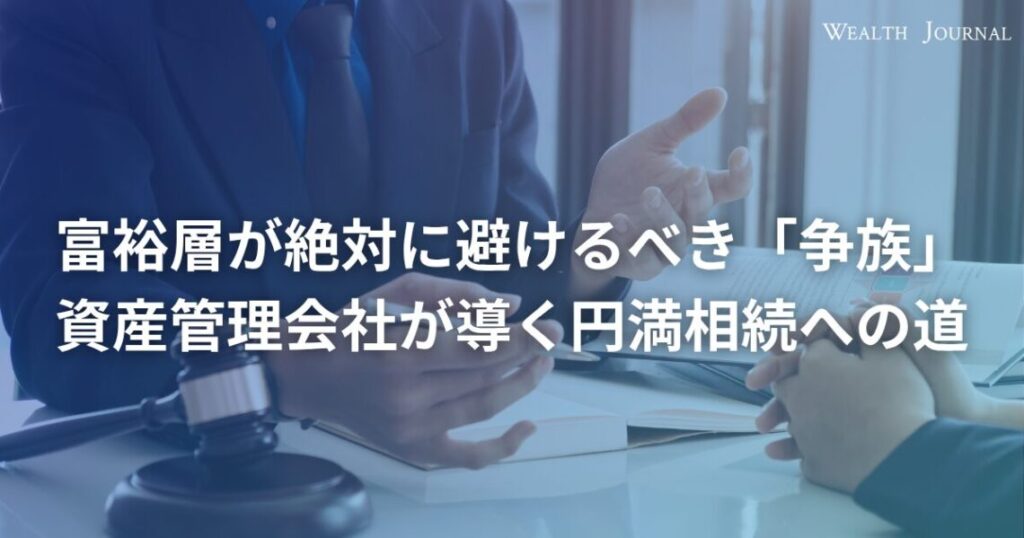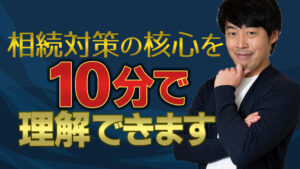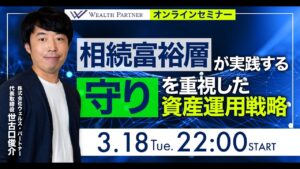目次
はじめに
資産があることは豊かさの象徴です。しかし、その豊かさが時に家族を分断し、「争族」という名の悲劇を生むことがあります。特に資産1億円を超える富裕層の方、さらに5億円〜10億円を超える資産をお持ちの富裕層の方であればなおのこと、不動産や株式、未公開株、自社株など多様な資産を抱えているがゆえに、単なる「分け方」では済まされない複雑な相続問題が発生します。
「兄は会社を継いだのに、私は何も受け取っていない」
「欲しい財産を分けてもらえなかった」
「生前贈与の実態が不透明で、公平性が感じられない」
こうした感情的な亀裂が、法定相続の枠を超えて争いを呼び起こすのです。
このような事態を回避するために、近年注目されているのが「資産管理会社」という選択肢です。単なる節税ツールにとどまらず、「争族対策」の中核としてその存在感を高めています。今回は、富裕層ほど絶対に避けなければならない「争族」がなぜ起きやすいのか、その回避策とともに、このテーマを深掘りしてみたいと思います。
1. 資産があるからこそ揉める実情
相続は、残された家族にとって故人を偲び、絆を深める機会であるはずです。しかし、実際には「争族」という言葉があるように、遺産を巡るトラブルは後を絶ちません。資産の多い少ないに関わらず、特に、「公平であるべき」という思いと「納得できない」という感情のズレが、争いの火種となることが少なくありません。
令和4年度の司法統計によると、家庭裁判所へ持ち込まれた遺産分割事件数は16,687件でした。高齢化等の影響により、近年は高止まり傾向にあります。案件の約3/4が、実は5,000万円以下という事実があるものの、富裕層の場合には、争いが表面化しにくいだけで、水面下では複雑な感情が渦巻いていることが少なくありません。
例えば、自社株を後継者に集中して渡す際、他の相続人に何をどのように分ければ「争族」を避けられるでしょうか。資産の評価額だけでなく、「実質的な影響力」や「相続税の負担」などが複雑に絡み合い、調整は一筋縄ではいきません。さらに、再婚家庭の異母兄弟など、家族構成が多様化している現代では、法定相続の枠に頼るだけでは感情的な納得を得られないケースも増えています。
相続トラブルが起こりやすい代表的なケース
相続トラブルは、故人の資産構成や家族関係の複雑さが主な原因となり、以下のようなケースで顕在化しやすい傾向にあります。
①自社株を含む相続
オーナー経営者の場合、会社を引き継ぐ子どもに自社株を集中させたいと考える一方で、他の相続人からは「自分たちも同等の価値の財産を受け取りたい」という要望が出ることがあります。特に、自社株の評価が難しく、現金や不動産での公平な分配が困難な場合、不満が募りトラブルに発展しやすくなります。
②不動産が多く流動性が低い場合
富裕層の資産は、収益不動産など換金しにくい不動産に偏っているケースが多くみられます。不動産は分割が難しいため、「誰がどの不動産を相続するのか」「売却して現金化するのか、それとも保有し続けるのか」といった点で意見が対立し、遺産分割協議が長期化することがあります。
③家族関係が複雑な場合
再婚や内縁関係、認知された子どもがいる場合など、家族構成が複雑な家庭では、相続人の範囲が広がり、関係者間の感情的なしこりが表面化しやすい傾向にあります。特に、長年同居していた配偶者と、交流のなかった異母(異父)兄弟との間で財産分与を巡る意見の対立が生じ、法廷闘争に発展するケースも少なくありません。
④生前贈与に偏りがあった場合
特定の相続人に対して多額の生前贈与が行われていたにもかかわらず、他の相続人がその事実を知らなかった場合、「不公平である」という感情が爆発し、トラブルに発展しやすくなります。遺留分減殺請求(現在は遺留分侵害額請求※)に発展することもあり、兄弟姉妹の関係に深い溝を残す原因となることがあります。
※遺留分侵害額請求とは…本来受け取れるはずの遺留分(法律で定められた最低限相続できる財産の割合)が遺言や贈与によって侵害され、受け取れなかった相続人が、その侵害された分の金銭を請求できる制度
⑤相続人同士の関係が悪い場合
相続人同士が普段から険悪な関係であったり、連絡をほとんど取っていなかったりする場合、遺産分割協議がスムーズに進まないことがあります。感情的な対立が先行し、合意形成が困難となり、遺産分割が何年も停滞するケースも少なくありません。
これらの代表的なトラブルパターンは、「資産があるからこそ起きる」ということもありますが、「資産の構成が複雑」「関係者が多様」「家族間の対話不足」といった点に起因しています。それゆえ、相続が発生する前から、しっかりと資産を整理し、家族間で話し合いの機会を設けるなど、事前の準備と仕組み作りが何よりも重要なのです。
2. 資産管理会社とは何か
「資産管理会社」とは、個人または法人が所有している不動産・株式・有価証券などの資産を法人に移管し、その法人を通じて一元的に管理・運用する仕組みです。もともとは節税や投資効率の向上を目的として富裕層に活用されてきましたが、近年では「相続対策の中核」として改めて注目を集めています。
新たに相続・資産保全を目的とした「資産管理会社」を設立する場合、出資者=オーナー家族となることが一般的で、家族単位で資産を管理するための器として機能します。この法人では通常の会社としての業務は行わないため、収益は不動産賃料・配当・運用益のみとなるのが特徴です。
資産管理会社を活用するメリット
資産管理会社を活用することで、次のようなメリットが得られます。
- 資産の可視化と一元管理
資産が多岐にわたる場合、個人所有のままでは所在や評価が不明確になりがちです。法人に集約することで、財務諸表を通じて第三者(専門家や家族)とも共有しやすくなり、相続時の混乱や不信感を防ぐことができます。 - 所得分散と税率コントロール
資産から得られる収益(賃料・配当・譲渡益など)を法人に帰属させることで、所得の分散が可能になります。個人に比べて法人税率は相対的に低く、内部留保にはその時点では個人の所得税がかからないため、タイミングをずらして事業投資に充てたり個人に支払ったりするなど、長期的な節税効果も期待できます。 - 株式を通じた「資産承継」のコントロール
資産を会社に移し、その会社の株式を相続させることで、「経営権の集中」「議決権の調整」が可能になります。例えば、長男に議決権の多い株式を、他の兄弟には配当優先の株式を持たせることで、相続後の経営の混乱を避けつつ公平感を持たせる設計ができます。 - 生前贈与の柔軟な設計
資産管理会社の株式は、評価額をコントロールしやすいため、生前贈与に適しています。特に「発行時に評価が低く、将来的に成長が見込まれる株式」を用いた贈与は、低い評価額の段階で贈与を行うため贈与税は少額で済み、相続税対策としてはかなり有効で、富裕層の王道の対策といえるでしょう。
一方で、留意点もあります。例えば、不動産を法人に移す際の譲渡税や登録免許税、継続的な法人維持コスト(税務申告・登記・会計等)は無視できません。設立後の実務管理等が複雑になるため、専門家との連携が必要になります。
つまり、資産管理会社は「作れば終わり」ではなく、「どう活かすか」が極めて重要なのです。相続対策として導入する際は、単なる節税目的にとどまらず、「家族にどう資産を託すのか」「経営権を誰に委ねるのか」という“想い”まで丁寧に落とし込んでいく必要があります。資産の管理と承継を法人という器に集約し「見える化」することで、家族の将来にわたる安心と信頼を築くこと、それこそが資産管理会社が導く円満相続への第一歩といえるでしょう。
3. 資産管理会社を活用することで防げる争族リスク
資産管理会社は、単に資産を法人に集約するための仕組みではありません。その本質は、「争いを未然に防ぐ設計図」を家族に遺すことにあります。ここでは、資産管理会社を活用することで具体的にどのような争族リスクを抑えることができるのか、その代表的なポイントをご紹介します。
財産の可視化と共有
資産管理会社を通じて不動産や証券、収益事業などを一元的に保有することで、家族間での資産状況の可視化が進みます。どこに何があるか、誰がどのように関与しているのかが明確になることで、不要な疑念や不信を防ぐことができます。
生前贈与・信託との併用で早めの意思表示
資産管理会社の株式を段階的に生前贈与することで、将来の相続争いを未然に防ぐことが可能です。また、少し高度になりますが、家族信託と併用することで、「資産の使い道」を指定できたり、財産凍結の回避が可能にできたりします。例えば「母親の介護費用はこの収益で補填する」というように、目的別の資産設計も可能となります。
経営権の集中と議決権のコントロール
株式を通じて経営の意思決定権を集約させることができるため、事業承継や不動産管理の方針にブレが生じにくくなります。例えば、株式の一部を相続人に渡す際、議決権の割合を調整することで、後継者の権限を明確に保持することができます。また、子どもに株式を相続させる際は、議決権の大部分を現経営者が保持しておくことで、すぐに経営の主導権を握ることを防ぎ、徐々に引き継ぐことができるため、スムーズで安定した経営を行うことが可能です。
4. 資産管理会社による円満相続を実現するためのステップ
資産管理会社は、あくまで「円満相続のための器」にすぎません。真に効果を発揮するためには、適切なプロセスを踏んで設計・運用し、家族との対話や意向の反映を図ることが欠かせません。以下に、資産管理会社を活用して円満相続を実現するための実践的なステップをご紹介します。
ステップ1:資産の棚卸しと法人化の検討
まずは、オーナーが保有するすべての資産を洗い出し、資産の種類・評価額・収益性・名義・所在などを整理します。この「棚卸し」が、後の相続対策のすべての基盤となります。そのうえで、どの資産を資産管理会社に移管するか、法人化に伴うコストや税務影響などを専門家とともにシミュレーションすることが重要です。特に不動産や有価証券などは、法人所有にすることで一元管理しやすくなると同時に、相続時の分割トラブルを回避しやすくなります。
ステップ2:株式構成と議決権設計による承継シナリオの構築
資産を管理会社に移した後は、誰に・どのような比率で株式を持たせるかが、将来の相続の形を左右します。例えば、経営権を握る長男には議決権の多い株式を集中させ、他の子には配当優先株式を持たせるなど、ご家庭ごとの事情に合わせた設計が可能です。この「見えない分割設計」が、将来の争いを未然に防ぐ大きな役割を果たすのです。
ステップ3:生前贈与・信託との組み合わせによる早期対策
資産管理会社を活用すれば、株式の贈与を通じた資産移転が可能です。特に評価額の低いうちに後継者へ段階的に贈与しておくことで、相続時の税負担を大きく軽減できます。また、家族信託と組み合わせれば、例えば「会社から得た配当を妻の生活費や介護費に充てる」といった、目的別の財産管理も実現可能です。早期にこうした設計を行っておくことが、家族間の“感情の溝”を防ぐ第一歩となります。
ステップ4:家族との対話と意向の共有
どれだけ精緻に設計しても、本人の想いや考えが伝わっていなければ、かえって誤解を生むこともあります。大切なのは、設計プロセスにおいて家族の意向を丁寧にヒアリングし、またオーナー自身の価値観や思いを伝えることではないでしょうか。そのために、家族会議の場を設けたり、信頼できる第三者を交えた対話の機会を持ったりすることは、相続の“納得感”を高めるうえで非常に有効です。
ステップ5:専門家とのチーム体制を構築する
資産管理会社の設立・運営・相続設計には、税務・法務・財務の専門的知識が不可欠です。顧問税理士だけに任せるのではなく、弁護士や専門家とチーム体制を構築することで、抜け漏れのない相続対策が実現します。特に資産規模が大きくなる富裕層の方ほど、チームで取り組むことの重要性は増していくでしょう。
まとめ
争族を避ける本質的な方法は、「財産をどう分けるか」ではなく、「オーナーの意思をどう伝えるか」に尽きます。資産管理会社は、その意思を形にし、仕組みとして遺していくための有力なツールとなるでしょう。資産管理会社という仕組みを「正しく使いこなす」ことで、財産の承継は単なる分配ではなく、“家族の未来への設計”となり得るのです。富裕層の方は、
いま一度ご自身の相続対策を見直してみてはいかがでしょうか。
私たちウェルス・パートナーでは、富裕層の方の資産運用に限らず、資産管理会社設立のお手伝いもさせていただいております。相談は無料となっておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。

株式会社ウェルス・パートナー
ポートフォリオマネージャー
早稲田大学国際教養学部卒業後、大和証券株式会社へ入社。富裕層と会社経営者を中心とした資産運用のコンサルティング業務に従事。顧客の資産全体の最適化や会社経営者への相続対策まで支援をしたいという思いがあり、株式会社ウェルスパートナーに入社。