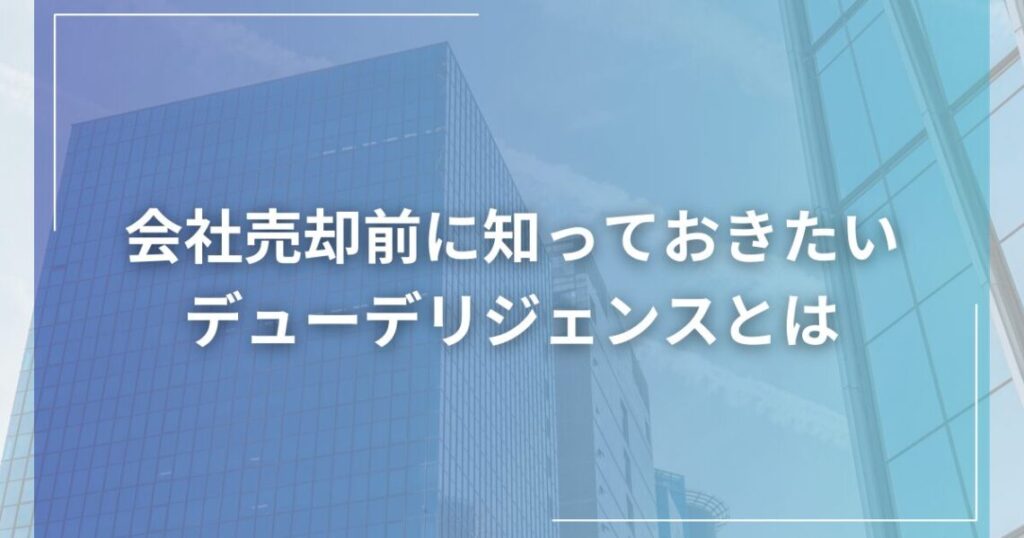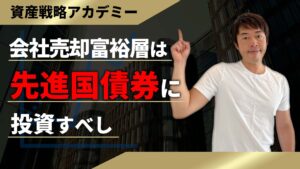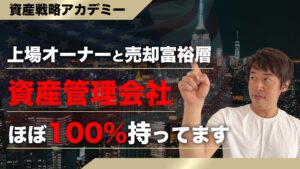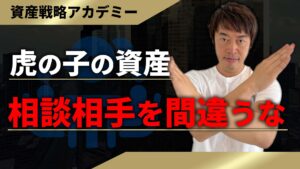はじめに
会社売却は、経営者にとって人生の節目ともいえる大きな決断です。特に富裕層の会社オーナーにとっては、長年築き上げた事業という「経営資産」を「金融資産」に変え、その後の資産運用や相続対策にも大きな影響を与える重要な転換点となります。
会社売却の場面で、買い手企業が必ず実施する「デューデリジェンス(Due Diligence)」と呼ばれる手続きがあります。これは、売り手企業の事業内容や財務、法務、税務などを、多面的に調査・検証するプロセスで、買収を判断するうえで欠かせないものです。デューデリジェンスの結果次第では、買収価格の見直し、契約条件の変更、最悪の場合は買収自体が白紙撤回されることもあります。
デューデリジェンスは、会社を売却する側にとっても極めて重要な意味を持ちます。「買い手がやることだから」と軽視し、必要な準備を怠ってしまうと、結果として不利な条件で契約を締結することになったり、売却のチャンスを逃してしまったりするケースもあります。
本記事では、会社売却を検討する会社オーナーの方に向けて、デューデリジェンスとは何か、どのような視点で行われるのか、そして売却前にどのような準備をしておくべきかについて、分かりやすく解説します。
デューデリジェンスとは何か
デューデリジェンス(Due Diligence)とは、日本語では「適正評価」「買収監査」などと訳される言葉で、M&Aにおいては買い手が売却対象の企業を多角的に調査・分析するプロセスを指します。買い手にとっては、投資対象としての価値を確認し、潜在的なリスクを把握するために不可欠な手続きです。
デューデリジェンスは単なる形式的な確認作業ではなく、会社の全体像を把握するために、財務諸表の正確性や事業の成長可能性、法的リスク、税務上の問題、人材面の課題など、あらゆる側面を細かく検証するものです。買い手はこれらの情報をもとに、最終的な買収価格や条件を決定します。もし重大なリスクや想定外の問題が見つかれば、買収条件の見直し、場合によっては交渉の打ち切りに至ることもあります。
デューデリジェンスを通じて、買い手は「この会社を買うことで自社にどのような価値をもたらすか」「将来的にどのようなリスクが発生する可能性があるか」を精緻に見極めようとします。売り手にとっても、買い手との信頼関係を築くうえで避けては通れない関門です。透明性をもって自社の情報を提示する姿勢が、好条件での売却につながる鍵となります。
このため、会社売却を考える会社オーナーは、デューデリジェンスの目的と内容を理解し、買い手がどのような視点で自社を見ているのかを知っておくことが大切です。これにより、事前に問題点を洗い出し、改善することで、売却条件を有利に進められる可能性が高まります。
デューデリジェンスの主な種類と内容
デューデリジェンスは、買収する対象企業の全体像を正確に把握するため、多岐にわたる分野で行われます。ここでは代表的な種類とその具体的な内容についてご紹介しましょう。
(1)ビジネスデューデリジェンス(事業内容の検証)
事業の競争力や将来性を把握するために行われる調査です。具体的には、市場環境や業界内でのポジション、競合優位性、主要な商品・サービスの収益性、顧客構成、取引先の継続性などが対象となります。売却後の成長性やシナジーを見極めるために、買い手が特に重視するポイントです。
(2)財務デューデリジェンス(数字の裏付け)
過去数年分の財務諸表を中心に、収益構造、費用の妥当性、資産の実在性、簿外債務の有無などを確認します。見かけの数字と実態に乖離がないかを精査するプロセスであり、企業価値の算定にも直結する領域です。売り手は、不動産・動産・債権・有価証券などの資料を提示するだけでなく、借入や預り金・社債・保証・担保など負債についても明らかにしなければなりません。粉飾や不正が疑われる場合には、売却交渉が中断されることもあります。
(3)法務デューデリジェンス(契約・法的リスクの確認)
会社が締結している取引契約、賃貸借契約、雇用契約、各種規程、許認可、訴訟・紛争の有無などを確認します。また、会社の登記情報と実態が一致しているか、株主構成に不備がないかなども重要な検証項目です。この調査では、名義だけ株主名簿に記載する「名義株」や過去の契約トラブルが発覚することもあります。
(4)税務デューデリジェンス(税務リスクの把握)
過去の税務申告の内容、税務調査の有無、節税スキームの合法性、グループ会社間取引の妥当性などが確認されます。過度な節税や形式的な処理などは、将来的な追徴リスクとして買い手の判断に影響を及ぼす可能性があります。一方で、繰越欠損金や含み損がある場合、損金算入が可能なケースもあるため、買い手はM&A後に節税を図ることが可能です。
(5)人事・労務デューデリジェンス(人的資源の把握)
従業員の構成、就業規則、労働条件、退職金債務、未払残業代の有無などを確認します。特に近年はコンプライアンス重視の観点から、労働問題の有無が買い手の評価を大きく左右する傾向にあります。キーパーソンの処遇や退職リスクも注視されます。
(6)ITデューデリジェンス(IT基盤・システムの評価)
近年重要性が増しているのが、ITデューデリジェンスです。業務システムや基幹システムの整備状況、クラウドやセキュリティ環境、ライセンス契約の適正性などが対象です。特にIT依存度の高い企業やDX化に取り組む企業では、買い手側のエンジニアチームが専門的に調査を行うこともあります。
(7)その他のデューデリジェンス
上記の代表的なデューデリジェンス以外にも、環境デューデリジェンス(公害や土壌汚染リスクの確認)、不動産デューデリジェンス(所有・賃借物件の評価)、知的財産デューデリジェンス(特許・商標・ノウハウの保護状況の確認)などが行われることもあります。業種や企業の特性に応じて、調査項目は柔軟に追加されます。
このように、デューデリジェンスは単なる「数字のチェック」にとどまらず、企業のあらゆる側面を総合的に評価するプロセスです。どこかに一つでも大きなリスクがあれば、買い手の判断に大きな影響を与えるため、売却を検討する際には、自社のどの領域がどのように見られるかを把握しておくことが必須となります。
デューデリジェンスでよく指摘されるポイント
デューデリジェンスの現場では、企業価値を損ねるリスクや、買収後に問題となり得る点が数多く指摘されます。なかには、売り手が「まさかこんなところまで見られるとは」と驚くような事例も少なくありません。ここでは、実務上よく問題となる代表的なポイントについて確認しましょう。
契約書や登記情報の不備
中小企業では、取引先との契約が口約束に近い状態である場合や、契約書が更新されず内容が現状と乖離していることがしばしば見受けられます。土地や建物の登記、許認可の名義が現状と一致していないケースもあり、こうした形式的な不備が想像以上に大きなリスクと評価されることもあります。
税務上のグレーな処理
過去に行った節税スキームや、グループ会社間の取引に対する税務処理の曖昧さもよく指摘されます。特に近年は、税務当局の調査が厳しくなっている背景もあり、買い手は将来的な追徴課税の可能性に非常に敏感です。「合法だと思っていた処理が、リスク要因として認識される」という場面も少なくありません。
オーナーの属人的な経営体制
オーナー経営者が営業・財務・人事のすべてを掌握しているような「属人的な経営体制」も大きな懸念点です。買収後にオーナーが退任すると業務が回らなくなるおそれがあり、経営の引き継ぎが困難と判断されれば、買い手は大幅なディスカウントやクロージング条件の厳格化を求めることになります。
数字の信頼性と再現性の欠如
決算書上の数字に一見問題がなくても、売上の大半が一社依存であったり、販促的な特需による一時的な利益であったりする場合、将来の収益再現性に疑問が残ります。買い手は“過去の数字”ではなく“将来の稼ぐ力”を見ています。数字が良くてもその裏付けが弱い場合、評価は伸び悩みます。
労務管理やコンプライアンス上の問題
未払残業、社会保険の未加入、就業規則の未整備など、人事労務面での指摘も増えています。これらは法令違反として是正勧告の対象になる可能性があるため、買い手にとっては深刻なリスクです。企業のガバナンスやモラルの問題として、イメージダウンにもつながりかねません。
これらは、いずれも突然発生するものではなく、日常業務のなかで放置されてきた「見えにくいリスク」です。売却を意識した段階で、これらの点に気付き、早期に手を打てるかどうかが、交渉の成否を大きく左右します。
売り手がデューデリジェンスに備えるべきこと
買い手による厳しい検証に備えるには、早めの準備が不可欠です。売り手自身が事前に自社をチェックする「セルフ・デューデリジェンス」を行い、必要な修正や改善を図ることで、買い手からの評価を高め、取引を円滑に進めることが可能となります。ここからは、売り手が事前に取り組むべきポイントを整理します。
①数年前からの計画的な準備
デューデリジェンスは、短期間で乗り越えられるものではありません。買い手からの評価を高めるためには、会社売却を見据えて2~3年前からの計画的な準備が理想です。日常の業務と並行して体制を整えるには時間がかかるため、早い段階から「いつか売却するかもしれない」という意識を持って経営を行うことが重要です。
②経営情報の整理
まず基本となるのは、経営に関する各種書類の整備です。財務諸表、取引先との契約書、登記簿謄本、就業規則、許認可の写し、取引先や顧客リストなど、会社の実態を説明するうえで必要となる資料は網羅的に整理しておく必要があります。特に財務関係では、過去数期にわたる決算書の整合性や、記載内容の裏付けを丁寧に確認しておくことが必要不可欠です。
③リスクの棚卸しと開示の準備
次に重要なのが、自社の持つ潜在的なリスクを洗い出し、説明できるようにしておくことです。たとえば、訴訟の有無、取引先への過度な依存、社内規程の不備、役員貸付金の存在などは、いずれもデューデリジェンスで指摘されやすいポイントです。これらのリスクを事前に把握し、適切な対応方針とともに開示することで、買い手からの信頼を高めることができます。
④組織・人事体制の見直し
多くの中小企業では、「経営者=会社そのもの」であるケースが少なくありません。属人的な経営スタイルが色濃く残っている場合、買い手からは「オーナー不在でも業務が回るのか」といった懸念を持たれることがあります。そのため、就業規則や雇用契約書の整備、退職金規程や評価制度の明確化など、人事面での基本的な管理体制を見直しておくことが望まれます。キーパーソンの継続雇用や引き継ぎ体制の構築も、売却後を見据えた重要な準備です。
⑤IT・情報管理体制の確認
近年では、IT環境の整備状況も買い手の評価項目に加わっています。業務システムや会計ソフトの使用状況、ライセンスの管理、社内データの保管ルール、セキュリティ対策の有無などが確認対象となります。ITに依存する部分が多い場合ほど、事前にチェックリストをもとに現状を可視化しておくとよいでしょう。
⑥専門家のサポートを得る
このような準備を独力で進めるのは現実的に難しく、抜け漏れが生じやすいのも事実です。そのため、M&Aに精通した税理士・公認会計士・弁護士、あるいはM&Aアドバイザーなどの専門家と連携しながら準備を進めることが重要です。特に初めての売却となる会社オーナーにとっては、第三者の客観的な視点が心強い支えとなり、売却後のトラブル防止にもつながります。
まとめ
デューデリジェンスは、単なる買い手側の「精査」ではありません。買い手からの信頼を勝ち取り、企業価値を正当に評価してもらうための重要なプロセスです。高値での会社売却を実現するには、「見られる前提」で自社を整えておくことが欠かせません。経営者にとって会社の売却は、経営人生を締めくくる“最後の大仕事”であり、その成果が、家族や次世代を守る資産形成や新たな人生設計につながる大きな一歩となります。後悔のない選択をするためにも、早めの準備と信頼できる専門家の伴走を得て、納得のいく形で未来へとバトンを渡していきましょう。
私たちウェルス・パートナーは、富裕層の方の資産運用をお手伝いしております。会社売却後の資産設計や運用戦略についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

株式会社ウェルス・パートナー
ポートフォリオマネージャー
早稲田大学国際教養学部卒業後、大和証券株式会社へ入社。富裕層と会社経営者を中心とした資産運用のコンサルティング業務に従事。顧客の資産全体の最適化や会社経営者への相続対策まで支援をしたいという思いがあり、株式会社ウェルスパートナーに入社。