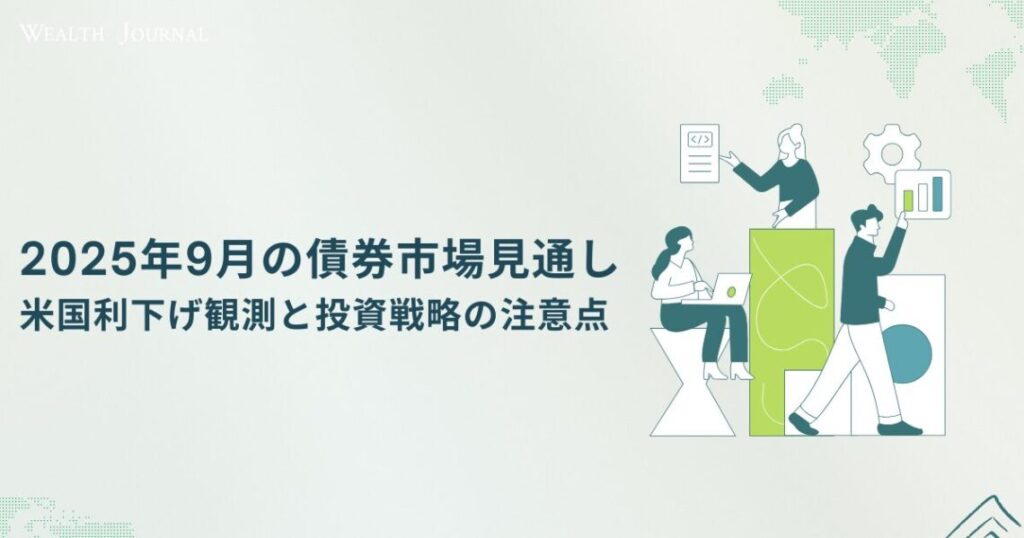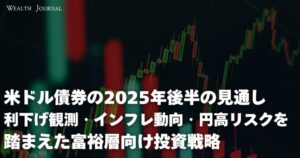はじめに
世界の金融市場は、新たな転換点に立っています。ここ数年、米国を中心とするインフレ高進と利上げ局面を経て、ついに「金利低下局面」へと移行しつつあります。富裕層投資家の多くが直面する問いは、「このタイミングで債券を買うべきか、それとも慎重に様子を見るべきか」というものです。
債券市場は金利が下がれば債券価格は上昇し、利回りは低下するシンプルな構造ですが、実際の投資判断となると、為替の動き、ヘッジコスト、信用リスク、さらには資産全体のポートフォリオバランスまで考慮する必要があり、単純に「金利低下=買い」という判断は要注意です。
特に資産1億円以上の富裕層にとっては「安全資産である債券をどのタイミングで、どの通貨で、どのように保有するか」が長期的な資産防衛に影響します。
株式市場は堅調ながら割高感が漂い、不動産も金利上昇の影響を受けた調整を経て再評価の段階にさしかかっている中で、債券は「分散」と「キャッシュフロー確保」という二つの役割を果たす重要な資産クラスとして、再び脚光を浴びています。
本稿では、2025年9月時点の米国金利動向を中心に、グローバルな債券市場の比較、富裕層投資家が直面する判断ポイント、そして今検討すべき投資戦略を整理することで、「どのように備え、どのように行動するか」を深掘りしていきます。
米国金利動向と債券利回りの変化
現在の債券市場を読み解くうえで、最も注目すべきはやはり米国金利の動向です。世界の資本市場における米国の影響力は圧倒的で、米国債利回りの変化は株式、不動産、さらには為替市場にまで波及します。
2024年から2025年前半にかけて、米国は長引くインフレとその抑制のための高金利政策を強いられてきました。2024年半ばまで政策金利は5.25%〜5.50%という歴史的に見ても高い水準に据え置かれ、企業や家計にとって資金調達コストの負担は大きく、景気減速の兆しが随所に表れ始めていました。しかし、2025年に入り、インフレ率が徐々に低下し、失業率がやや上昇する中で、FRBは慎重ながらも利下げに舵を切りました。9月時点では、政策金利は4.25%〜4.50%まで引き下げられ、昨年の「高金利停滞期」からは明らかに違う局面に入ったと評価できます。
この金利引き下げの背景には、「物価上昇率が2%目標に収束しつつある」という安心感と、「過度な景気失速を防ぎたい」という思惑が共存しています。インフレ率は2022年のピーク時に比べれば大幅に落ち着き、足元では2.3%〜2.5%程度で推移しています。賃金上昇も鈍化し、労働市場の逼迫はやや和らいでいるため、FRBは「インフレとリセッションのバランス」を取るために金融環境を緩めつつあるのです。
長期金利に目を向けると、米10年国債利回りは2024年秋に5%近くまで上昇しましたが、インフレ沈静化と利下げ開始を背景に低下し、2025年9月現在では4%前後に落ち着いています。この水準は依然として歴史的に見れば比較的高いものですが、「ピークからの低下」というトレンドが投資家心理に大きな影響を与えています。特に長期投資家にとっては「今の水準で利回りを確定しておくべきか、それともさらに下がる余地を見込んで長期債に積極的に投資すべきか」という判断が問われています。
債券価格の動きはこうした金利の変化に敏感で、2024年に5%超で国債を購入した投資家は、すでに価格上昇の恩恵を享受しているケースも少なくありません。一方、今から市場に参入する投資家は、利回り水準が下がった状態で購入せざるを得ず、将来のリターンは限定的になる可能性があります。つまり、2025年9月の市場は「早く動いた投資家の勝利が確定した後の局面」にあり、新規投資家は「残された利回りをどの程度享受できるか」という視点で戦略を練る必要があるのです。
ただし、金利低下が直線的に続くと考えるには尚早で、米国は依然として巨額の財政赤字を抱えており、国債発行の増加は長期金利を押し上げる圧力となります。さらに、エネルギー価格や地政学リスクが再びインフレを刺激する可能性もあります。つまり、「短期的には金利は低下基調にある一方で、中長期的には上振れ要因も存在する」という複雑な状況なのです。
また、米国の債券市場は規模と流動性で群を抜いており、世界中の投資家にとっては依然として最も重要な投資先であることに変わりはありません。米国債は世界中で最も信用度の高い資産のひとつとされているため、利回りが低下したとはいえ「資産防衛の柱」としての役割は依然として大きいのです。
さらに、債券投資を検討する際に見落とされがちなのが「タイミングの問題」です。市場は常に先を織り込もうとします。つまり、利下げが今後も続くと予想される場合、その効果はすでに債券価格に反映されていることが多いのです。2025年9月時点で長期債を購入しても、価格上昇の余地は思ったほど残されていない可能性があります。そのため、投資家は「市場がすでに織り込んでいるシナリオ」と「予想外の事態が起きたときのリスク」の両方を冷静に評価しなければなりません。
要するに、米国金利と債券市場の現状は、「チャンス」と「制約」が共存する状況です。利回りは依然として魅力的な水準にある一方で、金利低下局面の恩恵を最大限に享受するのは難しくなっています。だからこそ、今後は「利回りを確定させることによる安定的な収益の確保」と、「金利や市場環境の変化に備えた柔軟性」を両立させる戦略が求められます。
日本・欧州を含めたグローバル債券市場の比較
2025年9月の債券市場を考えるにあたって、米国だけでなく日本や欧州の動向を踏まえることは不可欠です。富裕層にとって資産を「どの通貨で保有するか」は投資収益に直結するテーマであり、米国金利が低下局面に入った今こそ、グローバルに視野を広げることが必要になります。
まず、日本の金融政策を見てみましょう。2024年に日本銀行は長らく続けてきたマイナス金利政策を解除し、短期金利を0.25%に引き上げました。その後も段階的に正常化を進め、2025年9月現在では政策金利を0.50%に据え置いています。消費者物価指数は2%前後で安定しており、急激なインフレ懸念は後退しましたが、金融環境が完全に緩和的だとは言えません。むしろ日本銀行は「過度な円安を是正するために一定の金利水準を維持する」という立場を明確にしており、円金利は依然として低いままながらも、数年前と比べれば「投資先としての存在感」を徐々に取り戻しつつあります。とはいえ、米国や欧州に比べれば利回り水準はかなり低いため、円建て債券だけで資産を運用することは依然として非効率と考えざるを得ません。
一方、欧州に目を向けると、欧州中央銀行(ECB)は2024年以降、積極的な利下げを実施しました。インフレの鈍化と景気減速を背景に、2025年9月時点で政策金利は2.25%程度に低下しています。ドイツ10年国債の利回りもおよそ2.3%と、米国債に比べて魅力度は劣ります。ただし、欧州債券には「安定的なユーロ建て資産」としての意味合いがあり、米ドルに過度に依存したポートフォリオを補完する役割を果たします。とりわけ富裕層にとっては、相続・贈与の際にユーロ建て資産を一部保有していることで国際的な分散をアピールでき、資産承継の観点からも意義があります。
ここで重要になるのが「通貨リスクの扱い」です。米ドル資産は利回りの高さという魅力を持ちますが、為替変動による評価損益が常に付きまといます。円安局面では米ドル建て債券の資産価値が膨らむ一方、円高が進行すればその逆です。たとえば1ドル=140円から120円へと円高が進んだ場合、ドル建て資産の評価額は円換算で15%程度減少します。これは利回り数年分を一気に失う規模のインパクトであり、無視できないリスクです。
為替ヘッジを使えばこうしたリスクを抑えられますが、そのコストは現在でも年率3〜4%に達しています。つまり、米ドル債券が年利4%の利回りを提供していても、フルヘッジをかけると実質利回りは1%前後にまで低下する計算になります。これでは日本国債やユーロ建て債券と大差なくなり、米ドル資産を選ぶインセンティブが薄れてしまいます。したがって、現実的な戦略は「ヘッジ」と「ヘッジ無し」を組み合わせ、為替の変動リスクを部分的に取り込む」というアプローチになります。
このように見ていくと、日本・欧州の債券市場は米国に比べると利回りの妙味は劣るものの、資産の通貨分散という観点では依然として重要です。米国一本足打法のポートフォリオは為替や政策リスクに脆弱であり、円やユーロを適度に組み合わせることで長期的な資産安定性を高めることができます。富裕層の資産設計においては、単に「どの国の債券が最も利回りが高いか」だけを基準にするのではなく、「どの通貨で将来の資産を保有することが、自分や家族の生活や承継にとって最適なのか」を考えることが求められます。
富裕層が直面する投資判断のポイント
富裕層が債券市場に向き合う際、最も重要なことは「単なる利回り追求」ではなく、「資産全体の安定性」と「長期的な持続可能性」をいかに確保するかです。株式や不動産のように価格変動が大きな資産を多く保有する人ほど、債券投資はリスク緩和の役割を持ちます。しかし2025年9月の市場環境では、いくつかの難しい判断を迫られる局面にあります。
まず考えなければならないのは、米ドル建て債券の利回りがすでに低下局面に入っている点です。米10年国債利回りは一時5%を超えたものの、現在は4%前後の水準に落ち着きつつあります。金利がさらに下がれば価格は上昇しますが、すでに大きな値上がりを経験した後であり、今から新規に購入する投資家にとって「キャピタルゲインを狙う余地」は限られています。つまり、この局面では「過去の投資家が享受した利回り確定の恩恵」を再現することは難しく、むしろ「今から買うならどの程度の利回りを確保できるのか」という視点に切り替える必要があります。
次に意識すべきは為替変動リスクです。前述の通り、ドル資産を保有すれば円安が進行した場合に為替差益を得られますが、円高に振れれば価値が一気に目減りします。為替ヘッジを行えばリスクは抑えられるものの、そのコストは年率3%〜4%であり、せっかくの債券利回りを削り取ってしまいます。富裕層が慎重に考えるべきは、「全額を無ヘッジで持つリスク」と「全額をヘッジして利回りを失う非効率」のどちらも避けるという選択肢であり、結果的に部分的にヘッジをかけてバランスを取ることが現実的になります。資産全体で見れば、生活基盤に必要な部分を円建て資産で固め、その上でリターンを狙う分についてドル建て債券を取り入れるという設計が望ましいでしょう。
さらに、信用リスクと流動性リスクも考慮する必要があります。米国債のような安全資産は利回りが下がり、期待できるリターンは限定的になっています。その一方で、社債や新興国債券は高い利回りを提供しますが、発行体の財務健全性や国の政治リスクに左右されるため、不測の事態で急激に債券価格が下落する可能性があります。富裕層にとって最も避けたいのは、資産全体の安定性を崩す「一点集中の失敗」です。ある企業の社債に過度に依存していた結果、信用不安に巻き込まれて資産価値を大きく減らすといったシナリオは、長期的な資産防衛という観点から最も避けるべき事態です。特に、今後数年のうちに相続や事業承継といった資金移動を控えている場合には、「換金性の高さ」、すなわち流動性が投資判断の大きな軸となります。売却したいときに売却できる資産であることは、極めて重要な要素です。
最後に、株式や不動産との資産分散効果について触れます。富裕層の多くは株式市場や不動産投資で一定の成功を収めてきていますが、これらは景気や金利動向に大きく影響を受ける資産です。株式が調整局面に入り、不動産が金利の影響で取引量を減らすような環境では、債券の安定的な利息収入がポートフォリオ全体を下支えすることになります。例えば、株式中心のポートフォリオに30%程度の債券を加えるだけで、リスクをいくらか抑えながら収益構造を安定化させる効果が確認されています。不動産からの賃料収入と債券のクーポン収入を組み合わせれば、生活費や事業資金を安定的に賄うキャッシュフロー基盤を構築することも可能になります。
要するに、2025年9月の富裕層投資家が直面する判断は、「利回りの確保」と「為替変動リスクの扱い」、そして「信用リスクと流動性のバランス」、さらに「資産全体との相互補完性」をどのように調整するかに集約されます。今のタイミングで重要なのは、大きなリターンを狙うのではなく、今後の環境変化に耐え得る安定したポートフォリオを築くことにあります。
2025年9月に検討すべき債券投資戦略
2025年9月というタイミングは、金利が低下局面に入った直後という点で非常に特徴的です。すでに利回りのピークは過ぎ、利下げ効果による価格上昇もかなり織り込まれています。つまり、ここから債券投資を検討する場合は「キャピタルゲインを得る」よりも「今後10年を見据えた安定的なインカムを確保する」視点が重要となります。では、具体的にどのような戦略が有効なのでしょうか。
ひとつは、長期債と中期債をバランスよく組み合わせる方法です。長期債は金利低下の恩恵を最も大きく受けますが、金利反転時には大きな損失を被る可能性があります。一方で中期債は利回りこそ控えめですが、価格変動リスクは限定的であり、数年先の金利水準を見極めながら乗り換えも可能です。富裕層にとっては「一定の利回りを確定しながら、資金需要にも対応できる柔軟性」を持たせることが不可欠であり、10年債と5年債を組み合わせて保有するような戦略が合理的です。相続や事業承継といったライフイベントを控える場合には、中期債を厚めに組み込み、資金流動性を確保する工夫も必要でしょう。
また、満期までの長さを分けて持つのも基本的な手法の一つです。短めと長めをあわせて持っておくと、毎年のように満期が巡り、その時の金利で組み替えることができます。金利がゆっくり下がる方向なら、やや長めの比率を増やして今の利回りを確保し、逆の局面では短めを厚くして次の機会を狙います。全体としての平均の長さを一定の範囲で保つ意識の方が、値動きと再投資の両面を管理しやすくなります。
その他、社債や新興国債券への分散も検討に値します。米国国債に比べて利回りの高い投資適格社債は、信用度の高い発行体を選べば、比較的安定したインカムゲインを得る手段となります。分散投資の一部として社債を10%〜15%程度組み入れることで、全体のリターンを底上げすることが可能です。一方でハイイールド債や新興国債券は、高利回りを提供しますが信用リスクがかなり高く、資産全体を安定させたい場合には「スパイス程度」にとどめておくのが現実的です。例えば全体資産の3%〜5%を新興国債券に配分し、残りは比較的安全性の高い社債や国債で固めるというのが典型的な戦略です。
米ドル建て債券と円建て債券の使い分けも、極めて重要なテーマです。米ドル建て債券は利回り面で魅力がありますが、為替変動リスクを伴います。円建て債券は利回りがかなり低い反面、生活基盤を支える資産としての安定性があります。資産全体を見たときに、米ドル建て債券を中心に据えながらも、相続や日常生活費に充てる資金は円建てで持つといった二層構造を意識することが効果的です。たとえば、全資産の6割をドル建て債券、4割を円建て債券という比率に設定することで、為替変動リスクと生活基盤の安定性をバランスよく両立できるでしょう。
さらに、投資形態として「個別債券」と「ファンド」のどちらを選ぶかも戦略上の重要な論点です。資産規模の大きな富裕層であれば、個別債券を直接購入して満期まで保有し、利息と元本を確実に得る設計が可能です。一方で、流動性や分散の観点からはETFや投資信託の活用も考えられます。特にETFは市場価格で容易に売買でき、状況に応じて素早くポジションを調整できるという強みがあります。実務的には、安定資産を個別債券で構築し、柔軟な部分をETFで運用する「二段構えの戦略」が現実的です。資産の7割を個別債券に、残り3割をETFや社債ファンドに振り分けるといった設計が、一例として考えられるでしょう。
これからの債券投資戦略は「現状の金利水準で利回りをいかに効率よく確定させるか」「将来の金利変動に備えて柔軟性を残すか」「為替変動リスクと信用リスクをどの程度許容するか」を同時に考えなければなりません。大胆なリスクテイクでリターンを追うのではなく、資産全体の安定と長期的な持続可能性を優先することが重要であり、そこにこそ債券投資の本質的な価値があります。
まとめ
2025年9月の債券市場は、富裕層にとって重要な分岐点にあります。米国の金利は高止まりから低下局面に入り、利回りのピークは過ぎつつあります。これからの投資は「価格上昇による短期的な利益」ではなく、「数年にわたり安定した利息収入を確定させる」ことに重点を置くべき時期です。
ただし、利回りの水準だけで判断するのは危険です。米ドル建て債券は依然として魅力的ですが、円高に振れれば数年分の利息が一瞬で失われる可能性もあります。為替ヘッジを利用すればリスクを抑えられるものの、そのコストは高止まりしており、実質利回りを大きく削ってしまいます。こうした状況では、ドル資産と円資産をバランスよく組み合わせ、「ヘッジ」と「ヘッジ無し」を併用する戦略が現実的です。
また、信用度の高い米国債やドイツ国債は依然としてポートフォリオの基盤として重要です。そのうえで、投資適格社債や選別された新興国債券を適度に取り入れることで、リターンを補完することができます。資産全体を安定させつつ、限られた利回りのチャンスを最大限活かすことが期待できます。
特に大切なのは、単なる利回りの追求ではなく、資産全体の安定と承継の準備です。相続や事業承継を控えている方にとっては、換金性や税務上の取り扱いも考慮すべき要素になります。こうした多面的な判断を個人で行うのは難しく、最新の市場環境と税制に精通したIFAやプライベートバンクの助言を受けることが、最終的には大きな差につながります。
2025年9月は「利回り確定のラストチャンス」とも言えるかもしれません。長期的な資産設計を見据え、いまこそ債券投資をどのように組み込むかを真剣に検討すべきでしょう。そしてその決断をより確実なものにするために、ぜひ専門家との対話を始めることをおすすめします。

株式会社ウェルス・パートナー
ポートフォリオマネージャー
早稲田大学商学部卒業後、株式会社群馬銀行へ入社。富裕層と会社経営者を中心とした資産運用のコンサルティング業務に従事。銀行での提案には限界があると感じ、もっと付加価値の高い提案をしたいと思い株式会社ウェルスパートナーに入社。富裕層、会社経営者の資産配分最適化や具体的な金融資産の投資実行サポートを行う。