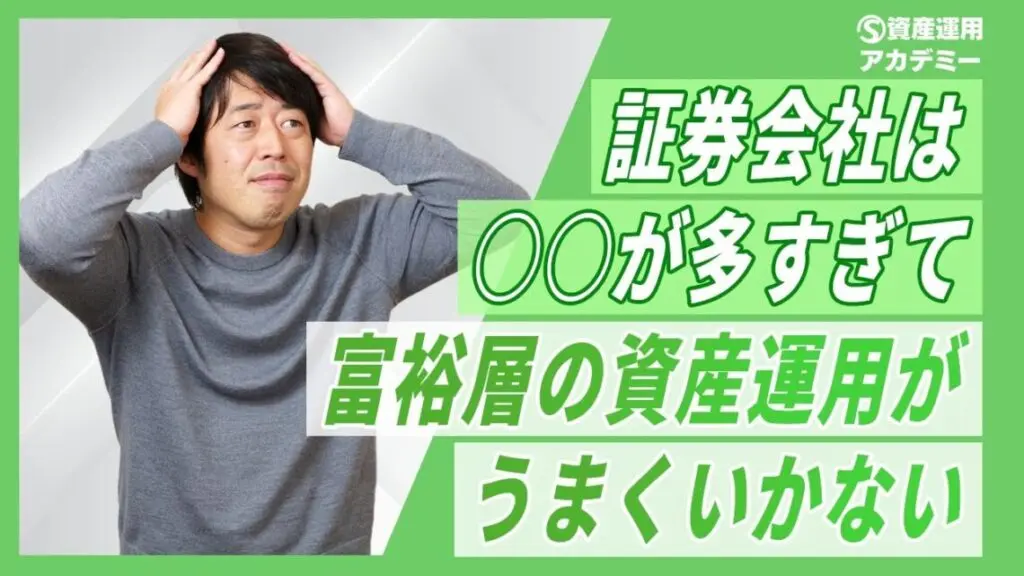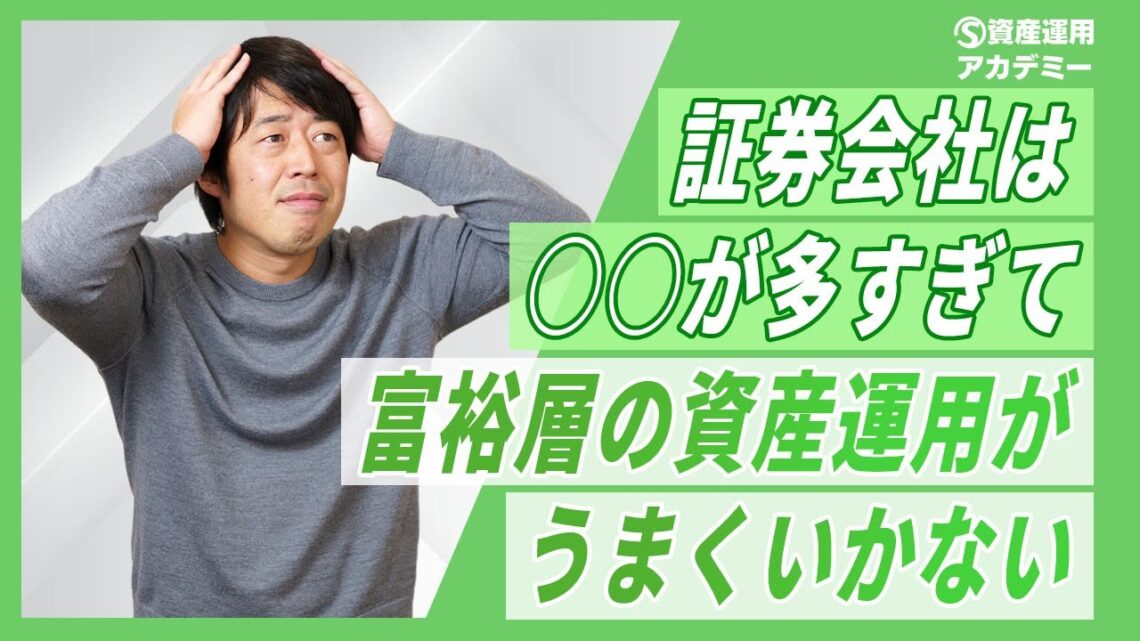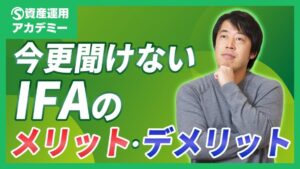目次
はじめに
皆さん、こんにちは。株式会社ウェルス・パートナー代表の世古口です。
今回のテーマは、「富裕層はなぜ証券会社で資産運用すると失敗するのか」です。
富裕層の方の資産運用の一般的な相談先として一番多いのは、おそらく大手の証券会社でしょう。証券マンが富裕層の方の担当について資産運用の提案をするという、対面の証券会社での資産運用がパターンとしては多いと思います。ただし、大体の証券会社での資産運用は明らかに失敗している可能性が高いです。富裕層の方の資産運用を見ていると、そのようなケースが多いと感じられます。今回は、富裕層の方が証券会社で資産運用するとなぜ失敗するのか、その理由について私の見解をお話しします。
失敗する4つの理由
富裕層が証券会社の資産運用で失敗する4つの理由についてご説明します。
理由1)顧客の目的より商品ベースの提案が圧倒的に多い
証券会社は金融商品を作るメーカーでもあり、その作った金融商品を販売する会社でもあります。商品を作る際には製造コストが掛かりますし、その商品を取り入れる導入コストも掛かります。一つの商品を作るのに、ものすごくたくさんのお金が掛かっているわけです。〇〇という投資信託・〇〇というラップ口座を作る、〇〇会社が発行する株式を引き受けるなど、このようなものには人的コストも掛かっており、多くの人が関わっています。
ですから、自社で作った金融商品をどうしても販売して、コストを回収しなければいけません。担当者は、そのプレッシャーによって、お客様がやりたいことや達成したい目的などは二の次で、正直考えていられないのです。販売しなければいけない自社の金融商品がたくさん存在していることによって、どうしても商品ベースの提案が多くなってしまうわけです。
これは、担当者の能力が低いといっているわけではありません。構造的に仕方ないものです。金融商品を作るメーカーと販売会社を兼ねていることによる大きなデメリットといえるでしょう。
お客様としては、自分の目的を達成するために提案してくれている金融商品だと信じて投資することになります。しかし、実際には目的を達成するものではない可能性が高いです。お客様の求めているものと証券マンが売りたいものがミスマッチしており、富裕層の方は資産運用の目的を達成できずに、失敗してしまうケースが多いのではないかと思います。
理由2)数年に一度の転勤で担当者は長期的な提案ができない
証券会社で働いている営業マンと話をすることがよくあります。ほとんどの担当者の方は、数年に一度転勤があり、早いと1~2年で転勤があって、モチベーションが下がると話していました。これは銀行や信託銀行でも同じことがいえますが、1年に1回や数年に1回お客様が代わることは、担当者からすると、長い目線でお客様に資産運用の提案ができないことになります。
1~2年で担当を外れるお客様に対して、5年や10年先を見据えた提案はなかなかできないでしょう。来年にはこのお客さんは別の人が担当していると思うと、長期的な提案をするモチベーションが持てないわけです。
これは、先ほどと同じで構造的な問題といえます。証券会社には、転勤を多くすることによって、お客様と担当者の癒着を防いだり、不正を未然に減らしたりする目的があります。しかし、担当者からすると、お客様に対する気持ちや長期的な提案をしようというものに、どうしても繋がりにくくなってしまっているわけです。
数年ごとの転勤により、お客様の目的を達成するための長期的な提案ができなくなることは、資産運用が失敗してしまう大きな理由の一つではないかと思います。
理由3)ラップや仕組債、短期売買など合理性低い商品が多い
このメディアでもたまに取り上げていますが、証券会社には、経済合理性の低い金融商品が多いという問題があるのではないかと思います。例えば、ラップ口座や仕組債、短期で売買する(今日買って翌日や翌週売る)ものなど、合理性が低い金融商品や取引を提案しないと、ノルマが達成できないという課題です。
これに関しては、構造的な問題というよりは、証券会社のビジネスモデルに根本的な課題があるからといえるかもしれません。証券会社は上場会社なので、どちらかというとお客様の利益よりも株主の利益や会社の収益を優先する傾向にあります。そのようなモチベーションの方が高いことによって、どうしてもこのような金融商品は生まれてしまいますし、それを販売せざるを得ない状況になっていることが多いのではないかと思います。
ですから、合理性が低い商品が多く、それを提案しなくてはいけないという点は、証券会社の大きな問題で、富裕層の方の資産運用が失敗してしまう大きな原因の一つになっていると考えられます。
理由4)資産配分全体を最適化するという発想がない
株、債券、不動産、金などの資産を、それぞれ何割ずつ持つかというのが資産配分です。この資産配分によって資産運用の結果の9割は決まるといわれています。資産配分を最適化することが、資産運用においては一番大事ということは明白ですし、証券会社の担当者も理解していることではあります。ただ、全体を最適化するという発想は、証券会社も担当者も持っていないというのが一般的です。
証券会社からすると、資産全体のことよりも証券会社に預けてくれているお金だけを見て提案していることが多いのではないでしょうか。資産配分全体を最適化する発想がないと、富裕層の方の資産運用が成功することは難しいと思います。
例えば5億円を持っている方が、5,000万円だけ証券会社に預けて、それをどれだけうまく運用したとしても、全体の1割の運用なのでインパクトは小さいでしょう。また、そもそもこの方がいくら持っているかを正確に把握する発想がないように見受けられます。
証券会社に口座を作る際、資産全体でいくら持っているのかを細かく聞かれることはほとんどありません。しかし、本来はこれではいけません。資産全体を把握しなければ、お客様の最適な金融商品の提案はできないはずです。
証券会社は、資産全体を把握することよりも、目先のノルマや販売すべき金融商品を優先しているので、どうしても森ではなく木を見るような提案になってしまいます。これでは、富裕層の方が「資産運用に成功した」と感じることは難しいでしょう。
本日は「富裕層はなぜ証券会社で資産運用すると失敗するのか」という内容でお届けさせていただきました。
https://wealth-partner-re.com/meeting/

株式会社ウェルス・パートナー
代表取締役 世古口 俊介
2005年4月に日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイスのプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。
2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。超富裕層のコンサルティングを行い1人での最高預かり残高は400億円。書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者1万人超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」での情報発信を通じて日本人の資産形成に貢献。医師向けサイトm3.comのDoctors LIFESTYLEマネー部門の連載ランキング人気1位。
メディア掲載情報:「m3.com」「ZUU online」「MONEY zine」「マネー現代」でコラムを連載中