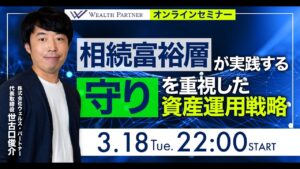目次
はじめに
保有する資産が4億円規模になると、多くの方が次のような疑問や不安を抱きます。
- 今の資産配分は果たして正しいのか?
- インフレや金利変動に資産は耐えられるのか?
- 将来の相続や資産承継に備えるにはどうすればよいのか?
- 安定収益(インカムゲイン)と成長性(キャピタルゲイン)のバランスは取れているのか?
「4億円」という規模は、資産運用を続けるうえで一つの転換点です。たとえば1億円〜2億円規模であれば「守り」に重きを置くだけでも十分なケースがありますが、4億円規模になると「守る」と同時に「増やす」「承継する」といった多面的な運用戦略が求められます。
この記事では、資産4億円をお持ちの方が直面しやすい課題や、ポートフォリオ見直しの具体的な方法、さらに実際の失敗事例やシミュレーション例を交えて、どのように資産を守りつつ効率的に運用していけばよいかを詳しく解説します。
資産4億円を持つ方の典型的な悩みと解決策
資産4億円ともなると、保有するだけでもさまざまなリスクに直面します。
ここでは、資産4億円を持つ人が直面する課題と解決策について解説します。
投資対象の偏り
4億円の資産を築いた方の多くは、これまでの成功体験から特定の資産に強く偏っているケースが多いのが実情です。
- 不動産中心:事業や不動産投資を通じて築いたため、現預金や債券がほとんどない。
- 株式中心:上場企業株や自社株に大きく偏り、マーケット変動に資産価値が左右されやすい。
偏りは資産成長の原動力になってきた一方で、資産防衛の観点からはリスクとなります。
解決策 : 資産配分の見直し、特に債券を組み入れたポートフォリオへの見直しが効果的です。
インカムゲインとキャピタルゲインのバランス不足
- 安定収益が少ない:キャッシュフローが株式配当や不動産収入だけで不安定。
- 成長性に欠ける:債券や定期預金に偏り、インフレで実質的に資産が減少するリスクがある
解決策 : 成長が見込まれる株式・不動産と安定したインカムゲインを期待できる債券を組み合わせた運用が効果的です。
流動性リスク
不動産比率が高すぎて換金に時間がかかる、あるいは株式が多くて価格下落時に現金化できない、といった流動性の問題も大きな悩みです。
解決策 : 資産の一部を現金・預金で保有する、または流通量の多い債券を保有するのが効果的です。
税金・相続への不安
資産4億円の場合、相続税が予想以上に膨らむ可能性があり、計画的な対策を怠ると家族に大きな負担を残してしまいます。
解決策 : 贈与の特例を利用した生前贈与や資産管理会社を活用した相続税対策が効果的です。また、不動産投資を活用して資産の相続税評価額を下げる方法も有効です。
ポートフォリオを見直すべき理由
保有資産が4億円ともなると、マーケットの変化が運用成果や資産額に大きな影響を与えるため、資産配分が偏っている方は、ポートフォリオを見直す必要があります。
ここでは、保有資産4億円の方がポートフォリオを見直すべき理由について解説します。
金利環境の変化
2025年後半以降、アメリカの利下げ局面が意識される中で、米ドル債券の利回りが下がる前に購入する動きが加速しています。
債券は利下げ局面では価格上昇の恩恵を受けられます。資産が株式や不動産に偏っている方は、ポートフォリオを見直し、債券を組み入れるのに適したタイミングといえるでしょう。
インフレリスク
資産を多く保有していても、2%〜3%のインフレが続けば10年で資産価値は2割以上目減りします。実質的に「静かなる損失」となり、資産を守っているつもりで減らしてしまう結果になりかねません。ポートフォリオに株式や不動産を組み入れ、インフレ率を超える運用が必要です。
相続・資産承継への備え
相続はいつ発生するか分かりません。不動産投資には資産の相続税評価額を下げる効果がありますが、資産配分が不動産に偏っていると、相続や資産承継の際にさまざまな問題が生じる可能性もあります。不動産は分割が難しいうえ、流動性が低く換金に時間がかかるためです。資産の一部を現預金で持つほか、ポートフォリオに債券など流動性が高い資産を組み入れる必要があるでしょう。
マーケットの偏り修正
株式相場の上昇で資産全体に占める株式比率が膨らんでいる場合、資産配分の調整を怠ると暴落時の下落幅も大きくなります。資産配分を当初の割合に戻すリバランスが必要です。
代表的なポートフォリオ構成例(シミュレーション付き)
現状の例
現状のポートフォリオが以下だと仮定します。資産構成が株式と不動産に偏っていることが分かります。
- 株式:50%(国内株中心)
- 不動産:30%(賃貸不動産)
- 現金・預金:10%
- 債券:10%
問題点
- 株式偏重で変動リスク大
- 不動産の流動性不足
- 債券比率が低いため安定収益が不足
見直し後の例株式と不動産の割合を減らし、債券と現金・預金の比率を高めた見直した例です。
- 株式:35%(国内株20%、海外株15%)
- 債券:30%(米国債・米ドル建て社債)
- 不動産:20%(賃貸不動産)
- 現金・預金:15%
これにより、期待利回りを年3%〜4%前後、最大下落リスクは半分に減少させることに成功しました。
期待利回り:年率3〜4%前後
最大下落リスク:株式偏重時の▲30% → ▲15%程度に軽減
シミュレーション
ここでは、資産配分ごとのシミュレーションについて解説します。
ケース1:株式・不動産偏重ポートフォリオ
株式・不動産に偏った資産配分例です。
- 株式50%、不動産30%、債券10%、現金10%
- 想定リターン:平均6%
- 想定リスク(最大下落幅):▲30%
株式と不動産が資産全体の80%を占めるため、想定リスク(最大下落幅)が▲30%と大きくなっています。
ケース2:分散型ポートフォリオ
株式と不動産の割合を減らし、債券の割合を増やした分散型ポートフォリオの例です。
- 株式35%、債券30%、不動産20%、現金15%
- 想定リターン:平均5%
- 想定リスク(最大下落幅):▲15%
想定リターン5%を確保しながら、想定リスク(最大下落幅)は半分に減少しています。
ケース3:超安定型ポートフォリオ
債券中心の超安定型ポートフォリオ例です。
- 株式20%、債券50%、不動産20%、現金10%
- 想定リターン:平均4%
- 想定リスク(最大下落幅):▲10%
想定リスク(最大下落幅)が10%と低く、長期的に安定した運用が見込めます。
この比較からわかるのは、「利回りのわずかな低下と引き換えに、資産全体の価格変動リスクが大幅に改善される」という点です。
失敗しやすい事例とその回避策
資産運用では、実際の失敗事例を元に戦略を検討することも重要です。
ここでは、失敗しやすい事例とその回避策について解説します。
資産が不動産に偏りすぎた例
資産4億円のうち3億円を都心不動産に投資した結果、賃料下落とともに売却価格が低迷、現金化まで1年近くかかり、希望通りの価格で売却できませんでした。
回避策:不動産比率を抑え、流通量の多い外国債券や投資信託などで流動性を確保する必要があります。
高配当株に依存した例
「配当利回り5%以上」の高配当株に集中投資したが、減配・株価下落で実際の利回りはマイナスになった。
回避策:債券や不動産など、安定収益が得られる資産を組み入れるべきです。また、株式も配当利回りの高さだけで銘柄を選ぶのではなく、連続増配株や累進配当株を選ぶのも一つの回避策です。
相続対策を先延ばしにした例
相続対策を先延ばしにした結果、約5,000万円の相続税が課される結果となりました。
回避策:贈与の特例を活用した生前贈与や資産管理会社の活用など、早めの相続対策が必要です。
信頼できる相談先の選び方
4億円の資産を守り、成長させていくためには、まず信頼できる相談先を選ぶことが重要です。ここでは、おもな相談先の特徴と注意点について解説します。
- IFA(独立系フィナンシャルアドバイザー)
→ 特定の金融機関に属さないため中立的な立場で資産運用の提案が受けられます。資産配分アドバイス・不動産投資や海外投資・税務相談まで幅広く対応可能です。 - プライベートバンク
→ 包括的な資産運用・管理のサービスが受けられます。投資の選択肢が豊富な反面、手数料が高い場合も多く、満足のいく運用成果が得られない可能性もあります。 - 証券会社・銀行
→金融機関によっては、自社商品に偏った提案が行われる場合もあります。また、担当者の異動によって長期的なサポートが得られないケースも考えられます。
まとめ
資産4億円の運用では「守る」「増やす」「承継する」という3つの目標をバランスよく達成させる必要があります。特にバランスの取れたポートフォリオ構築 は、資産を長期的に維持・成長させるために重要です。
もし現在の資産配分に不安を感じている、あるいは将来の相続や資産承継を見据えて総合的な戦略を立てたいと考えている方は、IFAなどプロに相談するのがよいでしょう。
私たち ウェルス・パートナー では、中立的な立場からお客様の資産背景や個別の状況に合わせたオーダーメイドの資産運用プランをご提案しています。
ぜひ一度、現在のポートフォリオを客観的にチェックし、必要な調整点を明確にすることから始めてみてはいかがでしょうか。

株式会社ウェルス・パートナー
ポートフォリオマネージャー
慶應義塾大学商学部卒業後、三井住友信託銀行株式会社へ入社。
富裕層や会社経営者、地主を中心とした資産運用、相続対策のコンサルティングに従事。お客様と強い信頼関係を築きたいと思い株式会社ウェルス・パートナーに入社。富裕層、会社経営者の資産配分最適化を行う。具体的な金融資産の投資実行サポートや地主への相続対策を主とした税務の最適化、資産管理会社設立、運営のアドバイス、サポート。また会社経営者の資産承継サポートを行う。