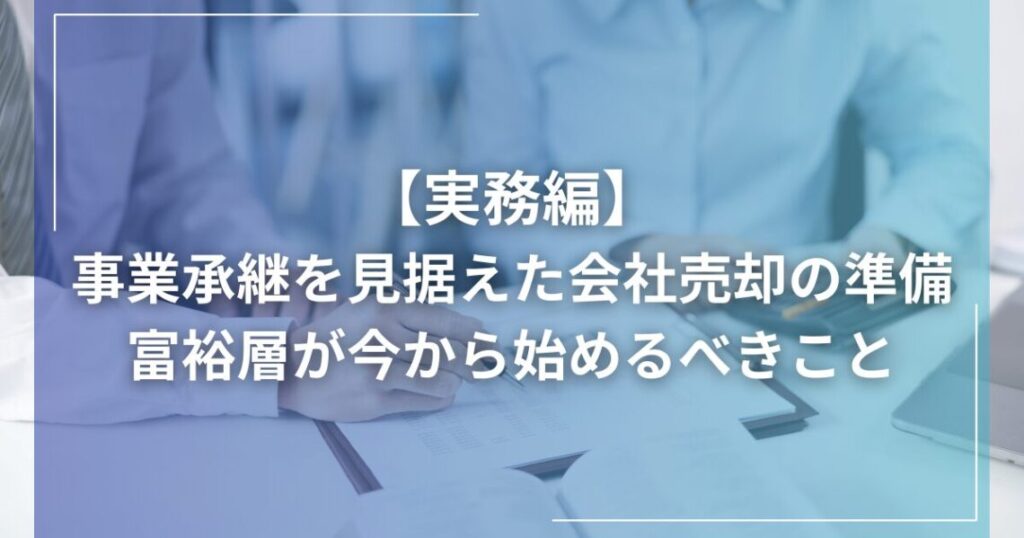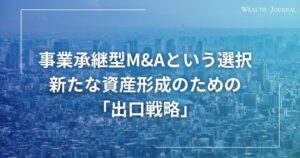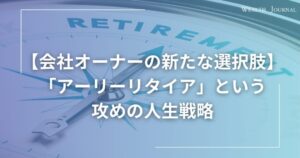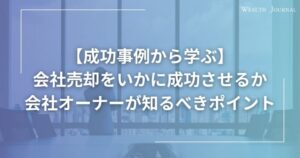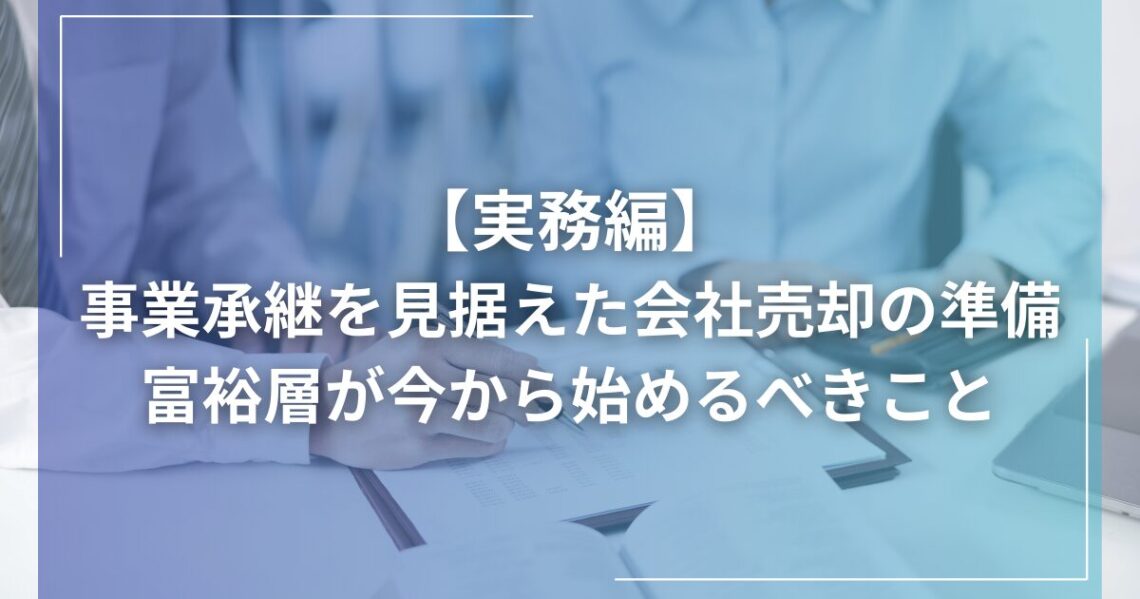
経営者の高齢化が進み、後継者問題に直面する企業が増えています。従来は親族や幹部社員への承継が中心でしたが、近年は「会社売却(M&A)」を通じた第三者承継が注目を集めています。
特に資産規模の大きい会社オーナーにとって、会社売却は単なる「事業の終わり」ではなく、経営と資産を分離し、次世代へ資産を託す戦略的な手段です。
本記事では、事業承継を見据えて会社売却を検討する富裕層の会社オーナーに向けて、今から始めるべき実務的な準備とそのポイントを具体的に解説します。
目次
Ⅰ.富裕層の会社オーナーが「会社売却による事業承継」を選ぶ理由
近年、後継者不足や経営環境の変化を背景に、第三者への会社売却(M&A)を通じた事業承継を選ぶ富裕層の会社オーナーが増えています。なぜ、富裕層は第三者承継による会社売却を選ぶのでしょうか。ここでは、その背景とメリットを3つの視点から見ていきましょう。
1.経営と資産を切り離すという発想
かつての事業承継では、親族や幹部社員への承継が一般的でした。しかし富裕層の会社オーナーの間では、「経営と個人資産を分けて考える」という発想が広がっています。
自社株の評価が高いまま相続を迎えると、多額の相続税が発生しかねません。会社売却によって株式を現金化すれば、資産を整理しながら相続対策を進めることができます。結果として、家族の生活基盤を安定させ、経営リスクから資産を守ることにもつながります。
2.「後継者不在」という現実的課題への対応
日本の中小企業は、後継者不在という深刻な課題に直面しています。帝国データバンクが全国の全業種約27万社を対象に実施した2024年の調査では、後継者が「いない」または「未定」とした企業が14.2万社に上り、後継者不在率は52.1%に達しました。下記の表のように、2018年からは改善傾向にあるものの、この問題は依然として中小企業にとって喫緊の経営課題といえるのです。

出典:https://www.tdb.co.jp/report/economic/succession2024/
多くの経営者が高齢化に直面し、引退を考える時期にあるにもかかわらず、
「子どもが事業を継ぐ意思を持たない(=やりたいことがある)」
「子どもに会社を継がせたくない(=苦労させたくない)」
「社内に適任者がいない・後継者教育ができなかった」
といったケースでは、外部の買い手への承継が合理的な解決策となります。
買い手企業に引き継ぐことで、従業員や取引先との関係を維持しつつ、会社を次の成長段階へ託すことができます。経営者個人にとっても、円満な引退と新たな人生設計のスタートを切るきっかけとなります。
3.会社売却は「終わり」ではなく「次の資産戦略の始まり」
会社売却によって得た資金は、資産管理会社を通じた長期的な運用に生かすことができます。不動産・債券・株式・ファンドなどへ分散投資することで、安定的な収益を得ながら、次世代への資産承継を計画的に進めることが可能です。
つまり、会社売却とは「経営を終える」ことではなく、「家族と資産を守るための新しいステージへの移行」といえるのです。
このように、富裕層にとっての会社売却は「事業の終焉」ではなく、「資産承継の始まり」といえます。経営と資産を切り離し、より長期的な視点で事業承継を設計することこそ、次世代型の富裕層会社オーナーの選択といえるでしょう。
Ⅱ.会社売却の準備ステップ①-会社・個人の資産の明確化と分離
事業承継や会社売却を見据える際、最初に取り組むべきは「会社と個人の資産の線引き」です。長年経営を続けてきたオーナー企業では、会社名義の資産と個人資産が混在しているケースが少なくありません。例えば、会社所有の不動産を自宅や親族の住居として使っていたり、経営者個人の借入で会社資金を補っていたりする場合です。
このような状態のままでは、企業価値を正確に評価できず、買い手がつかない・売却価格が下がるなどのリスクがあります。逆にいえば、「資産と負債の整理」は売却価格を引き上げるための第一歩といえるでしょう。将来的に事業を承継する際も、資産の所在が明確であれば、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。
【実務でやるべきこと】
① 資産の棚卸
まず、会社の貸借対照表をもとに、「会社が保有する資産」「経営者個人が保有する資産」をリスト化します。特に、不動産・有価証券・現預金など、名義と実際の使用状況が一致しているかを確認します。
② 事業と関係の薄い資産を整理
会社が保有していて事業に必要のない資産(遊休不動産や余剰現預金など)は、あらかじめ個人側へ移しておくことが有効です。これにより、会社本体の“事業価値”を明確にし、買い手からの評価も得やすくなります。
③ 役員貸付金・借入金を精算
「役員貸付金」「役員借入金」の精算も忘れてはなりません。帳簿上の貸借関係を放置しておくと、買い手によるデューデリジェンス(企業監査)の段階で大きな減点要素になりかねません。実態に合わせて返済・相殺・債権放棄などの対応を早めに行いましょう。
④資産管理会社を設立
会社売却後の資産管理を効率化し、税務上のメリットや相続対策を実現するためには、資産管理会社の設立が有効です。資産管理会社を通じて売却益や個人資産を一元管理することで、経営資産と個人資産を明確に分離し、税率差を活用したトータルの税負担軽減や、将来的な事業承継・資産承継を見据えた長期的な資産戦略を構築できます。
設立にあたっては、節税だけでなく、事業承継・資産承継の両面を見据えた設計が重要であるため、専門家との連携が不可欠です。ここでは、実際に資産管理会社を設立した製造業の会社オーナーのお話をご紹介します。
【資産管理会社を設立した会社オーナーのコメント】
50代でやや早いとは思いましたが、事業承継を見据え、会社売却を考え始めました。顧問税理士に相談したところ、「売却益が個人に直接入ると高い税率がかかるので、会社売却前に資産管理会社を設立した方がいい」とアドバイスを受けました。そこで、資産管理会社を設立し、本業とは関係のない余剰資金や不動産を合わせた3億円をこの会社に移転し、不動産と債券で運用を始めています。会社と個人の資産を明確に分離することができました。
Ⅲ.会社売却の準備ステップ②-企業価値を高める4つの実務対策
会社売却において、価格を大きく左右するのは「企業価値」です。企業価値とは、単に決算書上の数字だけで決まるものではなく、「今後どれだけ安定的に利益を生み出せるか」という“将来性”に対する評価です。したがって、業績や財務だけでなく、組織体制・顧客基盤・人材など、会社の内側を整えることが何より重要になります。
一方、売却直前に急いでテコ入れしても、買い手には一時的な利益操作と見なされてしまうおそれがあります。理想は売却の3年ほど前から計画的に「見える化」と「平準化」を進めておくことです。この準備が、最終的な売却価格の上振れや交渉の優位性につながります。
【実務でやるべきこと】
① 安定的な収益モデルの構築
売上・利益の一時的な変動が大きい会社は、買い手から「再現性が低い」と判断されます。顧客単価・粗利率・経費率などを定期的に分析し、安定的な収益モデルを整備しましょう。
特定の取引先への依存度が高い場合は、取引先の分散化も検討が必要です。特定の事業や顧客層に依存せず、複数の収益の柱を持つことで、特定の市場が落ち込んでも会社全体のダメージを最小限に抑えられます。 これは、買い手にとって事業リスクが低いと判断され、長期的な安定収益への期待として企業価値の向上に直結します。
② 財務情報の整理
決算書の整合性や会計処理の一貫性は、買い手にとって信頼性を判断する基準です。特に中小企業では、節税目的で経費を厚く計上しているケースが多く見られます。売却を見据える段階では、経営実態を正しく反映した「調整後利益(実質利益)」を把握しておくことが重要です。
この調整後利益の算出は、「企業価値評価(バリュエーション)」の基礎となります。また、過去数年間の財務諸表にわたって一貫した会計処理がなされているかを確認し、説明責任を果たせるよう準備しましょう。
③ 事業継続性を高める組織体制の整備
買い手が最も注視するのは「経営者が抜けた後も事業が回るか」です。後継幹部の育成や権限委譲、業務マニュアルの整備など、属人的な経営体制を脱する仕組みを整えましょう。従業員の定着率を高め、労務管理体制を整備しておくことも、企業価値向上に直結します。
キーパーソンが離脱しないよう、適切なインセンティブ設計や評価制度を導入し、人材面でのリスクを最小限に抑えることが不可欠です。
④ 顧客・契約・許認可の整理
取引先との契約書が未整備だったり、名義変更に制約のある許認可が放置されていたりすると、買い手にとって大きなリスク要因となります。契約書や登記、各種許可証の名義・有効期限をチェックし、更新や再契約を早めに進めましょう。
デューデリジェンス(企業監査)の過程で、これらの契約・法務面での問題が発覚すると、交渉が停滞したり、買収価格が引き下げられたりする大きな要因となります。事前に潜在的なリスクを洗い出し、解消しておくことが重要です。
これらの取り組みは、単なる「売却のための準備」ではありません。会社をよりよい状態で次世代につなぐための経営改善プロセスでもあります。
M&Aの成功は「売却のタイミング」だけでなく、「準備の質と期間」によって決まります。これらの改善を売却の1〜3年前から計画的に行うことが理想です。この地道な努力こそが、結果として、買い手からの揺るぎない信頼を獲得し、交渉において最良の条件を引き出す鍵となるでしょう。
Ⅳ.会社売却の準備ステップ③-売却スキームと税金対策の検討
会社を売却する際、同じ売却価格でも「手元に残る金額」が大きく変わることがあります。その最大の要因が、スキーム(売却の方法)と税務対策です。会社の売却には主に「株式譲渡」と「事業譲渡」という2つの手法があります。
株式譲渡は、会社そのものを丸ごと譲る形で、手続きが比較的シンプルです。一方、事業譲渡は事業資産のみを切り出して譲渡する方法で、譲渡対象の特定や契約の個別変更などが必要になります。
また、株式譲渡で得た売却益には20.315%(所得税・住民税を含む)が課税されます。事業譲渡の場合は会社に法人税が課され、さらにオーナー個人に配当課税が発生するため、実質的な手取りは大きく減る可能性があります。そのため、どのスキームが最も有利かは、会社の資産構成・含み益・繰越欠損金・株主構成などを踏まえて慎重に検討すべきです。
さらに、売却後の資産運用や相続を見据える場合は、「資産管理会社」や「信託」などを活用して税負担を分散させる戦略も有効です。これらの対策は、M&A仲介会社だけでなく、税理士・弁護士・ファイナンシャルアドバイザーといった専門家チームによる総合的な設計が欠かせません。
売却スキーム別の税負担イメージ
| 売却手法 | 主な税金 | 税率(概算) | 特徴 |
| 株式譲渡 | 譲渡所得税 | 約20% | 手続き簡便・会社一体で譲渡可能 |
| 事業譲渡 | 法人税+所得税 | 約30〜40% | 一部事業のみ売却可 |
| 会社分割 | 法人税 | 要件により異なる | 組織再編・承継に有効 |
【実務でやるべきこと】
① 最適な売却スキームを比較検討
株式譲渡・事業譲渡・会社分割など、複数のスキームを比較し、税務・法務・労務・契約面の影響を一覧化します。短期的な税負担だけでなく、売却後の資産形成や相続への波及効果も踏まえて判断しましょう。
② 事前の株価算定と含み益の確認
会社の資産に含み益(帳簿上の価格、すなわち簿価よりも、市場や実態の価値が高い資産)が存在する場合、その含み益は、株式の譲渡方法や価格によって課税対象となる可能性があります。
特に、不動産・有価証券・のれんなどの含み益を正確に把握することが、最適な売却タイミングと譲渡スキームを検討する上で不可欠です。
※のれんとは、築き上げてきた顧客基盤、ブランド力、独自のノウハウ、優秀な人材など、貸借対照表(バランスシート)には載らない無形資産の価値が、買収価格に上乗せされた部分です。
③ 個人の税負担と法人の税負担を総合的に設計
法人税・所得税・住民税・配当課税のバランスを見ながら、どの段階でどれだけ課税されるかをシミュレーションします。オーナー個人と会社の両方を一体として捉えることが、最終的な手取りの最大化につながります。
④ 売却後の資産管理と相続対策を並行して設計
売却益は多額の金融資産となるため、資産管理会社や信託を活用し、所得分散・贈与・相続対策までを一貫して設計することが重要です。早い段階から専門家チームと連携し、「売却後を見据えた税務設計」を進めましょう。
スキーム選択と税務対策は、売却の「出口戦略」でありながら、その成否を左右する最も重要な要素でもあります。税務の知識と経験を持つ専門家の助言を受けながら、早期に戦略的な設計を行うことが、最終的なリターンの最大化につながります。
まとめ
会社売却は、単なる経営の終わりではなく、会社オーナーの資産人生の新たなスタートです。成功の鍵は、売却直前ではなく「今」からの準備にあります。
まずは会社と個人の資産を明確に分け、次に企業価値を高める体制づくりを進め、そして売却スキームや税金対策を具体的に検討する。この3ステップを丁寧に実行することで、売却価格の最大化と税負担の最小化を同時に実現できます。
特に富裕層の会社オーナーにとっては、売却後の資産運用や相続設計まで見据えた一貫した戦略が欠かせません。「会社を高く売る」ことだけにとどまらず、「売却後に資産をどう守り、どう次世代へつなぐか」までを考えることが、真の意味での事業承継といえるでしょう。
私たちウェルス・パートナーは、中立的な立場から、売却益を最大限に活かすためのトータルサポートを提供します。
✅ 資産配分全体の最適化(国内外の金融資産、不動産への具体的な投資戦略)
✅ 資産管理会社を含めた税務の最適化
✅ 包括的な資産管理(ウェルスマネジメント)
売却後の資産運用戦略にお困りの方、最適なアドバイスをお求めの方は、ぜひ一度、当社の個別相談にお申し込みください。ご相談はオンラインでも可能です。まずはお気軽に無料相談をご活用ください。